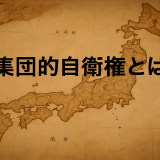国際取引では、誰が運送を手配するのか、保険は誰が付保するのか、輸出入通関や関税・消費税(VAT)はどちらが負担するのかといった取り決めを事前に明確にしておくことが欠かせません。
こうした取り決めがあいまいなままだと、トラブル発生時に「どちらの責任なのか」「どこまで費用を負担すべきなのか」が分からなくなる恐れがあります。
これらの責任・費用・リスクの分担を整理するための国際ルールがインコタームズ(Incoterms)です。2025年11月現在、国際的な標準として広く使われているのは2020年版(Incoterms® 2020)です。
本記事では、実務で特に利用頻度の高いFOB・CIF・DAP・DDPの4条件を中心に、それぞれの役割や特徴に加え、「どのようなケースで選ぶべきか」「2025年時点で注意したい最新のポイント」までを丁寧に解説します。
インコタームズとは?目的と構造

まずは、インコタームズとは何か、その目的と全体構造を整理しておきましょう。
インコタームズ(貿易取引条件)は、国際取引において「輸送費は誰が負担するのか」「関税やVATをどちらが支払うのか」「貨物のリスクはどの時点で買主に移るのか」といった、売主と買主の責任範囲を明確にするための国際ルールです。
国際商業会議所(ICC)が定めたもので、Tasks(誰が何をするか)/Costs(誰がどの費用を負担するか)/Risks(どこでリスクが移転するか)を標準化し、世界共通の“ことば”として使われています。
一方で、インコタームズは所有権がいつ移転するかや、支払条件(L/Cや送金条件など)、契約違反時の損害賠償や解除のルールまでは定めていません。これらは別途、売買契約書や基本契約(フレーム契約)で合意しておく必要があります。
あくまで「物流と通関に関する役割分担」を整理するのがインコタームズの役割だと理解しておくとスムーズです。
現行の2020年版(Incoterms® 2020)は、2025年11月時点でも国際標準として利用されている最新版で、輸送手段に応じて11種類の条件が定められています。
- 海上・内水路輸送専用:FAS、FOB、CFR、CIF
- あらゆる輸送手段に対応(マルチモーダル):EXW、FCA、CPT、CIP、DAP、DPU、DDP
とくにFOB、CIF、DAP、DDPは、コスト管理やリスク分担を検討するうえで実務での利用頻度が高い条件です。本記事ではこれらの条件を中心に、「どこまでが売主の責任で、どこからが買主の負担になるのか」を具体的に見ていきます。
FOB:本船積込みまで売主の責任。海上輸送の基本形

FOB(Free On Board)は、売主が輸出港で貨物を本船に積み込むまでを担当し、積込み後の費用・リスクは買主が負担する海上輸送専用の取引条件です。元々は在来船やばら積み貨物向けに設計されたもので、歴史的に最も多く使われてきた取引条件のひとつです。
しかし現代の国際物流では8割以上がコンテナ輸送と言われ、FOBは実務と定義の乖離が大きい条件として議論されています。特にコンテナ貨物は、実際にはCY(コンテナヤード)で運送人に引き渡した時点でリスクが生じるため、FOBにおける「本船積込み時」まで売主がリスクを負い続けてしまう点が問題視されています。
このためICC(国際商業会議所)は2020年以降、コンテナ輸送に対してFOBではなくFCAの使用が望ましいと繰り返し注意喚起しており、2025年時点でもこの傾向は変わっていません。
特徴
- 売主:本船への積込みまで担当(輸出通関含む)
- 買主:本船積込後の費用・リスクを負担(国際輸送・保険・輸入通関など)
- リスク移転:輸出港で貨物が本船に積み込まれた時点
実務では「現地での積込み作業を売主が手配する必要があるか」「海上保険は誰が加入するのが合理的か」など、コスト管理に直結する判断がFOB選択のポイントになります。また、船積書類(B/L)との整合性や引渡し証明の取得方法も、物流担当者がよく確認する実務論点です。
買主側のメリット
- 輸送手段や海上保険を自由に選べるため、コスト最適化がしやすい
- 輸送全体を自社で管理でき、納期調整もしやすい(船会社・フォワーダーを自社選定可能)
- 売主側の負担が限定されるため、条件交渉がスムーズになりやすい
特に大口取引を行う企業では、FOBを使うことで自社契約の海上運賃を適用し、物流コストの年間最適化を図るケースが多く見られます。
買主側のデメリット
- 本船への積込み完了を確認する必要があり、書類管理の負担が大きい
- 輸送や通関に不慣れな場合、手配ミスや遅延が発生しやすい
- コンテナ輸送では、CYでの引渡しとFOBのリスク移転が一致しないため、責任範囲が曖昧になりやすい
特に2025年の国際物流は、航路の遅延や港湾混雑が続いており、船積み管理の負荷が高まっています。買主側がFOBを選ぶ場合、現地でのフォワーダー連携や進捗管理が十分にできる体制が必要です。
向いているケース
- 在来船・ばら積み貨物など、FOBが本来の想定貨物である場合
- 買主が輸送・保険・通関に十分な知識とネットワークを持っている場合
- 輸送コストを自社で最適化したい企業(船会社契約を活用したい場合)
尚、コンテナ輸送主体の取引では、リスク移転の整合性からFCA(運送人渡し)の利用が国際的に推奨されています。FOBは便利な条件ですが、用途を誤ると売主・買主双方に予期しない負担が生じるため、貨物の種類と物流フローを踏まえて使い分けることが重要です。
FOBについては以下の記事で詳しく解説しております。

インコタームズは取引条件を明確にし、国際取引の効率と安全を高める重要な仕組みです。一方で条件選択を誤ると、予期せぬコスト負担やリスクが発生する可能性があります。
CIF:運賃・保険料込みの価格を提示できる海上条件

CIF(Cost, Insurance and Freight)は、売主が海上運賃と保険料を負担する一方、貨物のリスクは輸出港で本船に積み込んだ時点で買主へ移る海上輸送専用の取引条件です。
売主手配の保険は多くの場合ICC-C(最低限補償)となるため、補償範囲の確認は実務上必須のチェックポイントとなります。
2025年の物流環境では、CIFは「コストが分かりやすい条件」として依然人気があります。しかしFOBと同じく、本来は在来船・バルク貨物向けに設計されたため、コンテナ輸送では実際の引渡し地点(CY)とインコタームズ上のリスク移転地点(本船積込み)が一致しないケースが多く、トラブルにつながることがあります。
特に、航海中の事故で損害が発生した場合、買主側が早期からリスクを負う点や、ICC-Cでは補償範囲が狭い点は、初学者が誤解しやすいポイントです。ICC(国際商業会議所)はコンテナ輸送においてCIP(ICC-A)を優先することを推奨しており、2025年時点でも実務標準として広まりつつあります。
特徴
- 売主:輸出通関、本船積込み、海上運賃と保険料を負担
- 買主:輸入通関以降のすべての手続き・費用を負担
- リスク移転:輸出港で本船に積み込んだ瞬間
- 保険はICC-Cが一般的で、補償範囲の見直しや追加が必要な場面も多い
- 信用状(L/C)取引と相性がよく、書類取引の整合性を取りやすい
実務では、CIF価格をそのまま見積基準にできるため、サプライヤー比較がしやすいという特徴があります。ただし「価格の見やすさ」と「リスクの取り扱い」は別問題であり、特にコモディティ貨物や長距離航路では保険条件の改善(ICC-Aへのアップグレード)の交渉が重要になります。
買主側のメリット
- 輸入港までの費用が明確になり、総コストを把握しやすい
- 海上保険の手配が不要で、初めての輸入でも導入しやすい
- CIF価格(港渡し価格)を基準に複数社をフェアに比較できる
特に中小企業の輸入では、物流手配の負担を減らせる点が評価され、最初に選ばれやすい条件です。
買主側のデメリット
- 売主手配の保険はICC-C(最低限補償)が多く、補償不足の可能性がある
- リスクは本船積込み時点で買主に移るため、航海中の事故は買主の負担
- 保険金請求が買主側で手間になる場合があり、事前に条件確認が必要
航路によっては海難事故・港湾混雑・積替えリスクが高い地域もあるため、2025年の国際輸送では保険条件のグレードアップを前提に交渉するケースが増加しています。
向いているケース
- 輸入港までの費用を事前に正確に把握したい場合
- 海上保険や輸送に不慣れで、売主側の手配に任せたい場合
- 信用状(L/C)を利用する取引や、書類整合性が重要な案件
ただし、コンテナ貨物では実務とリスク移転が一致しないため、ICCはCIP(ICC-A)を優先することを推奨しています。CIFを使う場合は、保険条件の調整とリスクの正確な理解が不可欠です。
CIFについては以下の記事で詳しく解説しております。

DAP:最終配送先まで届けるが、通関は買主が行う

DAP(Delivered at Place)は、売主が買主の指定した場所(倉庫・工場・物流センターなど)まで貨物を届ける取引条件で、国際輸送から現地配送までの手配・費用をすべて売主が負担します。
一方で、輸入通関と関税・VATの支払いは買主の責任であり、この役割分担がDAPの最大の特徴です。複数輸送手段(海上+トラック、航空+宅配など)を組み合わせるケースや、越境EC・サンプル輸送のように柔軟な配送が必要な場面でも広く採用されています。
また、DPU(荷下ろし後引渡し)とは異なり、DAPでは荷下ろしは売主の義務ではない点に注意が必要です。納品現場の設備(フォークリフト・ドックレベラー等)や、荷下ろし責任の所在を事前に確認しておくことで、到着後のトラブルを防ぐことができます。
なお、2025年はEUのICS2や米国のAMSなど、事前通関データの厳格化が進んでおり、DAPを採用する場合でも買主側が通関情報を正しく提供できる体制が不可欠になっています。
特徴
- 売主:出荷〜買主指定地までの国際輸送・国内配送をすべて手配(海上・航空・トラックを含む)
- 買主:輸入通関および関税・VATの支払いを担当
- リスク移転:買主指定地で貨物を引き渡した時点(荷降ろし前)
- 荷降ろしは売主の義務ではない(荷降ろし込みを希望する場合はDPUを使用)
DAPは「最終配送まで任せたい買主」と「通関リスクを負いたくない売主」の双方のニーズを満たす、中間的かつ柔軟性の高い条件です。
買主側のメリット
- 倉庫や工場まで届けてもらえるため、輸送手配の負担が大幅に軽減
- 納品場所が固定されている場合、物流管理が容易
- 自社は輸入通関のみに専念でき、役割分担が明確になる
特に、現地のトラック手配が難しい地域(アフリカ・中東など)では、DAPを選ぶことで配送リスクを減らしやすくなります。
買主側のデメリット
- 輸入通関に不慣れな場合、遅延・追加費用・トラブルの原因となる
- 輸入申告内容に誤りがあると、最終配送に影響が出る
- 関税・VATは買主負担のため、到着時のキャッシュフロー管理が必要
なお、VATの即時還付制度がない国や税関の検査が厳しい国(インド、ブラジル等)では、買主側の税負担・手続き負担が大きくなる点にも注意が必要です。
向いているケース
- 買主が輸入通関の知識・経験を持っている場合
- 納品先が固定されており、売主が輸送計画を立てやすい場合
- 海上+トラックなど、複数の輸送手段を組み合わせる必要がある取引
DAPは「輸送は任せたいが通関は自社で管理したい」企業に最適な条件です。物流の柔軟性とコスト管理の両立を図りたい場合に有効な選択肢となります。
DAPについては以下の記事で詳しく解説しております。

DDP:すべて売主が手配・負担する完全対応型

DDP(Delivered Duty Paid)は、輸送・輸出入通関・関税・VATなど、あらゆる手続きと費用を売主が負担する取引条件です。インコタームズの中でも最も売主の責任範囲が広いことで知られ、買主は基本的に「受け取るだけ」で取引を完結できます。
越境ECやD2Cビジネスでは、購入者に追加請求が発生しないため顧客体験が向上し、欧米向け取引のスタンダードになりつつあります。ただし売主は仕向国の税制・電子申告制度(ICS2/AMSなど)・VAT登録の要否など、コンプライアンス面で高度な対応が不可欠です。
特に2025年8月の米国デミニミス(免税枠)規定の廃止により、米国向け越境ECではDDPが実質的な必須条件となり、事前の関税計算・電子申告・現地配送手続きの精度がこれまで以上に求められます。
特徴
- 売主:出荷〜買主指定地までの配送、輸出・輸入通関、関税・VAT・手数料をすべて負担
- 買主:貨物を受け取るだけで完了(追加手続きなし)
- リスク移転:買主指定地での引き渡し時点
- 売主は現地の税制・VAT番号・電子申告制度に精通している必要がある
配送から税務対応まで売主が一括管理するため、B2B・B2Cともに「トラブルを最小化したい」取引で多く採用されています。
買主側のメリット
- 輸送・通関の負担がほぼゼロで、海外取引の経験が浅くても安心
- 総費用が事前に確定するため、予算管理が容易
- B2Cでは追加請求がないため顧客満足度が向上(カート離脱率の低下にも寄与)
買主視点では「最も安心して受け取れる条件」であり、導入企業が増えています。
買主側のデメリット
- 売主がすべての費用を上乗せするため、商品単価が上がりやすい
- 売主が仕向国の通関実務に不慣れだと、遅延・追加費用のリスク
- 税務・品目情報(HSコード・原産地)を正確に提供する必要がある
特に食品・化粧品・医療関連品目は規制が厳しいため、情報提供のミスがあると大幅な遅延につながります。
向いているケース
- 買主が輸入通関に不慣れ、または通関リソースが不足している場合
- 売主が現地の物流・通関パートナーを確保し、包括的に対応できる場合
- 越境EC(特に米国・EU)で、購入者に追加請求を発生させたくない場合
DDPは「買主の利便性を最大化」できる一方、売主側のコンプライアンス負荷が最も大きい条件です。事前にVAT登録の要否、関税計算方法、輸入規制などを確認し、契約書上で責任範囲を明確化しておくことが重要です。
DDPについては以下の記事で詳しく解説しております。

その他の7条件の概要(一覧)
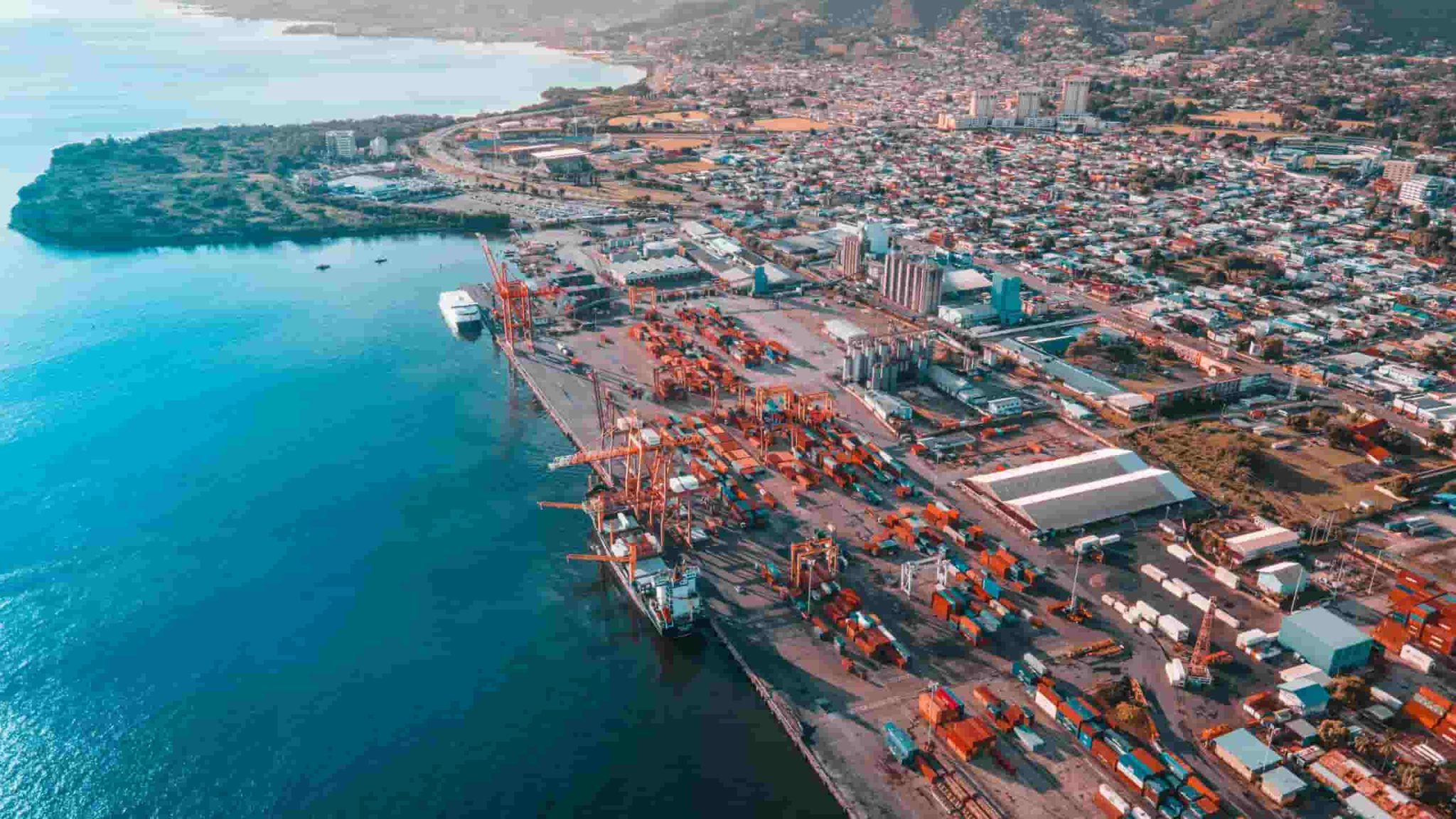
FOB・CIF・DAP・DDP以外にも、貨物の種類・輸送手段・企業の体制に応じて選べるインコタームズが7種類あります。実務では「どの地点で引き渡し(リスク移転)となるか」「誰がどこまで手配するか」を正しく理解して使い分けることが重要です。
-
EXW(Ex Works/工場渡し)
売主の拠点(工場・倉庫)で引き渡し、それ以降の輸送・通関はすべて買主負担。
売主の負担が最小で、買主の実務負荷は最大。初心者の国際取引にはやや不向き。 -
FCA(Free Carrier/運送人渡し)
売主が買主指定の運送業者に貨物を引き渡す条件。コンテナ輸送に最適で実務で最も使いやすい。
L/C(信用状)取引と相性が良く、FOBの代替として推奨される。 -
CPT(Carriage Paid To/輸送費込み運賃渡し)
売主が指定地までの輸送費を負担。ただしリスクは運送人引き渡し時に買主へ移転。
費用負担とリスク移転のタイミングが異なる点が注意ポイント。 -
CIP(Carriage and Insurance Paid To/輸送費・保険料込み運賃渡し)
CPTに保険手配が加わり、売主が輸送費+保険料(ICC-Aが原則)を負担。
高額品や精密機器など、広範な補償が必要な貨物に最適。 -
DPU(Delivered at Place Unloaded/荷下ろし後引渡し)
売主が指定地まで輸送し、さらに荷下ろしまで行う唯一の条件。
倉庫納品や重量物のプロジェクト貨物で便利。荷下ろし費用・作業リスクは売主負担。 -
CFR(Cost and Freight/運賃込み本船渡し)
売主が輸入港までの運賃を負担(CIFの保険なし版)。
リスク移転は本船への積込み時点で買主。海上輸送専用。 -
FAS(Free Alongside Ship/船側渡し)
売主が輸出港で貨物を本船の横(岸壁など)に届ける条件。積込みは買主の責任。
バルク貨物・重量物など特殊船積みに使われる。
FOB/CIF/DAP/DDPの比較早見表

輸送費や保険の負担、輸出入通関の手配、そして万が一の事故時にどちらがリスクを負うのか——これらは貿易条件によって大きく異なります。
以下の早見表では、国際取引で特によく使われるFOB・CIF・DAP・DDPの4つの主要条件について、買主/売主の責任範囲をひと目で比較できるよう整理しています。
| 条件 | 輸送費 | 保険 | 輸出通関 | 輸入通関 | 関税 | リスク移転 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOB | 買主 | 買主 | 売主 | 買主 | 買主 | 本船積込時 |
| CIF | 売主 | 売主 | 売主 | 買主 | 買主 | 本船積込時 |
| DAP | 売主 | 売主 | 売主 | 買主 | 買主 | 指定地引渡時 |
| DDP | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 売主 | 指定地引渡時 |
まとめ
インコタームズは、国際取引における責任の所在や費用負担、リスク移転のタイミングを明確化するための重要なルールです。特にFOB、CIF、DAP、DDPは実務で頻繁に利用されるため、それぞれの特徴と違いを正しく理解し、自社の体制・取引相手・取引国の規制に合わせて最適な条件を選ぶことが欠かせません。
インコタームズの選び方ひとつで、物流コスト、通関負荷、保険範囲やリスク管理の難易度が大きく変わります。複雑な輸送や複数モードの組み合わせ、税制の違いが関係する場合は、国際物流や貿易実務に精通した専門家に相談することが有効です。
本記事が、インコタームズの理解向上と、安全かつ効率的な貿易取引の実現に役立てば幸いです。