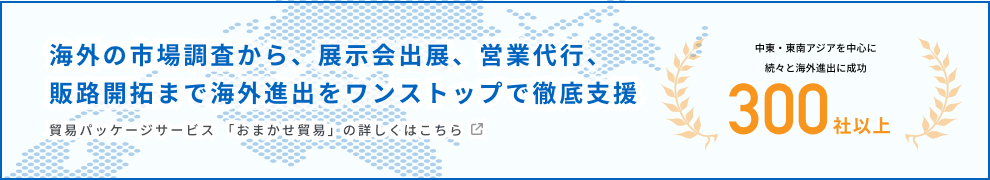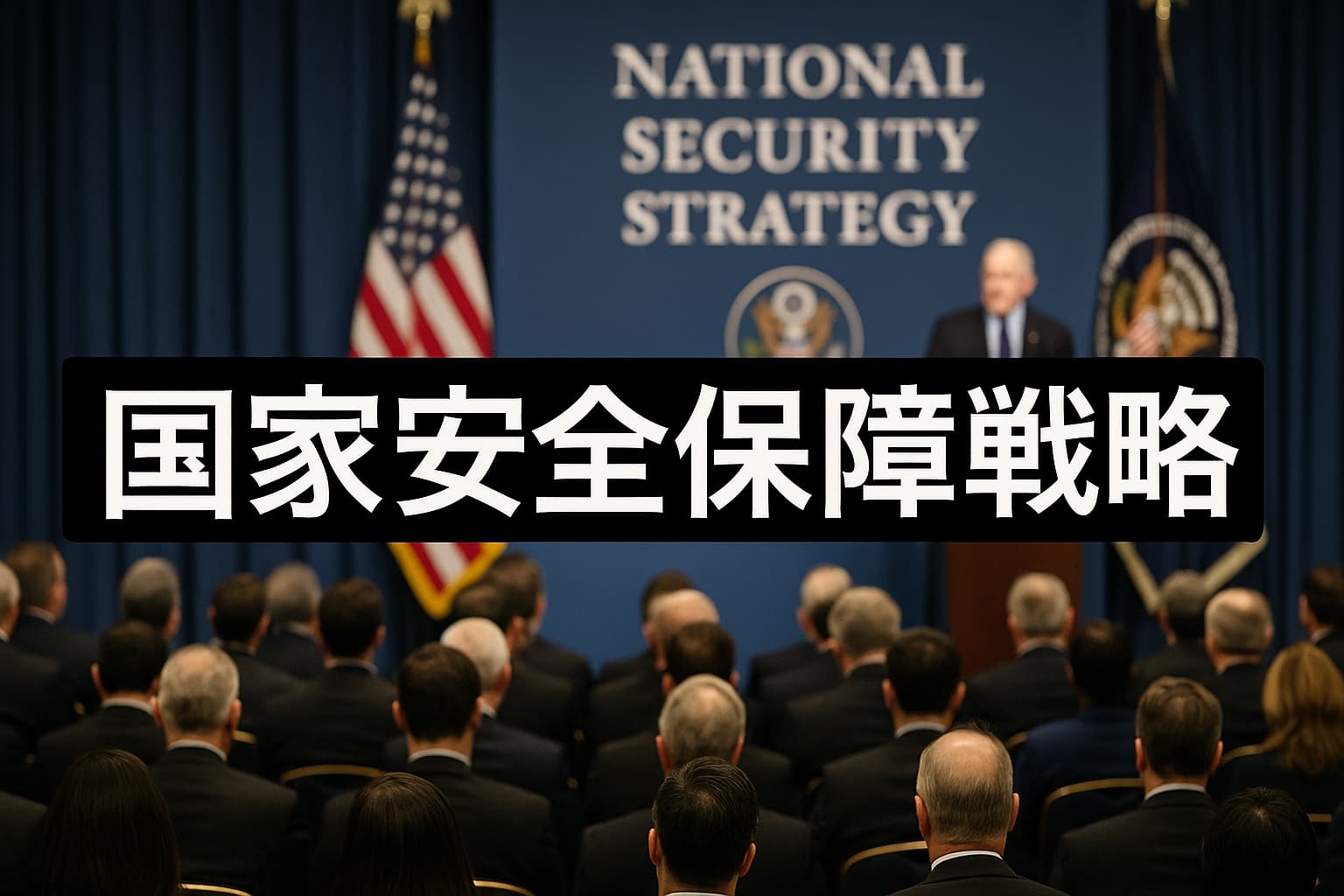2025年1月20日にドナルド・トランプ氏が第47代米国大統領に再任し、「アメリカ第一主義(America First)」を掲げ、貿易赤字の削減を最優先課題としています。これに伴い、日本を含む各国との貿易交渉が再び活発化し、自動車や農産品をめぐる協議が進められています。
特に、日本との貿易協定の見直しや追加関税の動向が注目されており、今後の経済関係に大きな影響を与える可能性があります。
本記事では、トランプ政権の貿易政策が日本に及ぼす影響について、主な5つのポイントを解説し、今後の展望を考察します。
最新の貿易実務・政策動向については、X(旧Twitter)でも随時発信中です。ぜひ @bouekidotcom をフォローして、海外展開に関わる情報をチェックしてください。
1. 日米貿易摩擦の再燃

トランプ政権は米国の貿易赤字を問題視し、日本の自動車輸出を標的にしています。2025年2月13日、トランプ大統領は「相互関税」の導入を指示し、日本にも適用される見通しです。
これにより、日本車の価格が上昇し、米国市場での競争力が低下する可能性があります。さらに、4月には自動車関税の追加導入を検討しており、最大25%の関税が課される可能性も指摘されています。
こうした動きは、1980年代の日米貿易摩擦を想起させ、当時の自主規制のように、日本メーカーが輸出抑制や米国での生産拡大を求められる可能性があります。
貿易摩擦とは、一国の輸出が他国の産業に影響を及ぼし、経済的不均衡を生じさせることで対立が生じる現象を指します。特に、米国は貿易赤字の削減を目指し、日本からの輸入が米国企業の競争力を損なうと主張してきました。
1980年代の日米貿易摩擦では、日本車の米国市場での成功が米国の自動車業界に打撃を与えたとされ、日米間の厳しい交渉の結果、日本企業は米国内での生産を拡大することを余儀なくされました。今回の貿易摩擦も同様に、日本の自動車産業が大きな影響を受ける可能性があります。
特にEV市場では、米国政府が国内生産を優遇する政策を進めており、日本企業は米国でのEV生産強化を迫られるでしょう。対応策として、日本企業は生産拠点の分散やEU・東南アジア市場の強化を進め、米国市場への依存度を下げる必要があります。
今後、日本政府と企業は、米国の政策変更を注視しながら貿易戦略を見直し、貿易摩擦の激化を回避するための外交交渉や経済対話を強化することが求められます。

2. 日米貿易協定の見直し

2019年に締結された日米貿易協定では、日本が米国産農産物の関税を引き下げる一方、米国は日本車への追加関税を見送りました。しかし、トランプ政権はこの協定の見直しを示唆し、自動車分野での関税引き上げや農産品市場のさらなる開放を要求する可能性があります。
特に、自動車貿易に関しては、日本市場における非関税障壁の撤廃や、米国内での現地生産拡大を求める圧力が強まることが予想されます。
さらに、農産品分野では、米国は牛肉・豚肉の輸入枠拡大や関税のさらなる引き下げを要求する可能性があり、日本の農業関係者にとって大きな懸念材料となります。特に、日本がCPTPP(包括的および先進的環太平洋パートナーシップ協定)や日EU経済連携協定(EPA)で他国と締結した関税条件と比較して、米国がさらなる優遇を求めることが想定されます。
日本の対応策として、多角的な貿易戦略の強化が不可欠です。自動車業界ではEV(電気自動車)生産の強化や、EU・東南アジア市場の開拓を進め、米国市場依存を軽減する必要があります。
また、農産品交渉では、日本の農業を保護しながらも、米国とのバランスを取るため、WTOのルールを活用しつつ交渉を進めることが重要です。
今後の日米交渉の行方次第では、日本企業の輸出戦略や国内産業政策に大きな影響を与える可能性があり、慎重な対応が求められます。
3. TPP離脱後の日本の対応とCPTPPの役割

2025年2月現在、米国は依然としてTPP(環太平洋パートナーシップ協定)への復帰を示しておらず、日本はCPTPP(包括的および先進的TPP)の枠組み強化に注力しています。2024年12月15日、英国が正式にCPTPPに加盟し、初の欧州メンバーとして参加しました。
これにより、CPTPPは12カ国体制となり、約6億人の市場規模を持つ自由貿易圏へと拡大しました。しかし、米国の不参加により、経済圏としての影響力は依然として限定的です。
日本は、韓国や台湾、タイなどの新規加盟国の受け入れを推進し、CPTPPのさらなる拡大を目指しています。
一方で、中国も加盟を申請していますが、知的財産権の保護や国有企業の扱いなどの条件を満たす必要があり、慎重な対応が求められます。
CPTPPの拡大は、米国が市場競争で不利になる可能性を高め、再加入を検討する圧力となるかもしれません。
また、日本は米国との個別の経済連携を強化するため、2023年に締結された「日米デジタル貿易協定」などを活用し、将来的な米国のCPTPP復帰への道を模索しています。
さらに、日本企業はCPTPP加盟国間での市場拡大を活用しつつ、欧州や東南アジアとの貿易関係を強化することが重要です。

今後、日本はCPTPPの拡大と米国への働きかけを両立させ、安定した貿易環境の構築に努める必要があります。
トランプ政権は米中貿易戦争を再燃させ、中国製品への追加関税や半導体・ハイテク分野での規制を強化しています。
これにより、米中両国と関係の深い日本企業も間接的な影響を受けており、特にサプライチェーンの混乱や輸出減少が懸念されています。
例えば、日本の電子部品メーカーは、中国経由で米国に輸出するルートが制限されることで、米中間の貿易摩擦の影響を直接受ける状況にあります。
これに対応するため、多くの日本企業が生産拠点の分散を進め、中国依存を減らす動きを強化しています。具体的には、東南アジアやインドへのシフトが加速しており、タイやベトナムでは新たな工場の設立が進んでいます。
また、日本政府も「経済安全保障推進法」などを通じて、重要産業の国内回帰や友好国とのサプライチェーン強化を支援しており、これにより日本企業の中国離れが加速する可能性があります。
しかし、中国市場の規模を考慮すると、完全な撤退は現実的ではなく、リスク管理をしながら現地事業を維持する企業も少なくありません。
今後、日本企業は米中対立の長期化を前提に、柔軟な事業戦略を求められるでしょう。

5. 日本企業の対米投資が増加

トランプ大統領は日本企業に対し、米国内での生産拡大と投資強化を求めています。特に自動車業界では、対米投資が加速しており、トヨタはケンタッキー州の工場拡張に数十億ドル規模の投資を実施。ホンダも米国内に電気自動車(EV)の開発拠点を設置し、現地生産を強化しています。
こうした動きの背景には、米国内の雇用創出と、関税や規制強化を回避する狙いがあります。さらに、EVや半導体分野でも対米投資が活発化。ソニーは米国での半導体工場の展開を検討し、トヨタはEVバッテリーの生産施設を新設する計画を発表しました。
また、日本政府も経済安全保障の観点から、対米投資を通じてサプライチェーンの強化を進めています。ただし、米国での生産拡大はコスト増につながるため、日本企業には慎重な投資判断が求められます。
今後も、日本企業は米国市場での競争力を維持しつつ、貿易摩擦を回避するために対米投資を継続すると考えられます。

今後の展望と課題:トランプ政権と日本経済の行方

トランプ政権の貿易政策は、日本にとって引き続き大きな試練となっています。
こうした貿易摩擦を回避し、日米関係を安定させるためには、複数の戦略的対応が求められます。
自動車貿易の不確実性と対応策
米国の貿易政策は今後も変化する可能性があり、日本の自動車メーカーは関税政策や電気自動車(EV)補助金の見直しに影響を受け続けることが予想されます。
特に、トランプ政権はEV政策の大幅な変更を示唆し、化石燃料を使用したエンジン車への支援を強化する方針を打ち出しており、日本のEV戦略にも影響を与える可能性があります。
これに対応するため、日本の自動車メーカーは市場の多角化を進め、EUや東南アジア市場への輸出拡大を図ると同時に、米国内での現地生産を強化し、関税リスクを軽減する必要があります。
CPTPPの拡大と多国間貿易の強化
日本はCPTPPの主導国として、経済圏の拡大を進めることが重要です。すでに英国が加盟を果たしましたが、今後は韓国、台湾、タイなどの新規加盟を促進し、貿易機会を増やすことが求められます。
一方で、米国の不参加により経済圏としての影響力が制限されているため、新規加盟国の受け入れを進めつつ、米国の再加入を促す外交交渉を強化することが不可欠です。
日米間の経済対話の強化
突然の関税措置や市場ルールの変更に備え、安定した貿易関係を維持することが不可欠です。特に、自動車・農産品・ハイテク産業をめぐる交渉では、日米間での対話を継続することが重要となります。
これに対応するため、日本は定期的な経済対話の場を設け、貿易摩擦の未然防止策を強化する必要があります。具体的には、WTO(世界貿易機関)のルールを活用しつつ、二国間の貿易協議を通じて日本企業の利益を保護する体制を構築すべきです。
今後、日本は自動車貿易の安定化、CPTPPの拡大、日米経済対話の強化を三本柱とした戦略を進め、米国との関係を維持しながらグローバル市場での競争力を確保することが求められます。
まとめ:日本の貿易・経済戦略の未来
トランプ政権の再任により、日本の貿易環境は大きな転換期を迎えています。日米貿易摩擦の再燃、貿易協定の見直し、TPP離脱の影響など、日本企業にとって対応が不可欠な課題が山積しています。
こうした貿易政策の変動は企業経営に直接的な影響を及ぼすため、最新の動向を把握することが求められます。特に、関税の変化や輸出入規制の強化により、新たな取引先の開拓やサプライチェーンの見直しが急務となります。
貿易の変動は企業経営にも大きく影響するため、専門家の意見を参考にしながら適切な対策を講じることをおすすめします。
海外販路開拓をゼロから始めるなら『おまかせ貿易』
『おまかせ貿易』は中小企業が、低コストでゼロから海外販路開拓をするための"貿易代行サービス"です。大手商社ではなしえない小規模小額の貿易や、国内買取対応も可能です。是非一度お気軽にお問い合わせください。