近年、製造拠点や輸出入の拠点として世界的に注目を集めているベトナム。多国籍企業の進出やサプライチェーンの再構築が進む中、貿易量も年々拡大し、貿易制度に関する実務的な理解の重要性が高まっています。
中でも「関税制度」は、取引コストや物流体制に大きく関わるため、現地ビジネスを展開する上で避けては通れないテーマです。
本記事では、ベトナムの関税制度の仕組み、最新の制度改正、FTA活用のポイント、そして輸出入ビジネスにおける実務上の注意点までを総合的に解説します。
ベトナムの関税の種類
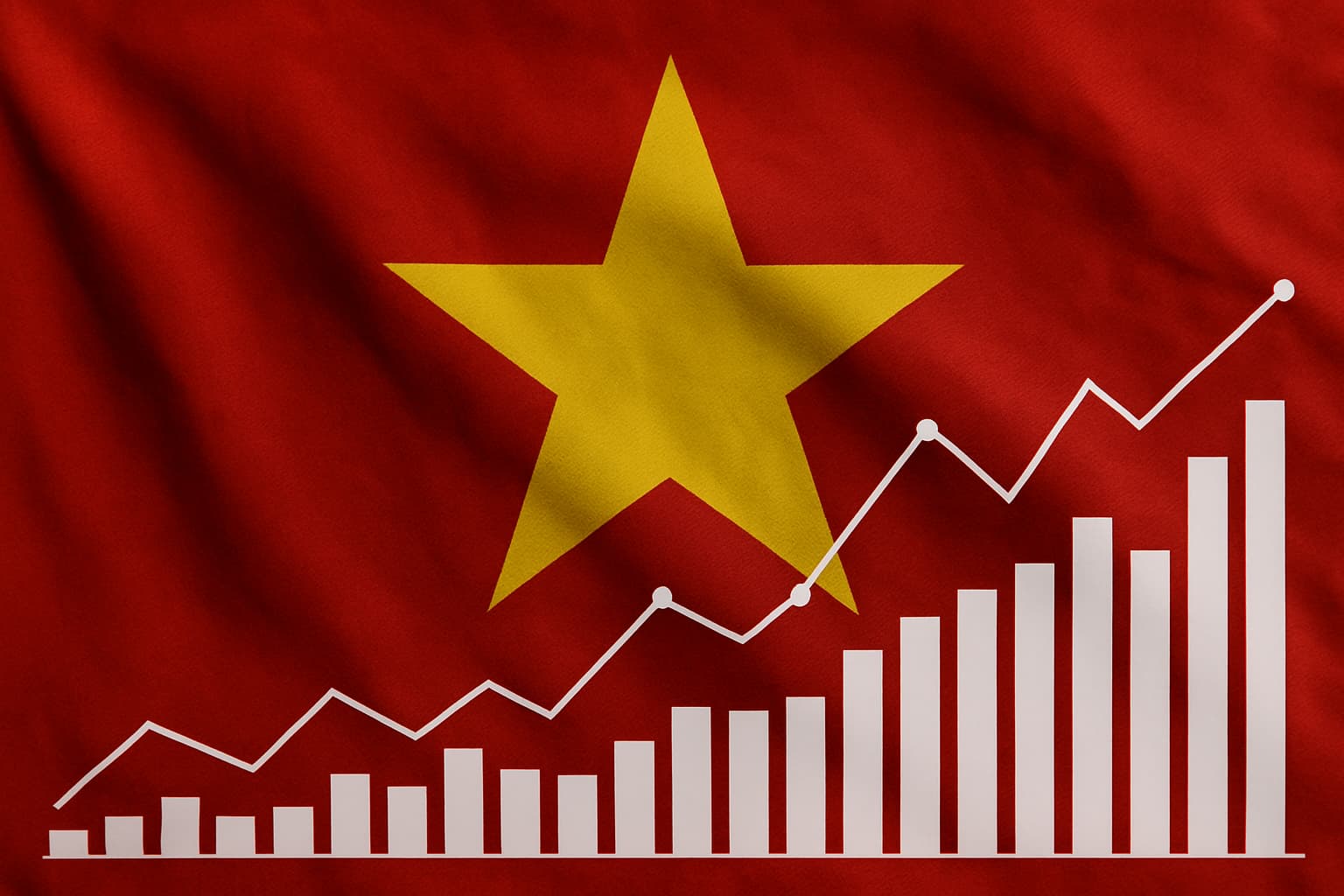
ベトナムの関税制度では、取引の性質や対象商品によって異なる3つの関税タイプが定められています。
これらはすべて、貿易コストや実務対応に直結するため、制度理解の第一歩として正しく把握することが重要です。
| 税の種類 | 内容 |
|---|---|
| 輸入関税 | 海外から輸入される商品に課される。基本税率が存在。 |
| 輸出関税 | 特定の天然資源や未加工品の輸出に対して適用される。 |
| 特別関税 | 反ダンピング税、報復関税、補助金相殺関税など特定状況で適用。 |
関税率の分類と適用基準
ベトナムの輸入関税は、対象国の貿易協定の有無により異なる税率が適用されます。以下の表は、それぞれの税率の特徴と適用範囲を示したものです。
| 税率区分 | 概要 | 適用対象 |
|---|---|---|
| 一般税率 | 最も高い関税率であり、 通常の基準税率とされる。 | FTAやWTOの枠外にある国との貿易 |
| MFN税率 | WTO加盟国に対して提供される 最恵国待遇税率。 | WTO加盟国 |
| FTA税率 | FTAに基づく税率。多くの場合、 関税ゼロまたは大幅減免される。 | ベトナムがFTAを締結している国・地域 |
なぜ今、ベトナムの関税が注目されているのか?

近年、ベトナムの関税制度は世界中のビジネス関係者から大きな関心を集めています。これは単にベトナムの経済成長によるものだけではありません。
より本質的には、国際的な経済環境の変化、地政学的リスクの高まり、そしてベトナムの戦略的かつ柔軟な貿易政策が重なった結果として、関税制度そのものがグローバルビジネスの重要テーマとなっているのです。
まず注目すべきは、米中関係の悪化がもたらしたグローバルサプライチェーンの再編です。中国への依存度を下げようとする動きが広がる中で、多くの企業が生産拠点や調達先を再検討しています。
その中で、地理的にも中国に近く、労働力やインフラも整備されつつあるベトナムが、有力な代替地として浮上しました。
さらに、ベトナムは政治的にも比較的安定しており、多国間主義を重視する外交スタンスが、企業にとって安心材料となっています。こうした信頼感が、関税を含めた貿易制度全体への期待感につながっているのです。
もう一つの要因は、自由貿易協定(FTA)の積極的な活用です。ベトナムは近年、CPTPP(環太平洋パートナーシップ)、EVFTA(EU-ベトナム自由貿易協定)、RCEP(東アジア地域包括的経済連携)などの大型協定を次々と発効させ、貿易の自由化を推し進めてきました。
これらの協定により、ベトナムとの取引には関税優遇が適用されるケースが大幅に増え、ビジネスのコスト競争力を高める要素となっています。
また、制度面でも改革が進行中です。電子申告やVNACCS(ベトナム電子通関システム)によるデジタル化が進み、手続きの透明性・迅速性が向上。これにより、これまで懸念されていた手続きの煩雑さや不透明さも大きく改善されつつあります。
つまり、現在のベトナム関税は、地政学的なリスク回避の受け皿であると同時に、FTAを活用した戦略的なコスト削減、そして効率的な通関制度という「三つのメリット」を兼ね備えた存在です。こうした背景が、企業の関心を強く引きつけているのです。
EVFTA や CPTPP といった自由貿易協定の適用によって関税ゼロ・大幅削減品目が拡大しており、品目改正により従来「その他」に分類されていた製品が細分化された点も制度運用における大きな変化です。
ベトナム関税の最新動向【2025年版】

2025年現在、ベトナムの関税制度は大きな転換期を迎えています。制度の近代化と貿易自由化のバランスをとりながら、ベトナムはASEAN内外との競争力を高めるための積極的な政策を推進しています。
このセクションでは、実務的な観点から見ても特に重要なポイントを、具体的な変化とともに詳しく解説します。
輸入関税の段階的撤廃と主要FTAの影響
ベトナムは複数の自由貿易協定に基づき、輸入関税の撤廃を進めています。特にEVFTA(EU-ベトナム自由貿易協定)やCPTPPの効果が顕著で、関税ゼロの品目が年々増加しています。
| FTA名 | 主な対象国・地域 | 関税撤廃対象品目例 | 2025年の適用状況 |
| EVFTA | 欧州連合(EU) | 機械類、医薬品、ワインなど | 約99%の品目で 関税削減・撤廃 |
| CPTPP | 日本、カナダ 豪州など | 自動車部品、繊維製品など | 加盟国との貿易で 関税ゼロ進展 |
| UKVFTA | イギリス | 食品、飲料、工業製品 | 漸進的にゼロ関税を拡大中 |
FTAの活用によって、輸入業者だけでなく、現地に生産拠点を持つ外資系企業にも恩恵が広がっています。
これによりベトナムを経由した第三国向け輸出戦略も拡大しています。
税関手続きのデジタル化とVNACCSの普及
ベトナム政府は通関手続きの迅速化と透明性向上を目的に、税関業務のIT化を強化しています。
現在主流となっているVNACCS(ベトナム版NACCS)は、日本のシステムを参考に構築された電子通関プラットフォームです。
申告手続きの完全オンライン化
24時間対応で通関書類を電子的に提出可能
処理時間の短縮
申告から許可までの時間が平均30〜50%短縮
リスク管理による選別検査
貨物の危険度に応じて検査の有無が自動判定
これらの取り組みにより、税関での滞留リスクが減少し、サプライチェーンの安定性が向上しています。
税率改正とHSコードの更新
2025年には一部品目での関税率見直しも実施されています。これには、WTOの協定やFTA再交渉の影響も含まれており、企業は最新の関税表やHSコードの動向を常に確認する必要があります。
| 品目カテゴリ | 旧税率 | 2025年税率 |
|---|---|---|
| 電子機器 | 10% | 5% |
| 農産加工品 | 15% | 10% |
| 化学製品 | 8% | 6% |
それぞれの背景は以下のとおりです。
電子機器
CPTPP(包括的および先進的環太平洋パートナーシップ協定)に基づく関税優遇措置の適用により、税率が半減。
農産加工品
EVFTA(EU-ベトナム自由貿易協定)における段階的削減スケジュールに従い、段階的に引き下げが実施。
化学製品
WTOとの整合性を高める制度改正の一環として、国際的な整合性重視の動きから税率を調整。
EUが導入を進めるCBAM(炭素国境調整メカニズム)に関連し、ベトナムでも環境関連税の検討が始まっています。これは、将来的に一部製品に対して「環境配慮型」関税が導入される可能性を意味しており、持続可能性を重視する輸出業者にとっては新たな対応課題となります。
このように、2025年のベトナム関税制度は単なる税率変更にとどまらず、FTA活用、通関の効率化、国際基準との整合、さらには環境政策との連携といった多面的な要素が絡み合っています。
今後も継続的な制度変更が予想されるため、企業は定期的な情報収集と柔軟な対応が求められます。
ベトナム関税とFTA活用の実務ポイント
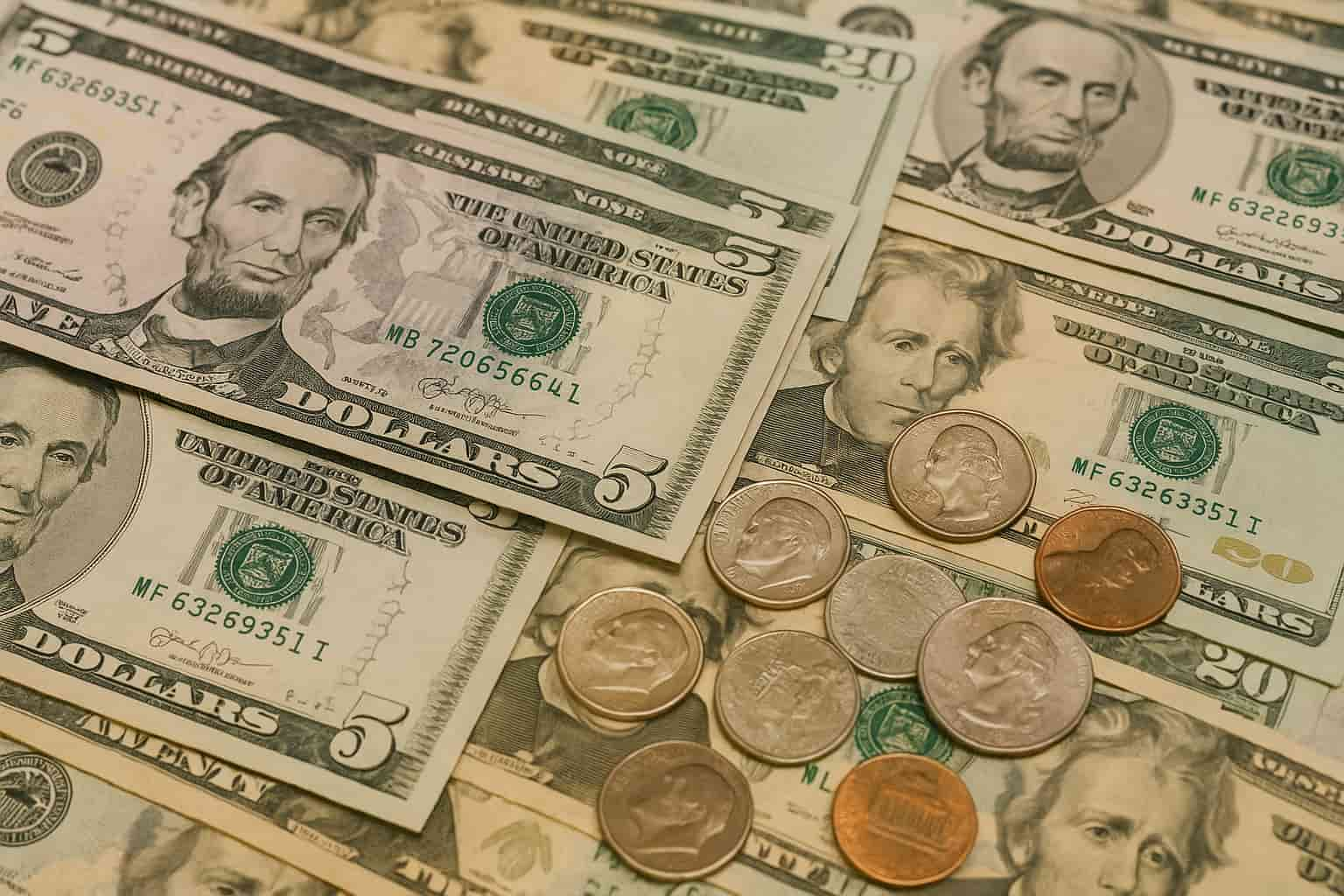
ベトナムの関税制度において、FTA(自由貿易協定)をいかに実務で活用するかは、輸出入業務における重要な戦略の一つです。
ベトナムは近年、多国間・二国間FTAを積極的に締結しており、それにより関税コストの大幅な削減が可能になっています。ただし、関税の優遇措置を受けるためには、原産地証明や品目ごとの適用条件など、複雑な要件を満たす必要があります。
このセクションでは、FTAの活用における具体的な実務のポイントを、貿易関係者の目線から詳しく解説します。
FTAを活用するメリットとは何か
FTAを活用することで、企業は以下のような恩恵を受けることができます。
- 対象品目に関する関税の削減または撤廃
- 原産地優遇による価格競争力の向上
- サプライチェーンの最適化(原産地ルールを活用した生産拠点の設計)
特にEVFTAやCPTPPなどのメガFTAでは、長期的に関税ゼロになるスケジュールが設定されており、戦略的な活用が可能です。
原産地証明書(C/O)の取得と提出
FTAによる関税優遇を受けるためには、対象貨物が協定に定める原産地で生産されたことを証明する「原産地証明書(C/O)」の取得が必須です。
| 証明書の種類 | 対象FTA | 管轄機関 |
|---|---|---|
| C/O Form E | ASEAN-China FTA | 商工省または認定機関 |
| C/O Form EUR.1 | EVFTA(EU-ベトナム協定) | 商工省・EU承認発給機関 |
| C/O Form CPTPP | CPTPP加盟国との貿易 | 商工省または電子申告 |
取得には、製品構成表、材料の仕入れ履歴、製造過程の証明などが求められる場合があります。
不備があると関税優遇が無効となるため、事前の準備が欠かせません。
実務上の注意点:品目分類と関税コード
FTAを活用する際の落とし穴の一つが「HSコード」の分類ミスです。
ベトナム税関は、細かい仕様の違いにも敏感であり、正確なコード適用がされていない場合は関税優遇の適用を拒否されるリスクがあります。
- 製品仕様が似ていても、分類が異なれば適用税率が変わる
- 関連法規の改正により、従来の分類が通用しない場合がある
- 輸入申告時に誤ったコードを使用すると、追徴課税の対象になる
専門の通関士や現地パートナーとの連携により、最新情報を正しく把握することが不可欠です。
FTA適用における企業体制の整備
FTAの恩恵を最大限に活用するには、企業内部でも次のような体制整備が求められます。
- 関税制度・原産地規則に精通した担当者の配置
- 貿易書類の一元管理と電子化
- 現地代理店や通関業者との連携体制の構築
- FTA適用判断のための自社製品データベースの整備
実際、FTA活用を進めている日系企業の多くが、専任チームの設置やERPシステムによる情報管理を導入しています。FTAを単なるコスト削減手段ではなく、経営戦略の一環として位置づけることが、競争力強化につながるのです。
輸出入ビジネスにおけるベトナム関税の注意点

ベトナムとの貿易においては、関税制度の理解に加えて、実務で直面する具体的なリスクや対応策にも目を向ける必要があります。制度そのものが整備されてきているとはいえ、実務上の誤解や手続きの不備によりトラブルが発生するケースは少なくありません。
このセクションでは、輸出入業務で特に注意すべき関税関連のポイントを詳しく解説します。
HSコードの誤分類リスク
関税適用の基礎となるHSコードの分類は、製品仕様に応じた正確な判断が求められます。
ベトナムでは関税率の差が大きいため、税関が独自解釈で再分類するケースも少なくありません。事前に専門家と相談し、正確なコードでの申告を徹底することが重要です。
関税評価額の透明性
インボイス価格に加え、保険料や運賃を含めたCIF価格が評価額の基準になります。特に関連会社間での取引では、税関による移転価格の調査対象になることもあります。
価格設定の根拠を示す文書や取引契約書を整備しておくことが、不要なトラブル回避につながります。
規制品目・禁止品目の事前確認
ベトナムでは一部の製品に対して輸出入の制限や許認可が設けられています。例えば、医薬品、化学品、中古設備などが該当します。
事前に該当品目リストや関係法令を確認し、必要な場合は輸出入許可証を取得するようにしましょう。
税関とのコミュニケーションと信頼構築
ベトナム税関は近年、透明性と効率性を重視する方向に進んでいますが、現場では担当官との解釈の相違や運用上のばらつきが生じることもあります。
過去の通関記録や申告履歴が参考にされるため、申告書類の正確性や対応履歴の記録が重要です。また、疑義がある場合は、税関との事前相談や事前教示制度の活用も有効です。
このように、輸出入業務における関税対応は、制度の理解だけでなく、運用面でのリスクマネジメントが求められます。特に新規参入企業や品目変更を予定している企業は、現地の最新実務動向を踏まえた対策を講じる必要があります。
まとめ
ベトナムの関税制度は、FTAの活用促進、電子通関の整備、さらには国際的な制度調和に向けた改革が進められており、貿易環境は確実に整いつつあります。一方で、実務上はHSコードの誤分類や原産地証明の不備など、基本的な対応でトラブルが発生するケースも少なくありません。
2025年以降は、環境政策や国際課税ルールの変化にも注意が必要であり、これまで以上に制度への理解と柔軟な対応力が問われます。
関税制度を正しく活用し、リスクを最小限に抑えるためにも、必要に応じて現地通関士や貿易専門家に一度相談してみることをおすすめします。














