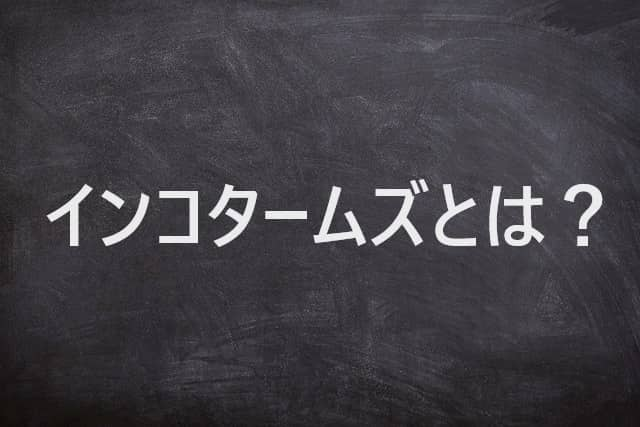貿易取引に携わる中で、「CIF(Cost, Insurance and Freight)」という言葉を目にしたことのある方は多いのではないでしょうか。価格交渉や契約書で頻繁に使われるこの用語は、単に「コスト込み」ではなく、売主と買主の間で費用やリスクをどの時点で移転するかを明確に定めた、国際ルール「インコタームズ(Incoterms)」の一種です。
本記事では、CIFの基本的な定義から、実務における運用方法、保険との関係、そして関税評価とのつながりまでを体系的に解説していきます。
なお、インコタームズ全体の概要については、以下の記事でまとめています。
貿易におけるCIFとは?定義と基本構造

CIFとは「Cost, Insurance and Freight」の略で、日本語では「運賃・保険料込み条件」と訳されます。
これは、国際商業会議所(ICC)が定めるインコタームズ(貿易取引条件の国際標準)の1つであり、海上輸送または内陸水路輸送を前提とした取引条件です。
CIFにおける特徴は、売主が以下を負担するという点にあります。
- 出発港での貨物の積み込み
- 仕向港(目的地港)までの海上運賃
- 買主のための貨物保険手配(最低限の補償)
一方、貨物のリスク(損害や事故の責任)は、本船に積み込まれた時点で売主から買主に移転します。
この「費用の負担」と「リスクの移転」が異なるタイミングで発生することが、CIF条件の最も重要なポイントです。
例えば、貨物が出発港で本船に積み込まれた後、目的地港に到着するまでの間に事故が発生した場合、その責任は買主側にあります。しかし保険の契約自体は売主が手配しているため、買主はその保険を使って損害補填を受けるという、やや複雑な構造となります。
なお、CIFはインコタームズ2020でも維持されており、港湾取引に限定される条件であることに注意が必要です。
航空輸送や宅配型の陸送にCIFを適用することは誤りです。これを混同すると、輸送途中での義務不履行やリスク分担に関する誤解が生じるため、適用範囲を明確に理解しておくことが求められます。
売主が運賃・保険を含んだ価格を提示するため、輸送コストの不確定性を抑えた見積もりを提供でき、貿易条件を単純化できることも強みです。
CIF貿易取引の流れと費用負担

CIF条件の取引は、以下のような流れで進行します。
| ステップ | 責任者 | 内容 |
|---|---|---|
| 輸出通関 | 売主 | 輸出許可の取得と通関手続き |
| 港までの輸送 | 売主 | 貨物を港まで運ぶ手配と費用 |
| 船積み(本船渡し) | 売主 | 本船への積み込み(この時点でリスクは買主へ) |
| 海上輸送手配 | 売主 | 運賃の支払いとブッキング |
| 保険手配 | 売主 | 最低限のカバー(通常ICC(C)条件)をつけた保険契約 |
| 目的港での荷卸し・通関 | 買主 | 荷卸し後の輸入通関、関税支払い、国内輸送など |
最大のポイントは、リスクが本船積込時点で買主に移るにもかかわらず、売主が海上輸送と保険を手配するという点です。これにより、万が一の事故が海上輸送中に起きた場合、買主が保険金を請求することになります。
しかしその保険契約自体は売主が締結しているため、保険内容やカバー範囲について買主が直接交渉できないという不都合が生じることもあります。
また、運賃や保険料も売主が負担するため、CIF価格にはこれらのコストが含まれています。
買主側はその分高い価格で購入することになりますが、条件としては「到着港までの輸送を任せられる」ため、輸送の煩雑な手配を避けたい場合には便利な選択肢と言えます。
貿易CIFとFOBの違い

CIFと混同されがちな取引条件としてFOB(Free On Board)があります。FOBでは売主の責任は本船への積み込みまでで、そこから先の運賃や保険手配は買主が行います。
CIFとの主な違いは以下の通りです
- CIF:売主が運賃・保険を含めて価格提示、買主は港での引取とリスク負担
- FOB:売主は積み込みまで、買主がその後すべてを手配
実務上、CIFでは保険の内容や名義が売主主導で決められるため、買主が必要なカバー範囲を十分に得られないケースがあります。
契約時に「被保険者の名義」や「ICC(A)条件でのカバー」を指定することで、リスクを軽減できます。
FOBについては以下の記事で詳しく解説しています。

CIFに含まれる保険と貿易リスク管理

CIF条件では、売主が手配する保険は通常「最低限の補償」にとどまります。一般的に使われるのは、ロンドン保険協会が定める「ICC C条件」と呼ばれるもので、火災・沈没・衝突といった基本的な事故のみをカバーしています。
しかし実際の物流では、盗難、積み替え中の破損、湿気による損傷など、より現実的なリスクが数多く存在します。
これらはC条件では補償されないため、より広範囲をカバーしたい場合には「ICC A条件」などの包括的な保険を指定する必要があります。
加えて、保険証券(Insurance Certificate)に記載される被保険者が誰かにも注意が必要です。売主名義のままだと、事故時に買主がスムーズに保険金を請求できない恐れがあります。
こうしたリスクを避けるためには、契約段階で保険の条件や被保険者の名義を明確にし、証券の写しを事前に確認しておくことが重要です。
CIFは一見便利に見えますが、実際には買主側がカバーしきれないリスクが潜んでいることも多いため、「保険がついているから安心」とは考えず、慎重な対応が求められます。
CIF貿易取引の落とし穴

CIF(Cost, Insurance and Freight)は、国際取引でよく用いられる取引条件で、売主が輸出港までの運賃と保険料を負担します。一見すると買主にとって負担が少ないように見えますが、保険内容の不十分さや関税評価における書類の曖昧さによって、後々大きなコストやトラブルにつながる可能性があります。
以下では、CIF取引における二大リスク「保険」と「関税評価」について詳しく見ていきましょう。
保険の補償内容は「ICC(C)条件」が主流
CIF契約では、売主が手配する貨物保険は多くの場合、ロンドン保険協会が定めるICC(Institute Cargo Clauses)C条件で付保されます。これは火災・沈没・衝突といった最低限の事故のみを補償する、最も簡素な内容です。以下の表にあるように、A・B条件と比べて補償範囲はかなり限定的です:
| ICC条件 | カバー内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| ICC(A) | すべてのリスク(All Risks) | 包括的補償 |
| ICC(B) | 自然災害や一部事故 | 中程度の補償 |
| ICC(C) | 火災・沈没・衝突など最小限 | CIF取引で一般的 |
つまり、盗難・荷崩れ・雨濡れなど実務上よく起こる損害がカバーされないことが多いため、CIF=安心ではないという認識が必要です。
保険金を受け取れるのは「名義人」のみ
もう一つ見逃されがちなのが、保険証券の「被保険者名義」です。CIFでは売主が保険契約を行うため、多くの場合、保険金の請求権も売主にあります。
つまり、たとえ貨物が破損しても、買主自身が保険金を直接請求できないリスクがあるのです。
これを避けるには、契約時に保険証券のコピーを確認し、必要に応じて買主側を「被保険者」または「追加被保険者(additional insured)」とする条項を入れておくことが肝要です。
関税評価額は「CIF価格」ベースで決まる
さらに重要なのが、日本の関税評価制度です。輸入時に課される関税や消費税は、商品価格だけでなく運賃や保険料を含めたCIF価格を基に計算されます。
そのため、インボイスや契約書にこれらの内訳が明記されていない場合、税関が運賃・保険料を推定により上乗せして評価額を決めることがあり、結果的に不利な関税が課される可能性があります。
特に運賃が「込み」価格で記載されていると、明細の確認ができずに誤解を招きやすくなります。
評価方法は国によって異なる
また、国によって関税評価方法が異なる点にも注意が必要です。たとえば米国などではFOB価格(本船渡し)を基準に評価を行うこともあります。
CIF価格を前提に交渉・契約していた場合、相手国側で関税計算が異なり、想定外のコストが発生するケースもあるため、取引相手国の制度を事前に調査し、価格構成を調整することが求められます。
まとめ
CIFは、運賃と保険料を売主が負担することで輸入者の手配負担を軽減できる取引条件です。しかし、リスクが本船への積み込み時点で買主に移転するため、保険内容や補償範囲の確認が非常に重要です。
また、CIF価格は多くの国で関税評価額の基準として使用されるため、通関書類の整備や費用の内訳明示にも注意が必要です。
表面的な「コスト込み」の便利さだけに頼らず、リスクと責任の所在を正しく把握したうえでCIF条件を選択することが、貿易実務におけるトラブル回避とコスト最適化の鍵となります。
取引条件の選定や契約内容に不安がある場合は、貿易実務に精通した専門家に一度相談してみることをおすすめします。