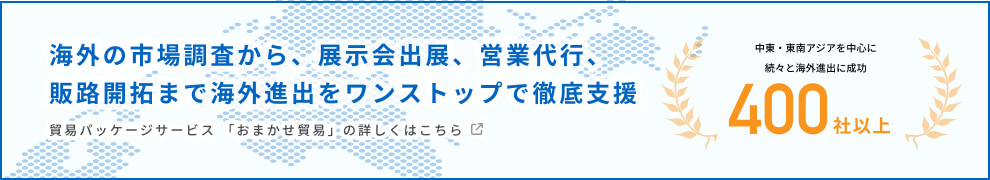スイスはEUに属していないものの、多数の自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)を締結しており、独自の関税制度を運用しています。こうした背景から、スイス向けの輸出入取引には他の欧州諸国とは異なる関税ルールが適用されることが多く、実務対応を誤ると予期せぬコストや通関トラブルを招く可能性があります。
さらに、2025年11月には米国がスイスからの輸入品に対して適用していた最大39%の関税を15%へ引き下げる措置を講じ、しかも遡及適用とする方針を発表しました。これにより、関税差額の還付請求や契約条件の再確認といった対応が各企業に求められています。
本記事では、スイスの関税制度の基礎から、最新の関税措置、EPAを活用した実務対応、還付申請の具体手順に至るまで、貿易担当者が現場で役立てられる視点で解説します。制度の理解と適切な対応は、コスト削減とリスク回避の鍵となります。
スイスの関税制度の全体像と他国比較

スイスの関税を理解するうえで重要なのは、EU加盟国とは制度設計の前提が異なる点です。見た目の税率だけで判断すると、実務上のコストやリスクを見誤る可能性があります。ここでは、制度の全体像を整理したうえで、他国との違いを確認します。
スイスの関税制度は「非EU・多国FTA型」が前提
スイスはEU加盟国ではなく、関税同盟にも属していません。一方でEFTA加盟国として多数のFTA・EPAを締結しており、貿易自由化を進めてきました。さらに重要なのは、2024年以降、スイスでは工業製品(非農産品)の関税が原則として撤廃されている点です。
このため、工業製品についてはFTAやEPAの有無にかかわらず無税となるケースが多く見られます。ただし、農産品や加工食品では引き続き関税が残る品目が多く、EPAの適用可否がコストに直結します。品目ごとの制度確認が不可欠です。
実務上は、スイス向け輸出が「EPA適用品目か」「通常関税が適用される品目か」を事前に切り分けることが不可欠です。特に原産地証明が取得できない場合、想定外の関税負担が発生するケースがあります。
スイス関税とEU・米国関税の考え方の違い
スイスの関税制度は、EUや米国と比べて考え方が大きく異なります。
以下の表は、実務者が判断する際に押さえておくべき違いを整理したものです。
| 項目 | スイス | EU | 米国 |
|---|---|---|---|
| EU加盟 | 非加盟 | 加盟 | 非加盟 |
| 関税同盟 | なし | あり | なし |
| 工業製品関税 | 原則無税(FTA前提) | 原則無税(域内) | 品目ごとに課税 |
| 農産品関税 | 高関税が多い | 高関税 | 品目差が大きい |
| 原産地証明の重要性 | 非常に高い | 高い | 高い |
スイスの場合、EUのような域内関税同盟がないため、「EU経由=無税」とはならない点に注意が必要です。特にEUからスイスへ輸出する場合や、スイス経由で第三国へ再輸出する場合は、原産地の扱いが関税判断の分かれ目になります。
HSコードと関税率確認で注意すべき実務ポイント
スイスでは、関税率の確認にあたりHSコードの精度が極めて重要です。HSコードが誤っていると、関税率だけでなくEPAの適用可否そのものが否認される可能性があります。
また、スイス税関はHSコードとインボイス記載内容、原産地証明の整合性を厳格に確認する傾向があります。
実務では、以下のような流れで事前確認を行うことが望まれます。
| 確認項目 | 実務上のチェック内容 |
|---|---|
| HSコード | 日本側・スイス側での解釈差がないか |
| 適用関税率 | 通常税率かEPA特恵税率か |
| 原産地要件 | 加工基準・付加価値基準の充足 |
| 書類整合性 | インボイス・証明書の記載一致 |
これらを事前に整理しておくことで、通関時の修正対応や追加コストを回避しやすくなります。
米国の15%関税措置とスイス輸出への影響

2025年11月、米国通商代表部(USTR)は、スイスからの輸入品に対して一時的に適用していた最大39%の追加関税を、2025年11月14日付で15%に引き下げると発表しました。対象は主に工業製品であり、この措置は貿易コスト、契約条件、価格設定に広範な影響を与える可能性があります。
以下では、この措置の概要と、スイス経由の輸出実務への影響を整理します。
15%関税措置の概要と対象品目の特定
今回の関税措置は、米国が2023年から適用していた対スイス追加関税(最大39%)の一部見直しとして発表されたもので、具体的には製造装置・計測機器・精密部品などの工業製品が対象です。関税分類(HTSコード)に基づき15%の税率が適用されるものと、引き続きそれ以上の税率が課される品目に分かれています。
以下は、関税引き下げの対象となるとみられる品目の例です。
| 品目分類 | 旧関税率(上限) | 新関税率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 工作機械部品 | 最大39% | 15% | HTS分類に基づく |
| 測定・検査装置 | 約20〜30% | 15% | スイス原産が条件 |
| 一部電子部品 | 約25% | 15% | 原産地証明が必要 |
対象品目の詳細はUSTRが発表したリストに基づき、通関時にHTSコードごとに判断されます。スイスでの製造実績や加工工程が明確に説明できる書類が求められるため、原産地証明や製造記録の整備が不可欠です。
関税差額の遡及適用と還付申請の可能性
この措置は2025年11月14日以降に米国へ通関された貨物に対し、遡及的に15%の関税を適用する内容です。すでに従来の高率で課税された貨物についても、条件を満たせば差額の還付を受けられる可能性があります。
以下の条件を満たす場合、輸入者側からの還付申請が可能です。
- 米国での通関日が2025年11月14日以降であること
- 対象品目がUSTRの指定リストに含まれていること
- スイス原産であることが証明されていること
申請に必要な書類としては、修正インボイス、原産地証明、関税支払い記録などが想定されますが、還付手続きは通関が確定しているか否かによって異なります。
未確定の場合は通関内容の修正、確定後は異議申立てなど、状況に応じた手続きと期限が設定されるため、事前に通関状況を確認したうえで対応することが重要です。
関税差額が与える影響は取引単位で大きくなる場合もあり、以下のような例が考えられます。
| 課税価格(USD) | 旧関税(39%) | 新関税(15%) | 差額(還付可能額) |
|---|---|---|---|
| $50,000 | $19,500 | $7,500 | $12,000 |
これが複数出荷分に及ぶと、年間でのコストインパクトは相当なものとなります。早期の調査と申請準備が求められます。
関税の変更が輸出価格に与える影響をより具体的に理解したい方は、関税引き下げによるコストメリットや実例についての以下の記事もご覧ください。

実務で注意すべき契約・価格設定の見直しポイント
今回の措置は価格設定や契約条件にも影響を与えます。例えば、すでにCIFベースで契約済みの場合、見積に含まれていた高関税率が15%に変更されたことで、次のような実務課題が発生する可能性があります。
- 販売価格と実コストの乖離が発生
- 買い手側から価格見直しを求められる
- 再契約や価格再設定の交渉が必要になる
また、三国間取引では還付申請権限がどの法人にあるか明確にしておく必要があります。契約主体と通関主体が異なる場合、責任の所在や対応フローが複雑化しやすいため、社内での確認体制が重要です。
このような関税見直しは突発的に行われることが多く、制度変更が即座に実務コストに直結します。今回の事例を、今後の契約設計や原産地管理体制の見直しに活用することが、貿易リスクの最小化に有効です。
日・スイスEPA活用による関税優遇と実務対応
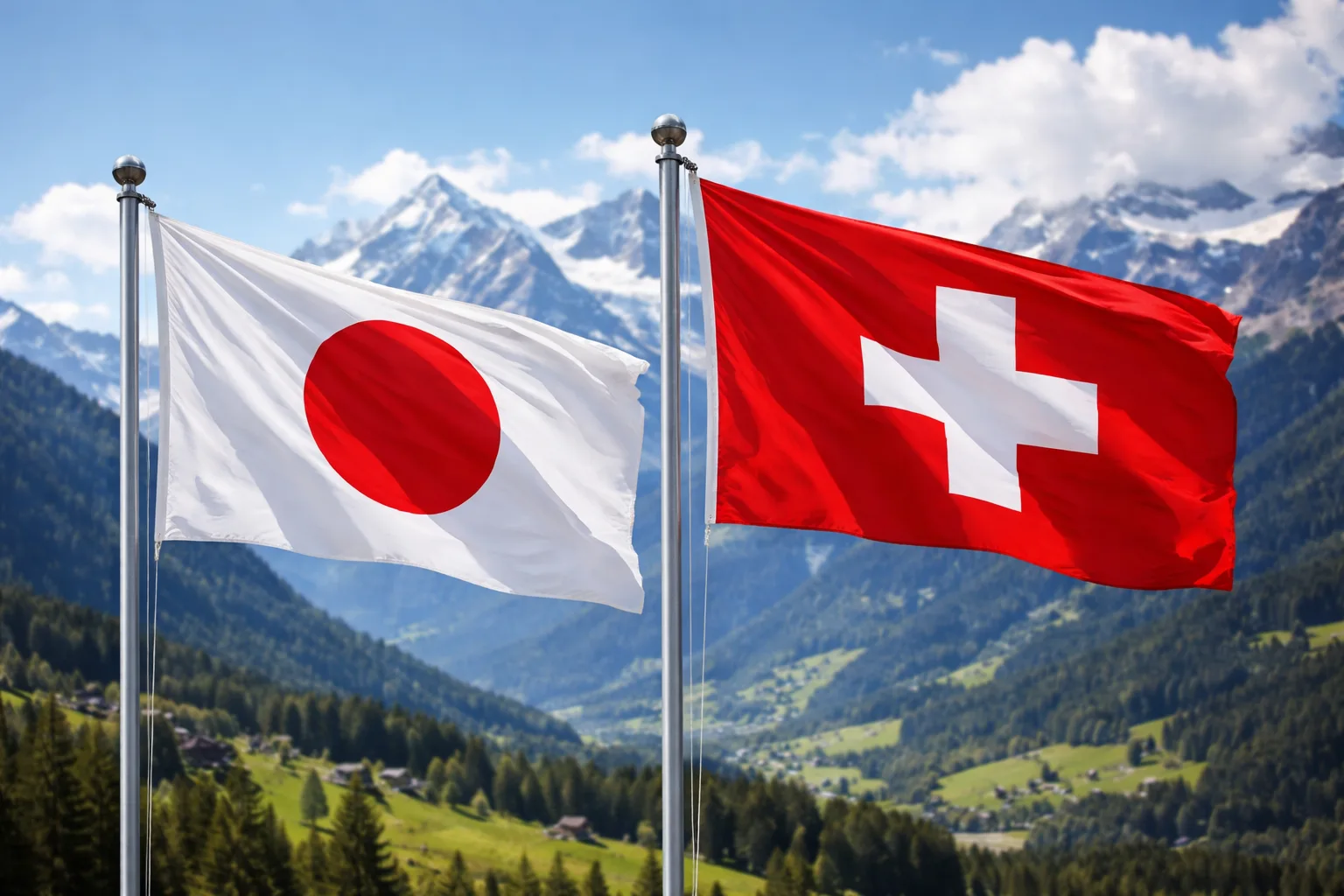
スイスは日本との間で経済連携協定(EPA)を締結しており、多くの日本製品が無税または軽減税率で輸出可能です。ただし、制度を正しく理解せずに適用を誤ると、本来受けられるはずの特恵が無効になることもあります。
ここでは、日・スイスEPAを実務で活用する際のポイントを整理します。
EPA適用により関税が免除される対象品目と効果
日・スイスEPAでは、工業製品を中心に関税が撤廃されており、自動車部品、電子機器、化学品など幅広い品目が対象となっています。農産品については一部の加工食品を除き、関税が残るケースもありますが、それでも段階的な引き下げが進んでいます。
例えば、以下のような製品群では実際に関税がゼロ、または低率で輸出できる可能性があります。
| 品目分類 | 通常関税率 | EPA適用後 | 原産地要件 |
|---|---|---|---|
| 自動車部品 | 約4〜6% | 0% | 完全に日本で製造 |
| プラスチック製品 | 約2.5% | 0% | 日本原産であること |
| 医薬品 | 0〜2% | 0% | 製造工程の証明が必要 |
こうした関税優遇は、製品単価が高くなるほど影響が大きくなります。価格競争力の維持だけでなく、営業戦略や見積単価にも直結する要素となるため、適用可能な品目は積極的にEPAを活用すべきです。
日・スイスEPAを実務で使いこなすには、そもそもEPAがどのような制度で、FTAと何が異なるのかを整理して理解しておくことが重要です。EPAについては、以下の記事をご覧ください。

原産地証明書と自己申告方式の違いと注意点
日・スイスEPAでは、原産地証明の方法として「第三者証明」と「自己申告(自己証明)」の2通りが認められています。実務での選択は、取引先の要求や社内体制に応じて決定する必要があります。
| 証明方式 | 特徴 | 提出先 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| 第三者機関による原産地証明書 | 商工会議所などの外部機関が発行 | 税関に提出 | 発行までに時間とコストがかかる |
| 自己申告(自己証明) | 輸出者が自ら作成 | インボイス等に記載 | 誤記や形式不備に注意が必要 |
特に自己申告方式では、原産性を裏付ける記録(生産工程表、部材表、コスト構成書など)を5年間保管する義務があり、税関監査が入った場合には即時提出が求められます。
過去には、輸出者が誤って非原産部材を含む製品に自己証明を適用し、EPA特恵を否認された事例もあるため、関係書類の管理体制が不可欠です。
実務でのEPA適用チェックリストと活用のポイント
日・スイスEPAを実際の業務で活用する際は、出荷前のチェック体制を構築しておくと安心です。以下に、実務担当者が出荷前に確認すべきチェックポイントを表形式で示します。
| チェック項目 | 内容 | 確認タイミング |
|---|---|---|
| HSコード | 両国での整合性が取れているか | 見積前/契約前 |
| 原産地判定 | 日スイスEPAの原産地基準を満たしているか | 出荷前 |
| 証明書の形式 | 自己証明 or 第三者証明を明確に選択 | 出荷前 |
| 書類の整合性 | インボイス、原産地証明書、契約書等の記載内容が一致しているか | 書類作成時 |
| 保存記録 | 原産地を裏付ける資料が5年間保管可能か | 出荷後 |
このようなチェックリストを社内で運用し、貿易管理部門と連携することで、EPAの適用漏れや否認リスクを最小限に抑えることができます。
スイスの関税制度はEPAの活用次第で大きなコスト削減が可能ですが、制度が複雑で誤った適用はリスクにつながります。原産地証明や遡及還付制度を正しく理解し、対応することが実務では不可欠です。
スイスの関税還付・遡及適用の仕組みと申請実務

関税制度が変更された際、過去に支払った関税が還付されることがあります。スイスでは、関税率の引き下げやFTA・EPAの新規適用があった場合に、遡及適用として差額の還付が認められるケースが存在します。正確な制度理解と的確な申請が、不要なコストの回収につながります。
還付が認められる代表的なケース
スイスにおける関税の遡及適用が可能な主なケースは次のとおりです。
- 政府による関税率引き下げの実施
- FTA・EPAの新規発効や改正
- 税関によるHSコード再分類による再評価
例えば、2025年11月14日以降の米国向け輸出で、従来39%の関税が15%に引き下げられたことを受け、すでに支払った関税の差額還付を申請できる可能性があります。
ただし、これらは自動的に反映されるわけではなく、輸入者の側で手続きを行う必要があります。
還付申請に必要な書類と期限
申請に必要な書類は制度ごとに若干異なりますが、基本的には以下の3点が重要です。
- 還付申請書(スイス税関指定の公式書式)
- 修正インボイスまたは補足計算書(関税差額の根拠資料)
- 原産地証明書(特恵関税の遡及適用時)
スイスにおける関税還付や減免は、制度の種類によって申請期限や条件が異なります。関税決定後の減免申請と、再輸出を前提とした還付では、適用ルールが異なる点に注意が必要です。
そのため、還付を検討する際は、どの制度を根拠に申請するのかを明確にしたうえで、スイス税関の公式案内に沿って対応することが重要です。
実務上の注意点と対応のコツ
関税還付で問題が起きやすいのは、「対象になることに気づかない」「手続きが煩雑で放置される」という2点です。
また、通関業務を委託している場合でも、申請責任は輸入者にあるため、社内での進捗把握が重要です。
たとえば、関税分類の誤りや原産地証明の不備があった場合、制度上は還付対象でも書類不備で却下されるケースがあります。
還付が見込まれる取引が発生した場合は、輸出入部門・経理部門・通関担当のあいだで、情報と書類の流れを確実に共有する体制が必要です。
まとめ
スイスの関税制度は、EU非加盟国であることに加え、EPAやFTAを広範に活用している点で、他国とは異なる特徴を持っています。輸出入実務においては、制度の表面的な理解だけでは不十分であり、原産地証明や適用ルールの確認、そして関税変更に伴う還付対応まで視野に入れた対応が求められます。
特に、2025年の米国による15%関税の引き下げとその遡及適用は、スイス向け・スイス経由の輸出取引に影響を及ぼす重要な動きです。このような制度変更は、コスト構造や契約条件の見直しに直結します。
また、日・スイスEPAを活用した関税免除には、正確な原産地判定と書類管理が不可欠です。制度は整っていても、実際に適用できるかどうかは、社内の体制と実務レベルの理解にかかっています。
関税制度は頻繁に更新されるうえに、各国ごとの運用にも違いがあります。輸出入コストや通関処理に不安がある場合は、専門家に一度相談してみることをおすすめします。