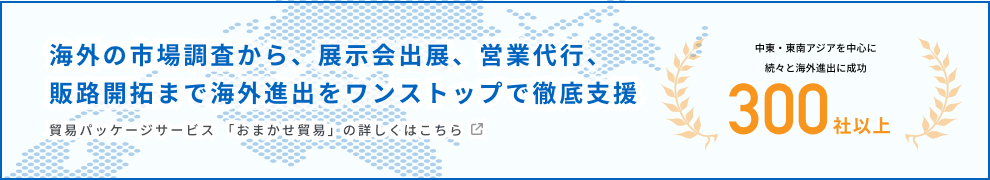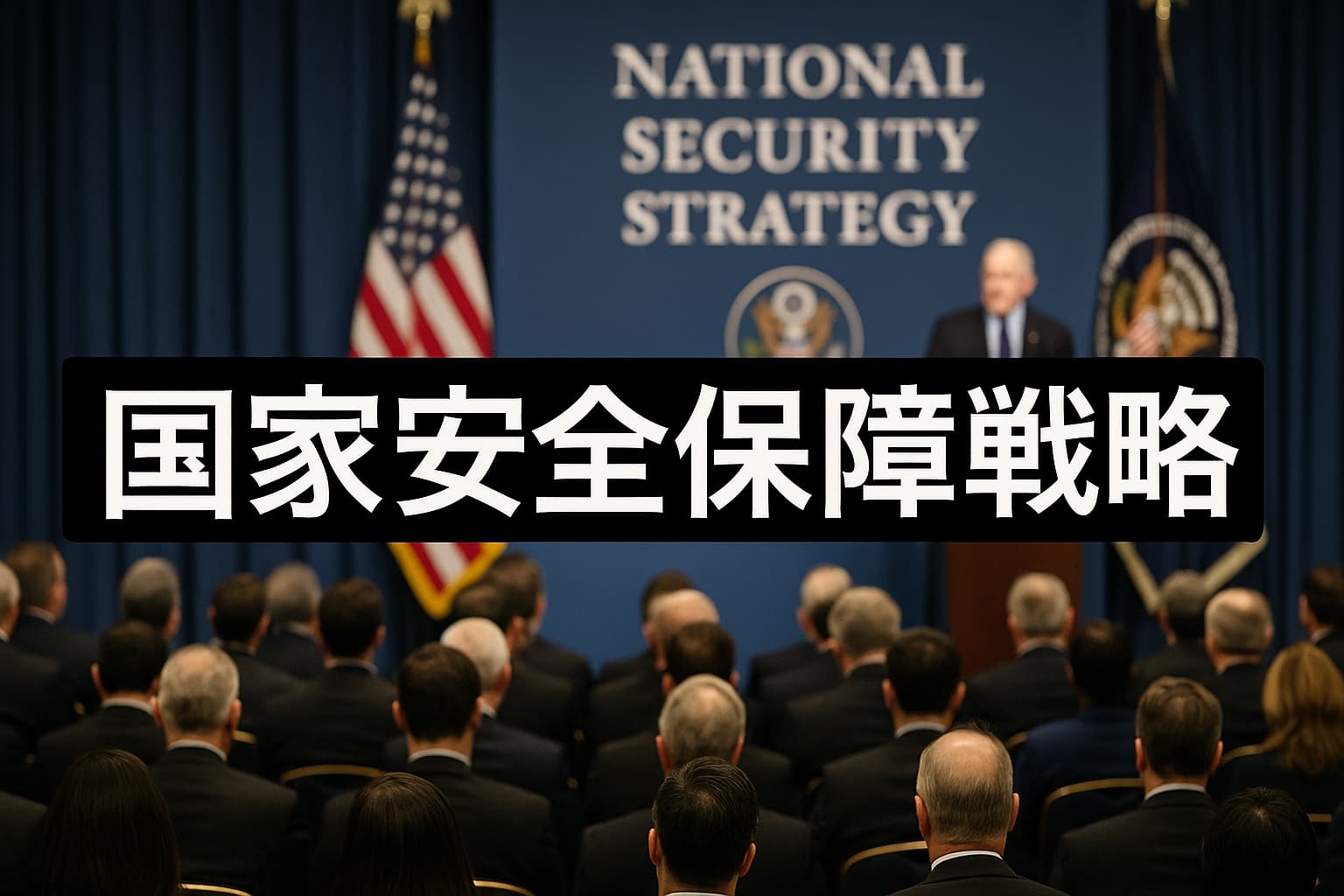ケニアは東アフリカの経済・政治の中核に位置し、地域へのビジネスや輸出拡大において戦略的な拠点として注目されています。農業や製造業、観光業など多様な産業が成長を続けており、さらに投資促進策や法人登記のオンライン化など、外国企業にとって有利な環境整備も進んでいます。
本記事では、ケニア進出を検討する企業が押さえておくべき基礎知識や制度のポイント、進出時の留意点をわかりやすく解説します。
最新の貿易実務・政策動向については、X(旧Twitter)でも随時発信中です。ぜひ @bouekidotcom をフォローして、海外展開に関わる情報をチェックしてください。
ケニア進出の基礎
ケニアと言えば、東アフリカ地域で随一の経済発展を誇る国です。
主要産業は紅茶や園芸作物などの輸出が盛んな農業、豊かな自然を背景に発達してきた観光業で、その他にも製造業や金融といった分野に関しても、この地域の中では最も進んでいます。
以上のように、今後ともに継続的に躍進を続けて行くと見込まれるケニアに関して、基本情報とビジネス上の留意点についてご紹介します。
ケニアの概況
ケニアは、約5,300万人の人口を有し、東アフリカ共同体内では2番目に大きな人口を持つ国です。首都のナイロビの人口は約400万人で、2024年までの実質GDP成長率は約7%と見込まれています。
国は東アフリカに位置し、豊かな自然資源と戦略的な地理的位置を持ち、多様な文化が結びついており、国際貿易において魅力的な輸出国となっています。
農業、製造業、観光業が主要産業で、特に農業はGDPの約25%を占め、コーヒーや紅茶の輸出で知られています。製造業も石油製品や化学製品、食品加工品などが主要な輸出品です。観光業も重要な部門で、野生動物や自然景観が魅力で多くの外国人観光客が訪れており、経済に大きく貢献しています。
将来的には新市場の開拓や競争力の向上を通じて、ケニアは経済成長を実現することが期待されています。

言語
ケニアの国語(national language)はスワヒリ語です。
公用語(official language)としてはスワヒリ語と英語が使われています(憲法(Constitution of Kenya, 2010)7条)。
ケニアにビジネス展開するメリット
①経済成長による市場拡大
ケニアは近年の経済成長率が高く、アフリカを代表する急成長国の一つとなっています。そのため、日本企業がケニアに輸出することで、成長著しい市場でビジネスの拡大が図れます。
②インフラ整備によるビジネスチャンスの増加
ケニア政府は、インフラ整備を重視しており、多くのプロジェクトが進行中である。このような状況から、インフラ関連の日本企業がケニアに輸出することで、さまざまなビジネスチャンスが生まれます。
③国際社会への関与強化
ケニアは東アフリカにおいて経済的・政治的な重要なポジションを占めており、積極的に国際社会への関与を強化している。そのため、ケニアへの輸出を行うことで、日本企業は国際社会への影響力を高め、ビジネスの拡大が見込めます。
④地域の安定性向上によるビジネス環境の改善
ケニアは政治的・経済的な安定性が向上しており、ビジネス環境が整ってきている。これにより、輸出先としてのリスクが低減されるため、日本企業にとっても魅力的な市場となります。
⑤ケニア人の日本製品に対する好意的な態度
ケニアでは、日本製品は高品質であると評価されており、好意的な態度が一般的です。このことから、日本企業がケニアに輸出することで、商品の市場競争力が高まり、売上の向上が期待できます。
⑥アフリカ市場への足がかりとしてのポジショニング
ケニアはアフリカ全土にビジネスを展開する上で、戦略的な立地にあります。そのため、ケニアへの輸出を行うことで、日本企業はアフリカ市場全体へのアクセスが容易になり、今後のビジネス戦略に役立ちます。
⑦労働力の豊富さ
ケニアは労働人口が多く、労働力が豊富であることが特徴です。そのため、日本企業がケニアに進出する場合、人材確保が容易であり、ビジネスの拡大を促進できます。また、労働コストが安いため、コスト面でもメリットがあります。
ケニアの強み
人材・調査能力・インフラ・知識層の厚み・技術力など80もの指標でランク付けする「グローバル・イノベーション・インデックス(GII)2019」に於いて、東アフリカではケニアがNo.1でした。
東アフリカでは、ルワンダ(世界No.94位)・タンザニア(No.97)・ウガンダ(No.102)と続いています。
アフリカでスタートアップへの投資額がケニアと南アに次いでナイジェリアはNo.114でした。
ケニアのスタートアップへの投資額は例年、アフリカでも例年上位に入っています。
GII2019でケニアの強みとして、以下3点が挙げられました。
- マイクロファイナンス融資額の対GDP比(4.2%、No.6)
- 与信の取得のしやすさ(No.7)
- 情報技術(ICT)を活用したビジネスの創造(No.33)
この強みの背景として、携帯電話・モバイルマネーが一般的になった事があります。
ケニアの人口は4,780万人なのにも関わらず、携帯電話の契約件数は3月に過去最高の5,103万件にまでのぼり、普及率は人口比106.8%に達するなど、躍進は続いています(ケニア通信局)。
一方のモバイルマネーのアカウント数は、2019年3月に3,206万件で人口比67.1%でした。
ケニアは、携帯電話を活用しビジネスと結び付ける事で、貧困層から富裕層に至るまで、様々な個人を金融サービスというアプローチで包括して行き、イノベーションを活発化させてきたと言えます。

外国人・外国企業に対する規制
海外からのケニアに対する投資については、原則として許認可等は必要とされていません。
しかしながら、以下の様な特定の業種や分野において、株式保有や出資は制限されている事があります。
(1)金融業 (2)保険業 (3)情報通信技術(ICT)産業 (4)航空業 (5)海運業
(6)建設業 (7)鉱業 (8)警備業 (9)エンジニアリング業 (10)ナイロビ証券取引所上場企業に対する出資
ケニアでは、金融・ICT・海運など特定産業への外国投資に株式保有や出資制限があり、ビジネス展開における業種選びに注意が必要です。また、10万ドル以上の投資で優遇措置を得られるものの、最低投資額のハードルは中小企業にとって参入障壁となる可能性があります。
投資家に対する助成制度
10万米ドル相当以上の額を投資する外国投資家は、ケニア投資庁へ投資証明書の発行申請をする事が出来ます。
投資証明書発行を受ける事で、特定の許認可の早期発行や、経営者・技術者・投資家等のための一定の入国許可等の早期発行といった優遇措置を受ける事が可能です。
為替管理法および外国送金
1995年に為替管理法が廃止されて以降、ケニアには為替管理法はありません。
外国為替取引をする場合は、ケニア中央銀行から許可を得ているケニアの銀行を通じて行う必要があります。
株式会社の概要
(1)取締役
非公開会社の取締役は1名で足りますが、公開会社の場合には最低2名の取締役が必要です。
自然人では無い場合でも取締役に就任する事が出来ますが、最低1名は自然人である必要があります。
(2) 取締役会
取締役会で別途定めない限り、取締役会の定足数は2名の出席で満たされます(ただし、公開会社に関しては、
定足数は常に2名以上である必要があります)。
取締役会の決議は、出席取締役の過半数の賛成で可決されます 。
(3)秘書役
非公開会社は、原則として秘書役を設置する必要はありませんが、
払込資本が5百万ケニア・シリング以上ある場合、秘書役を設置しなければなりません。
公開会社の場合には最低1名の秘書役を設置しなければなりません。
秘書役は、ケニア公認秘書役法の下で資格を持つ者でなければなりません。
(4)監査人
公開会社および非公開会社のどちらも、原則としては、各会計年度において監査人を選任しなければなりません。
会社の設立
ケニア政府の電子ポータルサイトを通じて行う事で、会社の設立登記が可能です。
手続きが完了すれば、設立証明書が発行されます。
まとめ
ケニアは、東アフリカのハブとして市場性・制度整備・デジタル浸透の三拍子がそろい、域内展開の足場づくりに適したロケーションです。農業・観光に支えられつつ、金融・ICT・製造などの裾野が広がっており、政府のインフラ投資や起業エコシステムの活況もプラスに働いています。
一方で、特定業種の外資規制、許認可・ガバナンス対応、為替・資金決済の実務、最低投資額などの参入要件がハードルになり得ます。現地金融やモバイルマネーを起点にした「デジタル×実需」の設計、信頼できる現地パートナー・専門家の活用、規制順守と内部統制の早期実装が成功の鍵です。
ケニア単体の販売ではなく、周辺国への越境展開を前提に供給網・人材・法務体制を設計することで、リスク分散とスケールを同時に狙える市場といえます。
- 【機会】
農業・観光にICTや金融サービスを重ねる“アグリテック/ツーリズム×デジタル”が有望。公共・インフラ投資の波及需要も狙える。 - 【留意】
外資規制のある業種では持分構成・許認可の事前設計が必須。資金還流や税務・移転価格、労務・取締役要件も初期から管理。 - 【実務】
会社設立・ビザ・各種ライセンスは電子化が進む一方、個別審査は時間差あり。現地法律事務所・会計事務所・金融機関と三位一体で推進。 - 【展開】
首都中心のB2Bだけでなく、モバイル基盤を活かしたB2C/B2B2Cモデルで地方まで浸透を設計。保守・アフターとサプライの現地化が差別化要因。 - 【ガバナンス】
贈収賄・情報管理・サイバー対策などのコンプライアンス枠組みを現地仕様で整備。透明性の高いパートナー選定と監査トレイルの確保が不可欠。
海外販路開拓をゼロから始めるなら『おまかせ貿易』
『おまかせ貿易』は中小企業が、低コストでゼロから海外販路開拓をするための"貿易代行サービス"です。大手商社ではなしえない小規模小額の貿易や、国内買取対応も可能です。是非一度お気軽にお問い合わせください。