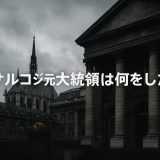2025年の日本の輸出は、完成車などの耐久消費財中心の構造から、半導体製造装置や精密部材といった先端資本財へ重心が移りつつあります。円高による価格圧力や政策リスクの影響を受けながらも、AI・データセンター需要に伴う設備投資が輸出を下支えしています。
本記事では、2025年最新データに基づく輸出品ランキングを踏まえ、主要品目の市場背景や構造的な変化、今後注目すべき分野を簡潔に整理します。
日本の輸出品ランキングの基本と統計の見方

日本の輸出ランキングは、単に「どの製品が多く売れたか」を示すものではなく、為替、技術革新、地政学リスクといった外部要因が輸出構造にどう作用しているかを映し出す重要な指標です。2025年は数量ベースでは回復傾向にある一方、円高反転により価格ベースの成長が抑制されるという非対称性が顕在化しています。
輸出統計は主に財務省の「貿易統計(通関ベース)」に基づき、国際比較の基準となるFOB(本船渡し価格)で表示されます。FOBは輸出港で貨物が船積みされた時点の価格であり、輸送費・保険料を含むCIFとは異なります。
為替が円高に振れた場合、FOB価格は外貨建てで割高となり、国際価格競争力を直接押し下げるため、2025年の分析では特に重要な要素です。
読み解くポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| データ出典 | 財務省「貿易統計」(通関ベース) |
| 分類基準 | HSコード(国際統一品目分類体系 / 日本は9桁・12桁へ拡張) |
| 表示価格 | FOB(本船渡し価格) ※保険料・運賃を含まず |
| 表示単位 | 金額(億円)・数量(台数、重量など) |
| 分析視点 | 金額=市場価値、数量=需要の実体(順位差が出る) |
| トレンド把握 | 年次推移+四半期推移(政策イベントの影響を抽出) |
| 注意点 | 為替、HS分類誤り、規制更新(輸出管理対象)の影響 |
HSコードは国際的な6桁分類を基礎とし、日本では9桁・12桁へ拡張されています。輸出申告では正確な分類が求められ、特に2025年は経済安全保障強化に伴い、先端装置・素材の誤分類が輸出規制違反・補助金不適格・納期遅延に直結するリスクがあります。
これは単なる統計項目ではなく、企業の収益に直接影響する管理指標です。
統計分析では金額ベースが主流ですが、2025年は数量ベースの動きが構造を示します。たとえば、自動車は出荷台数が増えても円高による単価下落で金額が伸びにくい一方、半導体製造装置は数量が横ばいでも高付加価値投資により金額が上昇します。単純な順位ではなく、「数量→単価→政策」の三層で読むことが重要です。
HSコードの詳細な仕組みや分類方法については以下の記事をご覧ください。

2025年 日本の主要輸出品目ランキングと主な輸出先・市場背景
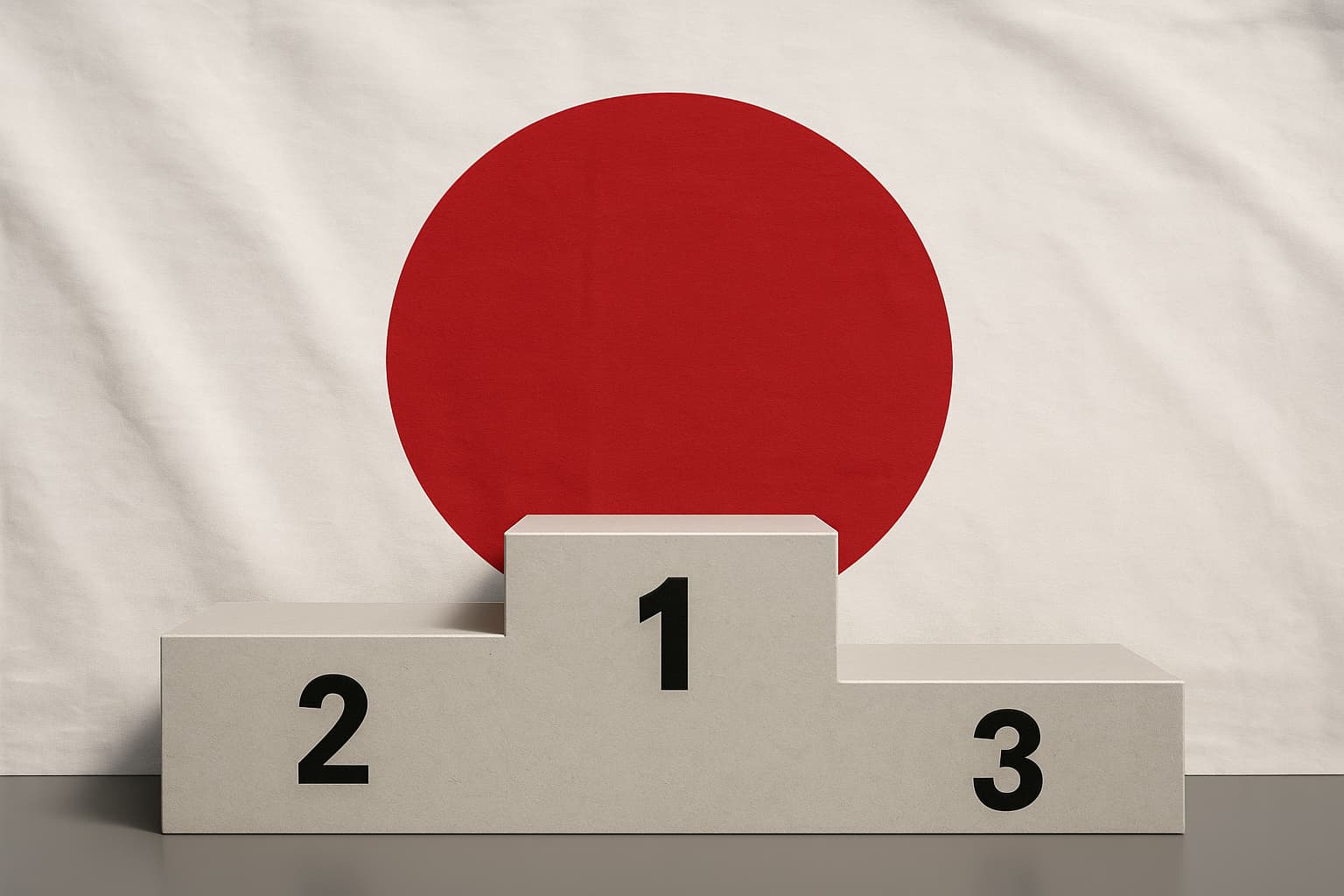
2025年の輸出動向を把握するうえで、まず確認したいのが日本の主要輸出品目です。
ここでは、財務省「貿易統計」令和7年度上半期(2025年4〜9月)の主要商品別輸出データをもとに、輸出額の大きい品目をランキング形式で整理します。自動車や半導体関連、鉄鋼など、日本の競争力を支える分野がどの程度の比重を占めているのかを見ることで、輸出構造の全体像が把握しやすくなります。
このランキングを出発点に、それぞれの品目がどの地域へ多く輸出されているのか、背景にどのような需要や政策的要因があるのかを続くセクションで詳しく見ていきましょう。
主要輸出品目ランキング(令和7年度上半期4~9月)
| 順位 | 輸出品目 | 金額(百万円) |
| 1 | 自動車(完成車) | 8,376,086 |
| 2 | 半導体等電子部品(うちIC等) | 3,248,264 |
| 3 | 半導体等製造装置 | 2,178,127 |
| 4 | 鉄鋼 | 1,917,923 |
| 5 | 自動車の部分品 | 1,819,823 |
| 6 | プラスチック(樹脂製品向け素材) | 1,689,914 |
| 7 | 原動機(エンジン・タービン等) | 1,482,742 |
| 8 | 非鉄金属 | 1,397,479 |
| 9 | 科学光学機器(計測・医療用など) | 1,298,708 |
| 10 | 電気回路等の機器 | 1,126,840 |
いずれも製造業の中核を成す分野であり、とくに自動車と半導体関連(半導体等電子部品・半導体製造装置)は、日本の輸出を牽引する「二本柱」となっています。鉄鋼や非鉄金属、原動機、科学光学機器などの基幹素材・装置も上位に入り、サプライチェーン全体で日本製品への信頼が厚いことがうかがえます。
主な輸出先と市場背景
①自動車(完成車)
主な輸出先:アメリカ、UAE、オーストラリア
- 米国
2025年9月の日米貿易協定により最大27.5%関税リスクが緩和し、駆け込み需要→短期回復。一方、円高反転により価格競争力は低下。EV補助金対象の見直し(IRA修正)が輸出に影響。 - UAE / 豪州
右ハンドル市場+SUV/高級車需要が堅調。景況感に左右されにくい富裕層需要が安定。
→ 台数回復・価格圧力で金額停滞の典型例。数量増でも円高で輸出額は鈍化。
②半導体等製造装置(装置・露光・成膜)
主な輸出先:韓国、台湾、中国
- AI・HBM投資の世界的ブームが需要を牽引。データセンター・5G・自動運転ECU向けの設備投資が続く。
- 中国は輸出管理対象(先端露光装置等)。制約により成熟ノード(28nmなど)需要が集中。
- 韓国/台湾:HBM・先端メモリライン増設の中心。歩留まり改善=日本製装置の強み。
→ 代替性が低く「セキュリティ・プレミアム」が乗る輸出の代表格。
③自動車部品(電子制御・EV駆動系含む)
主な輸出先:米国、メキシコ、タイ
- 完成車の現地生産回復が数量需要を押し上げる。
- ハイブリッド車向け、パワー半導体/ECU/バッテリー関連が輸出金額を底上げ。
- サプライチェーンはJIT→JICへ。在庫積増し・部品分散が安定供給の評価に直結。
→ 電動化部品ほど単価上昇、価格転嫁が可能で円高影響を相殺。
④電子部品(IC・センサー・電源)
主な輸出先:中国、ベトナム、マレーシア
- EMS(電子機器受託製造)集中。iPhone/低価格スマホ/PC/車載ECUの設計拠点と連動。
- 日本の強みは高機能品(電源制御・車載耐熱IC・センサー)。
- 台湾/韓国半導体製造装置向け材料との製造装置→電子部品の連動需要が特徴。
→ 「小型・高機能・高歩留まり」=単価維持しやすい輸出領域。
⑤医薬品(原薬・抗がん剤・高付加価値ジェネリック)
主な輸出先:米国、ドイツ、スイス
- 品質と安定供給が評価の核心。規制が厳しい市場でもアクセス可能。
- 慢性疾患・高齢化市場が確実に増えるため、受注が景気に左右されにくい。
- 米国での価格圧縮圧力があるが、高付加価値分野は逆に単価上昇。
→ 世界の医療制度に組み込まれる粘り強い輸出。
⑥鉄鋼(ホットコイル・鋼材)
主な輸出先:タイ、韓国、インドネシア
- ASEANの建設・港湾・エネルギー網の投資で需要安定。
- 為替の影響を強く受ける典型品目。円高になるほど価格優位が消える。
- 一方、輸入原料コストは円高で低下し、マージン補完が可能。
→ 価格勝負の分野=為替に最も敏感。
⑦プラスチック製品(樹脂原料・工業用)
主な輸出先:中国、米国、インドネシア
- 加工素材として電子部品/医療機器/包装材に横断需要。
- EU・米国の環境規制(CBAM・循環経済)に対応できる企業は強い。
- 単価低い汎用品→価格圧力、ハイグレード樹脂→単価維持。
→ 脱炭素適応の格差が輸出競争力を二極化。
⑧光学機器(医療・産業向けレンズ)
主な輸出先:米国、中国、シンガポール
- 内視鏡・半導体検査装置・計測器向けが主力。
- 日本製は精度・安定供給でプレミアム価格を維持。
- 半導体装置・医療機器のサプライチェーンと連動。
→ “用途特化の高単価輸出”=景気耐性が高い。
⑨化学製品(半導体材料・合成樹脂)
主な輸出先:台湾、中国、米国
- フォトレジスト、CMP材、スパッタリングターゲットなど装置とセットで伸びる。
- 中国市場は成熟ノード向けが堅調、米国・台湾は先端ライン。
- 製造装置との相互補完で価格が崩れにくい。
→ 資本財サプライチェーンに埋め込まれている不可欠素材。
⑩工作機械(NC/精密加工設備)
主な輸出先:ドイツ、中国、米国
- 半導体封止、精密金属加工、航空パーツなど高付加価値用途が伸びる。
- 中国一般製造は鈍化、欧米の高度加工ラインが主要需要源。
- 為替影響は強いが、ブランド性と精度が価格を支える。
→ 成熟市場ほど日本製でないと稼働できない領域が存在。
日本の輸出構造を理解するうえで欠かせないのが、最大の輸出相手国であるアメリカとの関係です。特に2025年は、米国の政策変更や自動車・半導体をめぐる関税方針が企業の戦略に直結します。
以下の記事では、トランプ政権下で再構築が進む日米貿易の最新情勢を整理しています。

日本の輸出に影響を与える外部要因

日本の輸出は、国内での生産能力や技術力だけでなく、世界経済の循環、通商政策、地政学リスク、産業トレンドといった外部環境の影響を強く受けます。
このセクションでは、輸出戦略を考えるうえで企業が押さえておきたい主要な外部要因と、その実務上のポイントを整理します。
為替レートの変動(円安・円高)
為替は価格競争力に直結する最重要指標です。円安局面では日本製品の国際価格が相対的に下がり、輸出には追い風となる一方で、原材料や部品の輸入コストは上昇します。
反対に円高は輸出価格を押し上げ、受注減のリスクが高まります。そのため、多くの企業は為替予約や契約通貨の分散、価格条項の工夫など、複数のヘッジ手段を組み合わせて影響を抑える工夫を行っています。
国際政治リスクと地政学的要因
米中対立やロシア・中東情勢、台湾海峡リスクなどの地政学的要因は、サプライチェーンの寸断や海上輸送ルートの混乱、保険料・物流コストの急騰を招く可能性があります。
こうした不確実性に備えるため、特定国への過度な依存を避ける拠点配置や調達先の分散、在庫水準の見直しといった「レジリエンス重視」のサプライチェーン設計が重要になっています。
各国の貿易政策・保護主義の強化
米国の関税政策、EUの環境関連規制(CBAMなど)、中国の輸出管理強化など、各国の通商政策は日本企業にとって新たな参入障壁にもビジネスチャンスにもなり得ます。
FTA(自由貿易協定)やEPA(経済連携協定)の活用、原産地証明の適正管理、サプライチェーン全体でのHSコード・インボイス整備など、制度面での対応力がコスト・リードタイムに直結する時代になっています。
技術革新と産業トレンドの転換
デジタル化、脱炭素、AI・ロボットなど、世界的な産業構造の転換が進むなかで、従来型の汎用品だけに依存した輸出ビジネスは相対的に競争力を失いつつあります。
一方で、環境性能の高い製品や高度なソフトウェア・制御技術を組み合わせたソリューションは、価格競争から距離を置きながら市場を開拓できる領域です。継続的な研究開発投資と製品・サービスの高付加価値化が、輸出競争力のカギとなります。
これらの外部要因は、品目別の競争力や市場シェア、輸出先ポートフォリオの組み方に大きく影響します。定量データと政策動向の両面から情報収集を続けながら、戦略とオペレーションを柔軟に見直していくことが、2025年以降の輸出ビジネスには欠かせません。
主な輸出先国やその背景事情(例:自動車は米国、半導体装置は台湾・中国、医薬品は米国・ヨーロッパ)と、技術力・付加価値によって日本が国際市場で競争力を保っている構図が読み取れるという点が押さえるべき要点です。
日本の輸出品の動向と今後の注目分野

2025年時点の日本の輸出には、従来の主力分野に加え、技術革新や政策転換を背景とした新たな成長領域が現れています。本章では、各産業の最新トレンドと今後の注目分野を整理します。
自動車産業のEV・ハイブリッド化
世界的な排ガス規制強化にともない、電気自動車(EV)やハイブリッド車(HEV)が輸出の中心に移行しつつあります。欧州・中国を中心に低排出車の需要が拡大し、日本メーカーの燃費性能・品質が評価されています。
国内メーカーは電動化シフトを急速に進め、バッテリー調達網の再構築やソフトウェア統合を含む車両開発の高度化を進めています。完成車だけでなく、駆動系部品や電池管理システム(BMS)など周辺分野の輸出拡大も見込まれます。
半導体供給網の再評価と投資加速
地政学リスクの高まりにより、先端半導体の供給安定性が重視されています。日本の半導体製造装置・高機能材料は依然として国際競争力が強く、需要が集中しています。
特にフォトレジスト、シリコンウエハー、スパッタリングターゲットなどは微細加工プロセスに不可欠で、グローバルサプライチェーンにおける日本の役割は大きい状態が続いています。政府の補助金政策や輸出管理の強化は、企業戦略との連動が不可欠です。
医療・ヘルスケア関連の高付加価値化
高齢化の進展と医療技術の高度化を背景に、日本製の内視鏡、透析装置、がん治療薬などの輸出は堅調に伸びています。精密加工と品質保証の強みを持つ製品は、欧米市場だけでなくアジア新興国でも導入が拡大しています。
特にアジア市場では病院設備の近代化が進み、導入後の保守性や長期利用を重視する傾向があり、日本製品の信頼性は大きな優位性となります。
再生可能エネルギー・グリーン関連製品
脱炭素政策を背景に、太陽光発電部材、水素関連機器、蓄電池などの輸出も伸びています。日本企業は部材レベルで技術優位性が高く、インバーター、高効率セル、制御装置といった周辺領域で存在感を発揮しています。
東南アジアや中東のエネルギー移行政策は調達需要を刺激し、長期プロジェクト型の輸出案件が増加する傾向にあります。
経済安全保障と戦略物資の管理強化
半導体・航空宇宙・防衛分野などの戦略物資は、輸出管理制度の強化により審査要件が増しています。一方で、希少金属や先端素材への国際需要は継続しており、適切な管理体制の構築は市場参入の前提条件となっています。
知的財産・ブランド輸出の重要性
製品そのものの輸出に加え、設計・特許・商標・ライセンスといった無形資産の提供は、日本企業の競争力向上に直結します。製造委託や共同開発を通じたソフト面の輸出はさらに拡大が見込まれます。
特にアジア市場では「日本製=信頼性」のブランド価値が強く、品質保証や長寿命設計が付加価値として認識されています。今後はハードとソフトの融合が競争力の源泉となる可能性があります。
今後の日本の輸出は、単なる製品供給にとどまらず、品質・持続可能性・知的資産を組み合わせた総合的価値の提示が求められます。市場ごとの需要構造を理解したうえで、長期的な戦略設計が重要です。
まとめ
2025年の日本の輸出品ランキングを通して、自動車を中心に半導体装置や医薬品など多様な製品が世界で高く評価されていることがわかります。特に、高度な製造技術と信頼性の高さは、日本製品の競争力の源泉です。
今後は、脱炭素や医療分野など、社会課題への貢献と技術革新の両立が求められる分野への対応がカギとなります。
貿易実務や輸出戦略を考える際は、こうした統計と動向を踏まえた上で、柔軟かつ長期的な視点を持つことが重要です。今後の貿易活動に不安や課題を感じる方は、専門家に一度相談してみることをおすすめします。