
目次
世界経済の二大巨頭であるアメリカ合衆国と日本の間の経済関係は、2025年初頭に米国が再導入した重要な関税措置を受け、新たな複雑性の段階に入りました。日本の主要な輸出品目を対象としたこれらの関税は、歴史的に重要で深く相互に結びついた貿易関係を背景に発生しています。
本稿では、これらの最新の関税の詳細、日本経済と主要産業への潜在的な影響、日本政府の対応について深く掘り下げ、さらに重要なことに、これらの展開を両国間の長年にわたる、時には困難な歴史を持つ貿易関係という広範な文脈の中で考察いたします。
日米貿易関係の歴史的視点
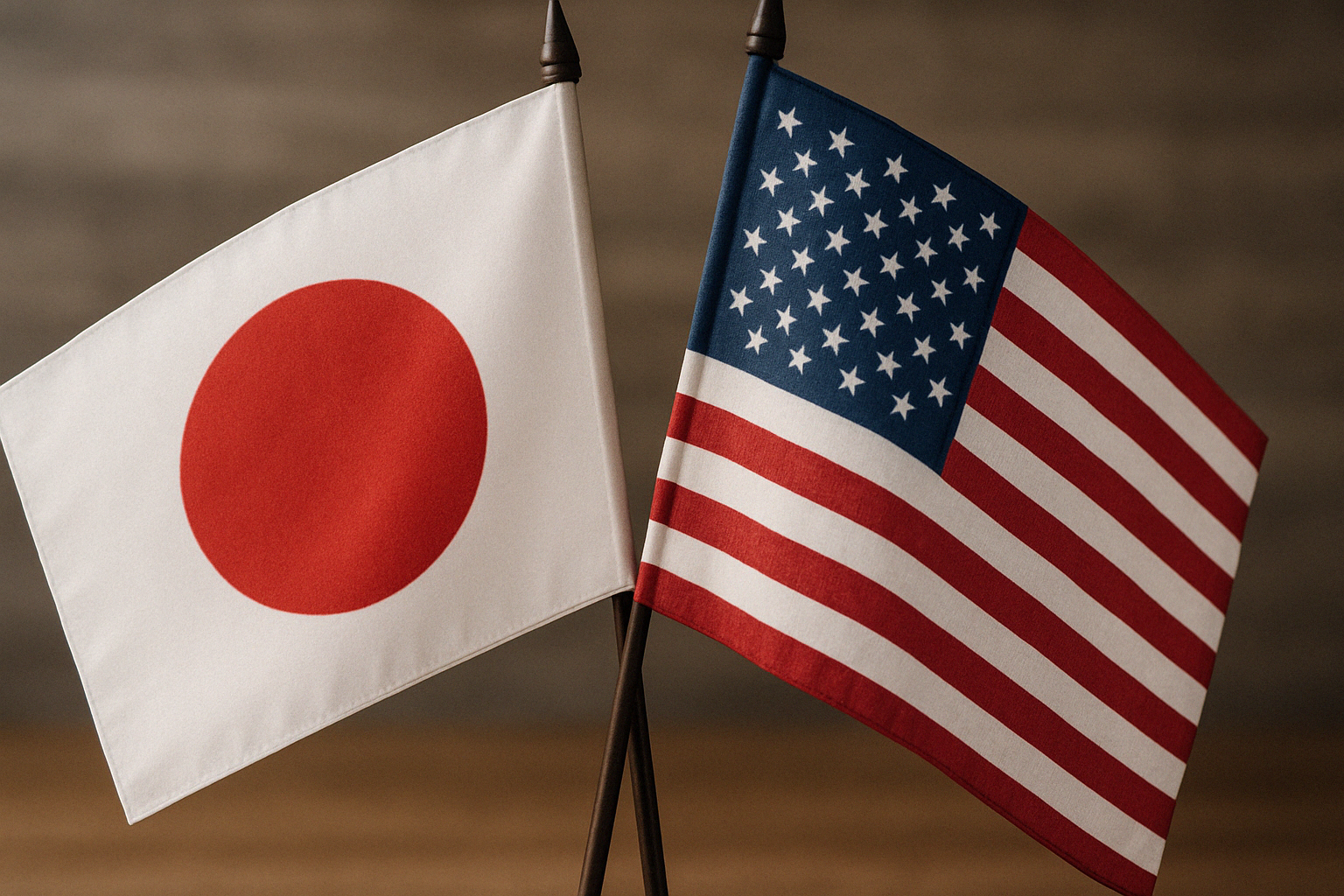
米国と日本の貿易関係は豊かな歴史を持ち、19世紀半ばの初期の接触から、今日見られる複雑な相互依存へと発展してきました。1850年代半ばにペリー提督の来航によって日本の港が開かれて以来、両国間の商業的な結びつきは着実に成長しました。
20世紀に入ると、日本は米国にとって重要な貿易相手国となり、特に第一次世界大戦中とその後に貿易量は大幅に増加しました。戦後、米国は日本の復興に重要な役割を果たし、両国関係は深い経済的基盤を持つ強力な同盟関係へと発展しました。
しかし、1960年代以降、日本の輸出主導型成長、特に自動車と電子機器において、米国との間で貿易不均衡が生じ、1970年代から1980年代にかけて米国で懸念と貿易摩擦を引き起こしました。これらの緊張にもかかわらず、日本企業は米国での製造業への投資を増やし、雇用創出とより深い経済統合を促進しました。
冷戦終結後、中国が主要なグローバル経済大国として台頭し、米国と日本の相対的な貿易の重要性に影響を与えましたが、日米同盟は依然としてアジアにおける米国の外交政策の要であり続けています。
時折摩擦はありますが、米国と日本の貿易関係は依然としていくつかの理由から根本的に重要です: 日本は米国の農産物、エネルギー、機械にとって主要な市場であり、逆に米国は日本の自動車、電子機器、工業製品にとって重要な輸出先です。
2023年の二国間貿易総額は3040億ドルを超え、日本は米国への最大の海外直接投資国であり、約100万人の米国の雇用を支えています。この投資は製造業、特に自動車セクターに集中しています。
経済的パートナーシップは両国間の安全保障同盟と深く結びついており、インド太平洋地域における米国の利益の要となっています。さらに、米国と日本は、AI、半導体、先進原子炉などの重要な分野を含む、科学技術と医療において広範に協力しています。
2025年、米国は貿易不均衡と非相互的な扱いへの懸念を理由に、日本からの輸入品に対して一連の関税措置を実施しました全ての米国輸入品に対して最低10%の関税が課せられ、米国との間で大きな貿易赤字を抱える国(日本を含む)に対しては、より高い「個別化された相互主義関税」として24%の関税が発表されました。
| 対象 | 関税率 | 発効日 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| 全輸入品
(日本含む) |
最低10% | 2025年初頭 | ベースライン関税 |
| 日本など
貿易赤字国向け |
24% | 一時停止中
(2025年4月10日〜 90日間) |
相互主義関税 |
| USMCA非準拠の
完成車 |
25% | 2025年4月3日〜 | 完成車が対象(北米域外) |
| 鉄鋼
(2018年導入分) |
25% | 2025年3月12日〜
再適用 |
日本の免除措置が撤廃 |
| 法的根拠 | – | – | 国際緊急経済権限法
(IEEPA)に基づく実施 |
ただし、この24%の関税は2025年4月10日から90日間一時停止されています(中国を除く)。USMCA非準拠の完全に組み立てられた車両に対して25%の関税が2025年4月3日より発効し、2018年に導入された鉄鋼(25%)に対する日本の免除措置が撤廃され、2025年3月12日より再適用されました。
これらの関税は、貿易不均衡と非相互的な扱いに関する国家非常事態宣言に基づき、国際緊急経済権限法(IEEPA)を行使して制定されました。
日本からアメリカへの主要な輸出品目

| 品目 | 輸出額(推定範囲)[億ドル] | コメント |
|---|---|---|
| 自動車
(鉄道・軌道用以外) |
503〜513 | 最も大きな輸出項目 |
| 機械類 | 320〜361 | 生産設備、工作機械など |
| 電気・電子機器 | 150〜192 | 半導体、コンデンサ等 |
| 光学・精密機器 | 72〜81 | 医療機器、測定機器含む |
| 医薬品 | 25〜74 | 特定製品の急伸が影響 |
日本から米国への主要な輸出品目は、自動車、機械類、電気・電子機器、光学・精密機器、医薬品など多岐にわたります。
2024年の輸出額を見ると、鉄道・軌道用以外の車両が503億ドルから513億ドル、機械類が320億ドルから361億ドル、電気・電子機器が150億ドルから192億ドル、光学・精密機器が72億ドルから81億ドル、医薬品が25億ドルから74億ドルとなっています。
これらの品目は、日米間の貿易関係において重要な役割を果たしており、米国の関税措置の影響を大きく受けることになります。

米国による新たな関税措置は、日本経済に対して複数の経路から下押し圧力を加える可能性があります。中でも自動車産業への影響は大きく、25%の輸入関税により輸出減少が予想されるほか、生産の一部を米国へ移す動きは日本国内の雇用喪失を招く恐れもあります。これにより、日本のGDP成長率は低下するリスクにさらされており、雇用面でも輸出型産業への影響が避けられません。
| 分野 | 影響内容 | 影響の度合い |
|---|---|---|
| 自動車産業 | 25%の高関税により輸出コストが増大し、米国市場での競争力が低下 | 非常に大きい |
| 電子機器・
半導体 |
関税によるコスト増加。ただし対中競合製品に比べ優位性を得る可能性あり | 中程度〜大きい |
| 機械・
工作機械 |
米国市場での需要減少と価格競争力の低下が懸念される | 大きい |
| 医薬品・
精密機器 |
主要輸出品目のひとつだが、関税の影響は限定的 | 小さい |
| 貿易収支 | 短期的に黒字拡大も、長期的には輸出減により黒字縮小の可能性 | 中程度 |
| 為替・
物価 |
ドル高による輸出競争力低下と、原材料コスト増による物価上昇圧力 | 間接的だが注視必要 |
| サプライチェーン | 調達・生産体制の見直しを迫られる可能性が高い | 中程度〜大きい |
| 投資戦略 | 米国への投資意欲が減退し、リスク分散が加速 | 中程度 |
電子機器やハイテク分野では、関税によるコスト増加が避けられないものの、対中国との相対比較では競争優位性を得る可能性もあります。ただし、これらの産業でも米国市場における利益率の低下が報告されており、全体としては厳しい事業環境が続いています。
さらに、機械産業を含む資本財分野では、米国市場へのアクセス制限が顕著となり、対米輸出の減少と設備投資の抑制が懸念されます。非電気機械分野は特に影響を受けやすく、日米間の貿易構造に変化をもたらす可能性があります。
また、為替市場におけるドル高は、日本製品の価格競争力を他市場で低下させる要因となり得るうえ、米国関税によって発生する原材料価格の上昇は、間接的に日本国内の物価上昇を引き起こす懸念もあります。
このように、関税の影響は単一の産業にとどまらず、成長、雇用、物価、貿易構造といった複数の経済要素に波及する広範なリスクを内包しているため、今後の動向については継続的かつ多角的な分析が必要です。
日本政府の貿易政策
日本政府は、米国関税に対して様々な対策と交渉努力を行っています: 日本の当局者は、特に自動車と鉄鋼に対する関税の免除を求めて米国政府に働きかけており、石破首相は当初、米国への多額の投資により関税を回避できるだろうという楽観的な見方を表明していました。
しかし、これまでのところ免除の要求は拒否されています。日本は非対立的なアプローチを取り、石破首相は当面の間、報復措置を課すことを否定し、二国間交渉を優先しています。日本は米国債保有を交渉の手段として使用する計画もないとされています。日本政府は、影響を受けた産業、特に中小の自動車部品メーカーに対する相談窓口の設置や財政支援の拡大などを行っています。
直ちに報復を避けているものの、日本は「あらゆる種類の対抗措置」を検討しており、米国関税の問題を世界貿易機関(WTO)に提起することも示唆されています。また、米国市場への依存を減らし、東南アジアとアフリカでの取り組みを強化する必要があるかもしれません。
米国は日本との間で約680億ドルの物品貿易赤字を抱えており、その大部分(78%)は自動車および自動車部品の貿易によるものです。2025年2月の日本の対米輸出は10.5%増加し、対米輸入は2.7%減少したため、日本は黒字になりました。これは、企業が関税前に出荷を急いだことが原因である可能性があります。
長期的には、米国関税は日本から米国への輸出量の減少につながり、日本の対米貿易黒字を縮小させる可能性が高いと予想されます。
日本の企業は、新たな関税体制に適応するために、生産拠点の調整、在庫水準の管理、潜在的な調達および製造拠点の多様化など、さまざまな戦略を実施しています。一部の日本の自動車メーカーは米国市場向けの日本での生産を削減する可能性があり、関税の影響を軽減するために米国で商品を在庫している企業もあります。
ホンダは、メキシコではなくインディアナでハイブリッド車を生産する計画を発表しています。新たな関税は、輸入部品や材料に対する関税に関連するコスト増加と、将来の貿易政策を取り巻く不確実性のため、日本企業の米国へのさらなる投資意欲を低下させると予想されます。
米国の関税は、より広範な地政学的な緊張と相まって、日本企業に投資ポートフォリオの多様化を促し、米国と中国の両方から他の新興市場または日本への資本移動を促す可能性があります。
米国が中国に課している関税水準は、日本に課している水準よりも大幅に高く、中国からの輸入品に対する関税は最大145%に達しています。一方、日本からの輸入品に対する関税は、相互主義関税が一時停止されている間は10%のベースライン関税が主となります。
この関税率の差は、特定の分野において日本が米国市場で競争優位性を得る機会を生み出す可能性があります。日本と中国の両国は米国関税によるマイナスの経済的影響を受けると予想されますが、より高い関税率と二国間貿易の規模を考慮すると、中国への影響はかなり大きい可能性が高いです。
日本は、貿易転換から限定的な利益を得る可能性さえあります。米国関税に対する日本と中国政府の対照的な対応は、両国の異なる戦略的優先事項と米国とのそれぞれの関係を反映しています。中国は報復措置を含むより対立的な姿勢を採用している一方、日本は同盟関係を優先し、外交的解決を模索しています。
最近の関税措置にもかかわらず、米国と日本は既存の貿易協定、すなわち2020年1月に発効した日米貿易協定(USJTA)を結んでいます: この協定は主に農産物とデジタル貿易に焦点を当てた部分的な合意であり、約72億ドル相当の米国農産物の対日輸出に対する関税を撤廃または削減します。
注目すべき点として、この協定は自動車を対象としていません。しかし、両国はより包括的な貿易協定に向けたさらなる交渉に関心を示しており、現在の関税環境はこれらの議論に複雑さを加えています。
長期的な影響と今後の展望
米国関税の長期的な影響は依然として不確実です: 自動車および自動車部品に対する関税は、日本にUSJTAの一時停止を促し、米国の対日農産物輸出に損害を与える可能性があります。
継続的な関税は、将来の日本から米国への投資を抑制し、経済協力と雇用創出に影響を与える可能性があります。より広範な地政学的状況、特に米中貿易摩擦は、日米貿易関係に影響を与え続けるでしょう。今後のより包括的な貿易協定に向けた交渉の可能性は残されていますが、現在の関税環境はこれらの議論に複雑さを加えています。
業界団体・専門家の分析

日本自動車工業会(JAMA)
日本自動車工業会(JAMA)は、自動車関税が米国と日本の経済に悪影響を及ぼす可能性があると警告しています。また、生産調整の可能性も指摘しており、自動車関税により日本のGDPが約0.2%押し下げられるとの予測もあります 。JAMAは、日本政府に対し、米国政府との間で関税免除に向けた交渉を行うよう強く求めています。
日本工作機械工業会(JMTBA)が発表したデータによると、2025年初頭には工作機械の受注額が減少しており 、関税による不確実性が機械産業の先行きに懸念をもたらしていることが示唆されています。台湾機械工業会は、米国の関税が日本と比較して台湾の機械産業に厳しい打撃を与える可能性があると分析しており 、日本の市場シェアにも影響が出る可能性があります。
エコノミストたちは、米国の関税が日本のGDPを0.2%から1.8%押し下げる可能性があると予測しています。また、輸出成長の鈍化と米国におけるインフレの加速も予想されています。
米国による関税措置の事例
1980年代のレーガン政権による日本の電子機器に対する関税は、米国の貿易赤字を大幅に削減するには至らず、むしろ米国の競争力を損なう可能性もありました。2018年にトランプ政権が実施した鉄鋼とアルミニウムに対する関税は、米国内の生産量を一時的に増加させたものの、報復関税を招き、関連産業のコストを上昇させました。
また、1980年代のプラザ合意は、円高を引き起こし、日本の経済に大きな影響を与えました 。これらの過去の事例は、米国の関税措置が必ずしも意図した効果をもたらすとは限らず、予期せぬ結果を招く可能性もあることを示唆しています。
米国が日本からの輸入品に対して再び関税を課したことは、単なる通商措置ではなく、長年にわたる複雑で戦略的な日米経済関係の中で非常に重要な転換点といえます。短期的な経済的影響はまだ不透明であるものの、自動車産業をはじめとする日本の主要輸出産業にとっては深刻なリスクが存在し、企業経営や産業政策に対する影響は無視できません。
日本政府が即時的な対抗措置ではなく、冷静な交渉による解決を優先していることは、米国との同盟関係と地域的安定性への配慮が背景にあります。しかし、既存の貿易協定の今後や、米中を含めた地政学的な構図の変化に照らして考えると、今後の影響を見通すには一層の分析と対応が求められます。
本稿が提示した内容は、複雑な通商政策の一端にすぎません。とりわけ、自社の事業戦略や貿易実務に直接関わる方々にとっては、より詳細な法的・経済的助言が必要となる場面も多いはずです。状況の変化は早く、かつ多岐にわたる可能性があるため、ぜひ一度、貿易・通商分野の専門家にご相談されることを強くおすすめいたします。
刻一刻と動く国際情勢の中で、確かな情報と専門的知見に基づく判断が、将来の安定と成長を支える鍵となるでしょう。
カテゴリ:製品別貿易ノウハウ
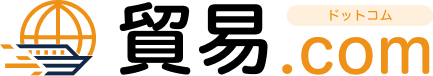






 X(旧Twitter)
X(旧Twitter)