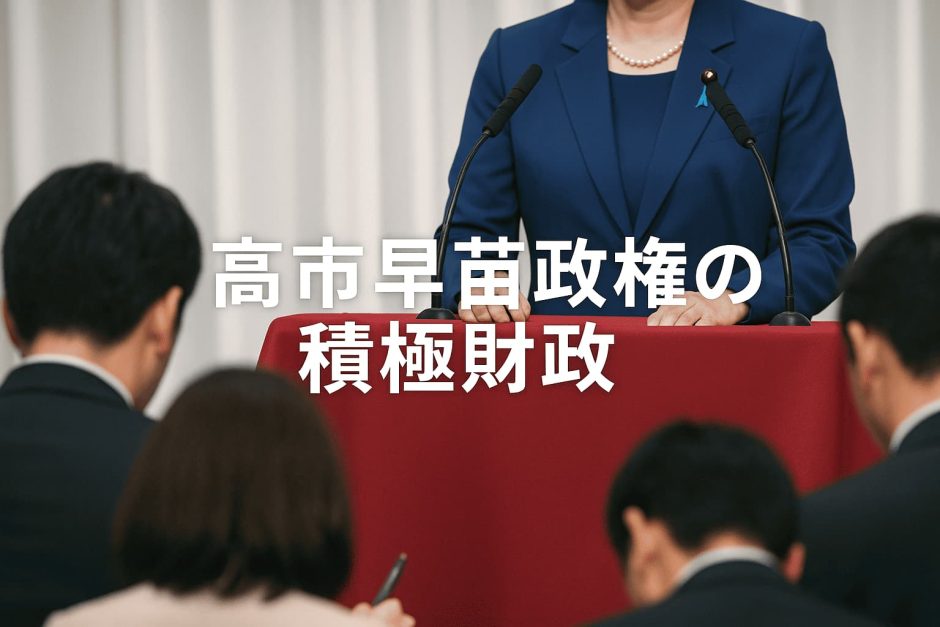2025年10月24日、高市早苗首相は「責任ある積極財政」を新たな経済方針として正式に打ち出しました。防衛やAI・半導体といった成長分野に積極的に予算を投じることで、日本経済の立て直しを図る構想です。
この記事では、初心者の方にもわかりやすく、高市政権の政策が私たちの暮らし、企業活動、そして国際取引にどのような影響を与えるのかを丁寧に解説していきます。
「積極財政」を掲げる高市早苗政権の狙いとは?

高市早苗首相が打ち出した「責任ある積極財政」は、財政支出を通じて景気を押し上げる成長重視の政策です。2025年度の補正予算では、防衛・子育て・技術投資を柱とする十数兆円規模の経済対策が報道各社で検討中と伝えられています。
これまでの「財政健全化路線」との違い
この積極財政は、近年アメリカやEUでも注目されている「財政出動型の成長戦略」に近く、日本でもようやく本格導入が進もうとしています。
日本の財政政策は長年、「財政健全化」を重視してきました。国の借金はGDPの2倍以上に達し、2024年度末時点では国と地方の債務残高が1,200兆円を超える見通しです。そのため、増税や歳出抑制によって財政赤字を抑えることが最優先とされてきました。
とくに社会保障費の増加が続く中では、支出の厳格な管理が不可欠とされ、「プライマリーバランス(基礎的財政収支)の黒字化」という目標が政府方針として何度も掲げられてきました。
しかし高市政権は、こうした均衡重視のアプローチでは日本経済の成長力を十分に引き出せないと判断。
そこで掲げられたのが、成長分野への戦略的支出を中心とする「積極財政」への転換です。短期的には一定の財政赤字を容認しつつ、中長期では税収増による財政健全化、つまり「成長による財政再建」を目指す姿勢が明確になっています。
「積極財政」はお金を回して経済を元気にする方針
積極財政とは、政府が需要の創出に積極的な役割を果たすことで、景気や民間投資を下支えする政策です。特に景気が低迷する局面では、民間の消費や投資が慎重になりやすいため、政府支出が経済の下支えとして重要な役割を担います。
具体的には、公共事業の拡充、企業への設備投資支援、家計への給付措置などが典型例です。こうした支出は、即効性を持ちながら波及効果も大きく、雇用や所得の増加を通じて経済の好循環を促す狙いがあります。
以下は、「財政健全化」と「積極財政」という異なるアプローチを比較したものです。
| 項目 | 財政健全化路線 | 積極財政路線 |
|---|---|---|
| 支出の方針 | 抑制的 | 拡張的(必要な支出は実施) |
| 目的 | 債務抑制、財政赤字の縮小 | 景気回復、産業支援 |
| 主な施策 | 増税、歳出削減 | 減税、補助金、公共投資 |
「責任ある」の意味は?無駄遣いしない前提の投資
「責任ある積極財政」という表現には、支出拡大と同時に、その使い道の明確化を求める姿勢が込められています。単なるばらまきではなく、経済安全保障や技術革新、育児・教育支援など、将来の成長が期待される分野への投資が前提とされています。
また、高市首相は、国債発行への過度な依存を避けつつ、官民が連携して成長を支える仕組みづくりを重視する姿勢を示しています。所信表明演説でも「民間活力の最大限の活用」を強調しており、公共と民間が協調することで支出効果を高め、財政の持続可能性との両立を図る方針です。
高市早苗首相の積極財政、具体的な支出先は?注目の分野を解説

高市政権の積極財政は、約15兆円規模の補正予算に基づき、防衛、子育て、技術投資など複数の重点分野に配分される予定です。これは「成長と安定の両立」を掲げた戦略的な財政出動であり、分野別の支出内容が日本経済の構造に影響を与えると注目されています。
防衛費の増加で関連企業に追い風
防衛費の増額は、政権が掲げる「経済安全保障」の中核に位置づけられています。また、高市首相は、国債発行への過度な依存を避けつつ、官民が連携して成長を支える仕組みづくりを重視する姿勢を示しています。
所信表明演説では「民間活力の最大限の活用」を強調したほか、国家安全保障戦略で定める対GDP比2%水準について「補正予算と合わせて、今年度中に前倒して措置を講じる」と明言しました。
公共と民間の協調によって支出効果を高め、財政の持続可能性との両立を図る方針です。
具体的な施策としては、自衛隊の装備近代化、サイバー防衛体制の強化、ミサイル迎撃システムの更新などが挙げられます。これにより、造船、電子部品、センサー、素材開発といった関連業種に波及効果が及ぶと期待されています。
また、防衛関連のサプライチェーンを国内に戻す動きもあり、部品調達や製造の国産化が進む可能性も高まっています。
AI・半導体支援は輸出にもつながる分野
成長戦略の柱として注目されるのが、AIや次世代半導体などの先端技術分野です。政府は新たに「日本成長戦略会議」を設け、研究開発支援、製造拠点の誘致、先端人材の育成を一体的に進める方針を打ち出しています。
これは国際競争力の回復と供給網の強化を同時に実現するための施策です。
たとえば、北海道・千歳で建設が進むラピダス社の半導体新工場は、政府による数千億円規模の補助金支援を受けた象徴的なプロジェクトです。こうした国内製造体制の整備は、供給網の強靱化だけでなく、高付加価値製品の輸出拡大にもつながると期待されています。
さらに、日米・日台間での技術連携が進めば、日本の製品が再びグローバルサプライチェーンの中心的存在となる可能性もあります。これは単なる国内産業保護ではなく、「輸出競争力の再構築」に直結する成長戦略と言えるでしょう。
高市政権の積極財政は、防衛やAI・半導体などの成長分野を中心に支出を拡大し、日本経済を「守り」と「攻め」の両面から立て直す狙いがあります。財政赤字を容認しつつも、成長による税収増で再建を目指す点が特徴です。
税制改革や給付で家計支援も視野に
積極財政のもう一つの柱は、家計への支援です。高市政権は、物価高対策として「給付付き税額控除」の導入を視野に入れ、子育て支援や教育費負担の軽減といった家計基盤の強化策を進めようとしています。
これらの施策は、消費の下支えや生活安定だけでなく、将来的な成長基盤づくりという視点も含まれています。実質的な可処分所得の向上は、企業活動の活性化や雇用拡大にもつながると考えられています。
税と社会保障の制度改革に関しては、給付付き税額控除の導入や、超党派・有識者による「国民会議」の設置といった取り組みが検討課題として挙げられています。いずれも、制度の持続可能性や所得再分配のあり方を見直すための議論であり、今後どのように具体化していくかが注目されています。
高市早苗政権の積極財政が貿易にも波及、国際取引への影響とは

積極財政による大規模な政府支出は、為替相場やコスト構造を通じて、国際貿易の現場にも直接的な影響を及ぼします。とくに輸出入に携わる企業にとっては、為替リスクや物流変化への対応が今後ますます重要になるでしょう。
円安が続けば、輸出に有利・輸入に不利
積極財政による支出拡大は、国債発行増 → 長期金利上昇 → 円安圧力という経路を通じて為替市場に作用します。とくに日銀の金融緩和姿勢と連動する形で財政拡大が進めば、円安基調が継続する可能性が高まります。
円安が進行すれば、輸出企業は為替差益を得やすくなり、製品価格の国際競争力が高まります。とくに自動車、機械、精密機器などは恩恵を受けやすく、外需拡大による企業収益の押し上げが期待されます。
一方、原油・LNG・穀物・医薬品といった輸入品目では、円安による仕入れ価格上昇が企業の利益を圧迫します。エネルギー、食品、医療といった業種では、価格転嫁やコスト管理がより難しくなるでしょう。
さらに、財政拡大と金融政策の連携次第では、金利上昇圧力が強まり、円相場の変動幅が拡大するリスクもあります。貿易企業にとっては、こうした為替変動への備えが不可欠です。
| 影響項目 | 円安の影響 |
|---|---|
| 輸出企業 | 為替差益で価格競争力上昇(自動車、機械、精密機器など) |
| 輸入企業 | 原材料コスト増で利益圧迫(燃料、穀物、医薬品など) |
| 消費者 | 輸入品価格の上昇で物価高圧力 |
投資先によっては貿易チャンスも広がる
積極財政で優先されるAI・半導体・クリーンエネルギーなどの先端分野は、貿易機会の拡大にもつながります。政府の支援を受けた高付加価値製品は、海外市場での競争力強化が期待されます。
たとえば、ラピダス社の半導体工場のような国内生産拠点は、供給網の安定化とともに輸出拡大の起点となり得ます。技術力を活かした製品のグローバル展開によって、輸出構造が従来の素材・部品型から付加価値型へと転換していく可能性もあります。
また、自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)との連動による関税緩和や市場アクセス改善が進めば、日本企業にとっては海外販路の拡大というメリットも加わります。財政支出が単なる国内対策にとどまらず、貿易政策と結びついて相乗効果を生む展開も見込まれます。
物流や港湾インフラ整備にも注目を
インフラ整備への財政投入は、貿易実務にも直接影響します。積極財政において、港湾・空港・高速道路といった輸送インフラの整備が進めば、輸送コストの削減や通関時間の短縮によって、企業の貿易効率が向上します。
また、国内生産回帰や部品調達の多角化を促す補助金制度の整備も検討されており、サプライチェーン見直しの後押しとなるでしょう。とくに海外依存度の高い企業にとっては、国産パートナーとの連携強化や調達ルートの多様化が現実的な選択肢として浮上します。
中小企業にとっては、こうしたインフラ整備や制度改革が海外市場へのアクセス改善につながります。制度と物流の両面から貿易環境が整えば、日本全体として輸出基盤の底上げが期待されます。
積極財政の行方と高市早苗政権の今後の焦点―補正予算と制度改革に注目

高市政権の積極財政は、理念から実行段階へと本格的に進みつつあります。今後は、財源の使い方と制度設計、そして実効性ある運用が注目されます。
どの分野にいくら配分されるかが焦点
政府は2025年度の補正予算として、およそ15兆円規模の経済対策を検討中です。重要なのは、予算の総額ではなく支出の配分比率と優先順位。たとえば、防衛費に重点を置くのか、AI・半導体や子育て支援に厚く配分するのかによって、政策の方向性や国民生活への影響は大きく異なります。
さらに、単年度で完結する短期的支出ではなく、中長期的に波及効果のある「投資的支出」への重点が求められます。具体的には、人材育成や国内拠点への補助金といった、継続的成長を狙う施策が評価の分かれ目になるでしょう。
企業も家計も、円安・金利の変化に備えるべき
積極財政による国債増発は、長期金利の上昇を引き起こし、企業や家計に波及します。企業にとっては資金調達コストや設備投資計画への影響が避けられず、戦略の見直しを迫られるケースも出てくるでしょう。
個人でも、住宅ローンや教育費など変動金利型の借入を抱える層にとっては、金利上昇リスクへの対応が重要です。支出の見直しや金融リテラシーの向上は、今後の生活防衛の基本となります。
また、仮に財政への信認が揺らげば、日本国債の売却圧力や為替の急変動といった副次的リスクも生じます。企業も個人も、「積極財政の副作用」への備えを冷静に進めておく必要があります。
円安が続くと、輸出産業には追い風となります。日本の主要な輸出品や輸出先の動向については、以下の記事で詳しく解説しています。

制度改革や外国人政策の行方も要注目
積極財政と表裏一体で議論されるべきなのが、社会制度の再構築です。たとえば少子高齢化や人手不足への対応を誤れば、いくら財政出動しても持続的な成果は得られません。
政府内では、防衛・医療・介護・インフラといった分野での外国人材の受け入れ拡大が議論されています。これは単なる労働力の補完ではなく、担い手不足を補いながら、国家戦略としての生産体制を維持するための重要なテーマと位置づけられています。
今後の制度設計や、経済安全保障との整合性が注目される分野です。
また、税制の見直しや社会保障制度の改革も急務です。特に給付付き税額控除の導入や超党派の国民会議の設置といった新たな提案は、世代間の公平性や財政の持続性をどう保つかという根本課題に向き合うものであり、今後の政治的な実行力が試される場面となるでしょう。
制度改革により、貿易協定の活用も一層重要になってきます。USMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)の影響や日本企業への展開については、以下の記事をご参照ください。

まとめ
高市首相の「責任ある積極財政」は、日本経済を活性化させる新しいアプローチとして、大きな注目を集めています。防衛や成長産業への投資、そして家計支援や制度改革など、多くの政策が動き出すことで、景気や物価、為替といった身近なテーマにも影響が出てきます。
特に、為替の動きや支出の方向によっては、企業活動や貿易の戦略を見直す必要が出てくるかもしれません。これから年末にかけて、補正予算や総合経済対策の内容が明らかになっていく中で、最新の情報を正しく読み取ることが大切です。
今後の経済変化に備えるためにも、不安があれば専門家に一度相談してみることをおすすめします。