仮想通貨の中でも「価格の安定性」を特徴とするステーブルコインは、今や投資家だけでなく、実務面での金融インフラとしても注目されています。これまで価格変動の大きさが課題とされていた暗号資産市場において、ステーブルコインはその安定性ゆえに、決済・送金・資産保全といった幅広い分野で利用が広がりつつあります。
日本では、2023年に改正資金決済法が施行されたことを契機に、ステーブルコインに関する法的枠組みが明確化されました。さらに2025年8月には、金融庁が初めて国内発行の円建てステーブルコイン「JPYC」を承認し、同年秋の正式発行が予定されています。これは、日本におけるデジタル通貨政策と金融革新の大きな節目となるでしょう。
本記事では、ステーブルコインの基礎知識から始め、日本国内における法規制、国際貿易への応用、日本と海外の事例比較、そして今後の課題と展望までを包括的に解説します。
ステーブルコインとは何か:日本における定義と種類
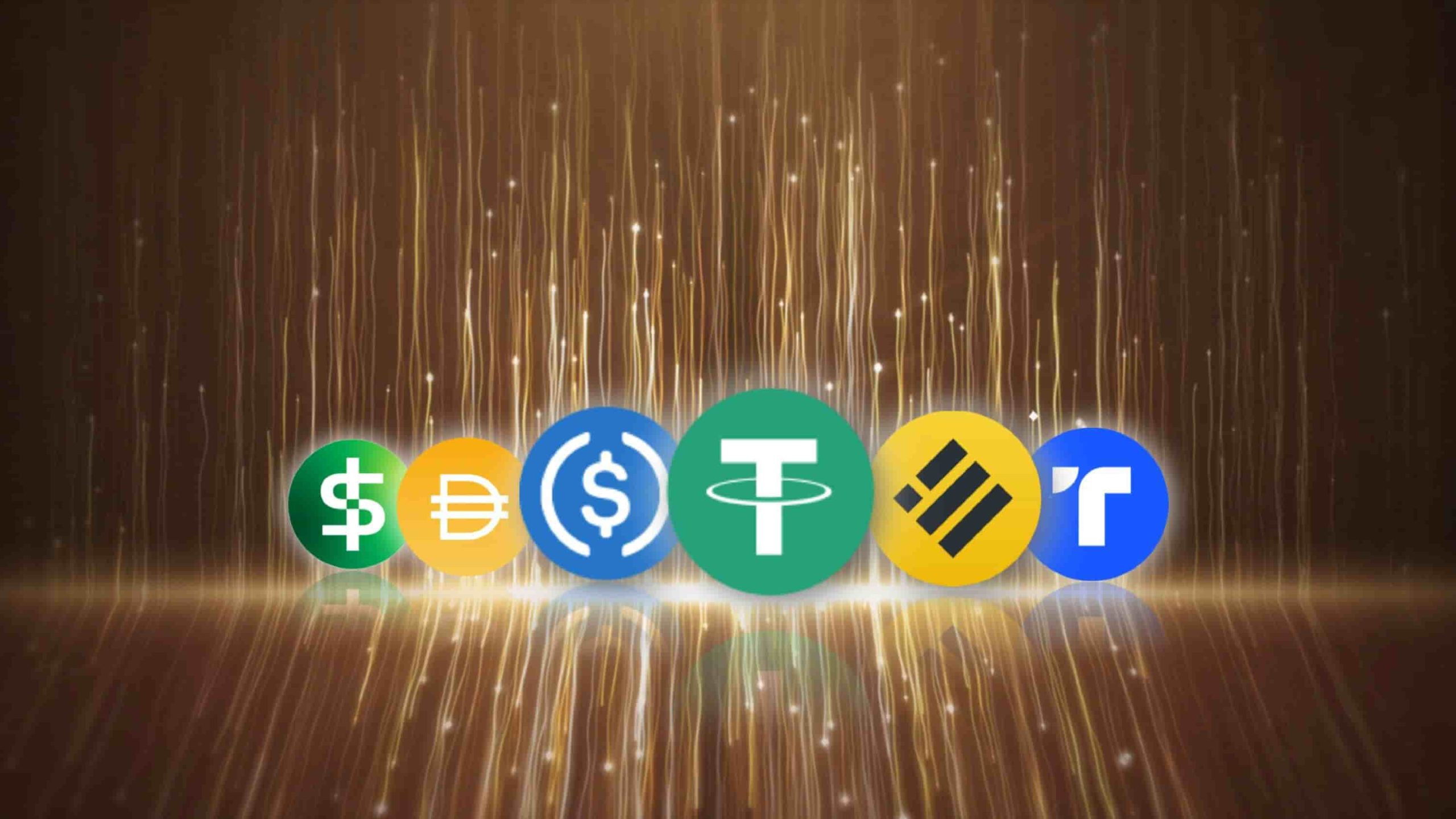
ステーブルコインとは、ブロックチェーンを基盤としつつ、法定通貨のような価格安定性を保つことを目的としたデジタル通貨です。ビットコインやイーサリアムのように値動きの激しい暗号資産とは異なり、ステーブルコインは円やドルといった現実の通貨や資産に価値を連動させることで、取引や決済における安定した利用が可能になります。
日本では、ステーブルコインは投機的な投資商品というよりも、「電子決済手段(Electronic Payment Instruments)」として制度的に定義され、実際の決済インフラの一部としての活用が進められています。
日本における法的定義と制度上の位置づけ
2023年6月に施行された改正資金決済法により、ステーブルコインは新たに「電子決済手段(Electronic Payment Instruments:EPI)」として制度上の位置づけが明確化されました。これは、法定通貨と価値を連動させた安定したデジタル通貨を、安全かつ実務的に活用するための法的枠組みです。
この制度では、次のような3つのプレイヤーが明確に定義されています:
| プレイヤー | 役割 | 規制主体 |
|---|---|---|
| 発行者 | ステーブルコインの発行・担保管理 | 銀行・信託会社・登録資金移転業者 |
| 仲介業者 | ウォレット提供や流通管理 | 登録制の「電子決済手段取扱業者」 |
| 利用者 | ステーブルコインを利用する 企業・個人 | 消費者保護の対象 |
この制度により、発行から流通、利用に至るまでのフローが制度的に整理され、金融庁および日本銀行の監督のもとで透明性の高い運用が可能となっています。
ステーブルコインの主要3タイプ:日本国内外での実態
ステーブルコインは、価格の安定性をどのように担保するか(=ペグの仕組み)によって、主に3つのタイプに分類されます。
| タイプ | 価値裏付け | 日本での導入状況 |
|---|---|---|
| 法定通貨担保型 | 円・ドルなどの預金や国債で担保 | JPYC、Progmat Coin などで 実装進行中 |
| 暗号資産担保型 | ビットコインやイーサリアム等を ロックして担保 | 日本では普及途上、 海外ではDAI等が先行 |
| アルゴリズム型 | スマートコントラクトで発行・供給量を自動調整 | 日本では未普及。 米国でもUST崩壊で信頼低下中 |
それぞれの仕組みを詳しく見ていきます。
1.法定通貨担保型ステーブルコイン(Fiat-Collateralized)
これは日本国内で最も実装が進んでいる方式です。発行体が、日本円や米ドルを銀行口座や信託に預け、それと同額のトークンを発行する形式です。担保資産が明確に保全されていることから、金融庁の監督制度とも高い整合性があり、日本国内で最も導入が進んでいるタイプです。
代表例:
- JPYC(株式会社JPYC):2025年秋に正式発行予定。日本国債や預金で担保。
- Progmat Coin(三菱UFJ信託):大手金融グループによるブロックチェーン対応のステーブルコイン。
2.暗号資産担保型ステーブルコイン(Crypto-Collateralized)
こちらは、仮想通貨(例:ETH、BTC)をスマートコントラクトで担保にしてステーブルコインを発行するモデルです。価格の変動に備えて過剰担保を前提とするため、資産効率が悪くなることもあります。
代表例(日本国外):DAI(MakerDAO):ETHなどを担保にした分散型ステーブルコイン。
日本国内では、法的リスクの観点から導入事例は限定的です。
3.アルゴリズム型ステーブルコイン(Algorithmic)
供給量の調整(ミント・バーン)によって価格を維持するステーブルコインです。中央管理者が存在しない分、完全な分散性を追求できますが、UST(TerraUSD)の崩壊のように、安定性を維持できなくなるリスクが顕在化しています。
日本では、金融当局の規制の観点から現在のところ認可・実装されていません。
日本が法定通貨担保型を推進する理由
日本の金融政策は、「ステーブルコイン=電子マネーの延長ではなく、通貨に代わる新たな金融インフラ」として捉える立場を取っています。特に円建てステーブルコインに対しては、以下のような理由から法定通貨担保型が推奨されています:
- 信託や預金による透明性と信頼性
- 価格変動リスクの極小化
- 金融庁の監督下に置きやすい制度設計
- 国内企業との連携に適した設計
今後、地方銀行や信用金庫の参入が進めば、地域通貨との連携や地場産業のデジタル化にも貢献できる可能性が高まります。
日本におけるステーブルコインは、改正資金決済法を基礎として法的に整理されています。2025年には金融庁が「JPYC」を正式に認可するなど、制度的な枠組みが整いつつあります。
日本初の円建てステーブルコイン「JPYC」の承認と発行計画
| 項目 | 内容 | 意義 |
|---|---|---|
| 発行体 | 登録資金移転業者(JPYC社) | 日本円ペッグの実現 |
| 担保資産 | 銀行預金・日本国債 | 安定性・法的裏付け |
| 利益構造 | 利子収入(手数料ゼロ) | 透明性・ユーザー負担軽減 |
2025年8月、ステーブルコイン「JPYC」の発行を手がけるJPYC株式会社は、金融庁より資金移転業者としての登録認可を取得。これにより、日本初となる法的に認可された円建てステーブルコインが、2025年秋に正式に発行される見通しです。
ステーブルコインと日本の法制度:規制・登録・最新方針

日本では、ステーブルコインの発行・流通は、ビットコインなどの暗号資産とは異なる専用の法制度(電子決済手段制度)に基づき、厳格に規制されています。背景には、価格安定性の確保だけでなく、決済インフラや国際送金への実務的な応用を促進する狙いがあります。
日本の改正資金決済法におけるステーブルコインの位置づけ
改正資金決済法(2022年成立・2023年施行)により、ステーブルコインは新たに「電子決済手段(Electronic Payment Instruments、以下EPI)」として制度的に定義されました。これにより、暗号資産とは異なるルールのもとで、決済や商取引への活用が可能なデジタル通貨として明確に位置づけられています。
電子決済手段(Electronic Payment Instruments)とは
EPIとは、特定の発行者により発行され、他者に譲渡することで実際の決済手段として機能する電子的な価値です。通貨そのものではないものの、法定通貨に連動した価値を持ち、実務上の通貨代替手段として位置づけられます。
具体的には以下の3点が定義要件となっています。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 発行主体の明確化 | 銀行、信託会社、資金移転業者等が発行可能 |
| 通貨との連動 | 一定の価値を持ち、価格が法定通貨に連動 |
| 移転可能性 | 他人に譲渡・使用できる電子的価値 |
この制度設計により、ステーブルコインは投機的な暗号資産ではなく、日常的な送金・決済に使える信頼性の高いツールとして制度的に整理されました。
ステーブルコイン発行における登録・監督体制
ステーブルコインの制度上の柱は、「発行の担保責任」と「管理の信頼性」の確保です。改正資金決済法では、発行者と取扱業者に対し、それぞれ登録義務と監督体制を設けています。
発行者(Issuer)としての資格要件
発行者として登録できるのは、以下のように一定の金融ライセンスを持つ事業者に限定されています。
- 銀行(例:メガバンク、地方銀行)
- 信託会社(例:三菱UFJ信託銀行)
- 資金移転業者(登録制)
例:JPYC株式会社(2025年8月に認可取得)
これにより、利用者から預かった資金や担保資産が信託分別管理される仕組みが制度上担保されています。
電子決済手段取扱業者としての登録義務
ステーブルコインを流通させるためのウォレット事業者やプラットフォーム提供者は、「電子決済手段取扱業者」として登録が必要です。主な義務は以下の通りです:
- KYC/AML(顧客確認とマネロン対策)
- 取引記録の保存
- セキュリティ基準への準拠(サイバーセキュリティ対策)
こうした体制により、EPIを扱う事業者はKYCやAMLへの対応を通じて、マネーロンダリング対策や利用者資産の保護に取り組むことが義務化されています。
最新動向:JPYCの承認と新たなステーブルコイン戦略
2025年8月、金融庁が日本初の円建てステーブルコインを承認
2025年8月、JPYC株式会社が資金移転業者として金融庁から正式に登録認可を受け、日本で初となる法的に認可された円建てステーブルコイン「JPYC」が、2025年秋に発行予定となりました。
| 項目 | 内容 | 意義 |
|---|---|---|
| 発行予定 | 2025年秋 | 日本で初の法認可ステーブルコイン |
| ペッグ通貨 | 日本円(1 JPYC = 1 JPY) | 為替リスクなし、実務活用へ期待 |
| 担保資産 | 銀行預金・日本国債(JGB) | 安全性と透明性の両立 |
| 利益モデル | 利子収入/手数料ゼロ | ユーザー負担なし、商用展開しやすい |
JPYCは、スマホ決済やBtoB送金、越境ECなど、商用領域への応用可能性が高く、実装段階に入ったステーブルコインとして注目を集めています。
ステーブルコインとCBDC(中央銀行デジタル通貨)との違い
ステーブルコイン(民間発行型)とCBDC(中央銀行発行型)は、役割や設計思想が異なりますが、将来的には共存し、役割分担をすることが期待されています。
| 比較項目 | ステーブルコイン(例:JPYC) | CBDC(日本銀行デジタル円) |
|---|---|---|
| 発行主体 | 民間企業(銀行・信託等) | 日本銀行 |
| 価格安定性 | 担保資産によって維持 | 国家が保証する |
| 利用対象 | 主に民間の取引・商用 | 公的インフラ、全国民対象 |
| 現状 | 実用化フェーズ(JPYC) | 実証実験中(発行時期未定) |
両者は補完的に機能する可能性があり、日本政府・日銀も両制度の並行活用を視野に入れています。
日本における制度の意義と今後の課題
日本の制度は、国際的に見ても透明性・信頼性の高さで評価されており、商用化に向けた堅実なインフラ整備が進んでいます。一方で、次のような課題にも対応していく必要があります。
- 国際的な規制との整合(FATF、BIS等との連携)
- 地方銀行や中小金融機関の参入支援
- 地方自治体との社会実験(例:地域通貨型ステーブルコイン)
ステーブルコインと日本の貿易実務:国際決済への応用可能性

際貿易においては、為替変動リスクや送金コスト、着金遅延などが長年の課題となってきました。とくに円建てでの国際取引は、為替ヘッジや送金プロセスの煩雑さから、中小企業にとって導入のハードルが高い分野でもあります。
こうした課題に対して、日本で実用化が進む円建てステーブルコイン(例:JPYC)は、為替安定性・即時性・低コストという特長を備え、円ベースでの国際決済を可能にする新たな決済手段として、貿易実務における注目度が高まっています。
ステーブルコインが日本の国際貿易にもたらすメリット
従来の貿易決済では、主に以下の2つの方法が使われています。
- 信用状(L/C:Letter of Credit)
銀行が輸出者に代金支払いを保証する仕組み。安全性は高いが、発行手数料・書類のやりとり・時間がかかる。 - 電信送金(T/T:Telegraphic Transfer)
銀行間送金による直接支払い。スピードはあるが、着金確認や送金手数料、為替変動リスクが課題。
ステーブルコインを活用することで、従来の貿易決済と比較して、中小輸出入業者を中心に次のような具体的な利点が得られます。
1. 為替リスクの回避とコストの削減
日本円に価値を連動させたステーブルコイン(例:1 JPYC = 1円)を使用すれば、円建てで価格を固定したまま海外送金・決済が可能になります。為替レートの変動によるリスクをヘッジしながら、コストを予見しやすくなります。
2. 即時決済によるキャッシュフロー改善
ブロックチェーンベースの送金であれば、国際送金でも数分〜数十分以内で着金が完了し、土日祝日や時差の影響も受けません。これにより、仕入先への支払い遅延リスクが低減し、キャッシュフロー管理も容易になります。
海外送金が数分〜数十分以内で着金することで、納品タイミングや支払条件との整合が取りやすくなり、資金繰りの精度向上や信用向上にもつながります。
3. 書類のトレーサビリティと透明性の向上
スマートコントラクトを活用すれば、ステーブルコインの送金と同時に、インボイスやB/L(船荷証券)などの電子書類との連動が可能になります。これにより、不正防止や書類ミスの削減が期待されます。
B/Lやインボイスなど貿易実務上不可欠な書類と自動連携することで、誤送・改ざん防止や手続き効率化に貢献します。
日本の貿易実務での導入における課題と整合性
一方、ステーブルコインを日本企業が貿易取引に導入するにあたっては、以下のような実務上の課題も無視できません。
| 課題 | 説明 | 解決の方向性 |
|---|---|---|
| 為替取引扱い | ステーブルコインはあくまで「電子決済手段」扱いであり、為替取引と見なすか否かが曖昧な場合あり | 外為法・税法との整合を専門家と確認 |
| 税務処理 | 会計上の評価損益・為替差損との関係が不明確なケースあり | 会計基準と照合した帳簿設計が必要 |
| 通関処理 | 電子決済と通関書類(インボイス、B/Lなど)との連動性が制度的に未整備 | デジタルインボイス制度や電子帳簿保存法と統合的に検討 |
| 契約実務 | 貿易契約(売買契約書)上に「JPYC払い」等を明記する場合、現地側の法制度に左右される可能性あり | 相手国の通貨法・電子決済法の調査が必要 |
特に注意すべきは、相手国の制度と整合が取れない場合、着金遅延や違法送金扱いとなるリスクがある点です。日本側が制度整備を済ませていても、受取国の法律が未整備であれば、取引が成立しないケースもあり得ます。
想定されるユースケース:貿易現場でのJPYC活用モデル
以下は、ステーブルコインを活用した貿易取引の簡易モデルです。
日本企業A社が、シンガポール企業B社から部品を輸入するケースを想定します。
| フロー | 従来のT/T送金 | ステーブルコイン(JPYC)活用 |
|---|---|---|
| 契約 | 円建て or ドル建て契約 | 円建て契約(JPYC払い) |
| 決済 | 銀行でT/T送金(3営業日) | ブロックチェーンで即時送金 |
| 手数料 | 為替+送金+中継銀行手数料 | 数十円以下、または無料 |
| 書類 | 銀行でL/C書類精査 | スマートコントラクトで自動照合 |
| リスク | 着金遅延、為替変動 | リアルタイムで価値確定 |
このように、従来のT/T送金に比べて、送金時間は数日→数分、コストは数千円→数十円以下へと劇的に圧縮されます。
また、リアルタイムでの決済と書類確認の同時進行が可能となるため、業務効率の向上や人的ミスの削減にも貢献します。
日本企業が導入する際のステップと留意点
準備段階
- 自社の業務フロー(契約、会計、税務)を棚卸し
- 相手国の法制度や受取環境をリサーチ
- 国内の会計士・弁護士との連携体制を整備
実装段階
- ウォレットの導入と管理責任の明確化
- 外部セキュリティ監査を受ける
- 社内研修とリスク対策マニュアルの整備
このように、ステーブルコインは貿易実務における新たな決済インフラとなり得る存在です。
ただし、現段階では制度・実務ともに発展途上であり、導入に際しては法的・技術的な慎重な検討が求められます。
ステーブルコインの商用活用が広がるには、制度の柔軟性、国際的な整合性、そして企業側の実務対応力の3点が重要です。
日本が「ステーブルコイン先進国」となるためには、規制と実務の両面でバランスの取れた対応が求められます。
AML/CFT(マネーロンダリング・テロ資金供与防止)対応や、サイバーリスクへの備えが今後の鍵となります。特に国際的な規制調和を欠いた状態での流通は、国境を越えた誤解やトラブルを生みかねません。
ステーブルコインを日本で導入する企業へのアドバイス
| 項目 | 推奨対応 | 理由 |
|---|---|---|
| 法務 | 弁護士・行政書士との連携 | 金融商品取引法との重複対応 |
| 税務 | 税理士による処理設計 | 仮想通貨課税との違いに留意 |
| 技術 | 安全性・改ざん防止機能 | サイバーリスク対策が不可欠 |
ステーブルコインの日本国内・海外での活用事例と展望

ステーブルコインは、いまや投資対象にとどまらず、決済・送金・資産管理・Web3経済のインフラとして世界各地で急速に実装が進む基盤技術です。
日本でも2025年に初の円建てステーブルコインが登場予定であり、いよいよ「構想から実装フェーズ」へと本格的に移行しつつあります。
ここでは、日本と海外の代表的なプロジェクトやユースケースを比較しながら、今後の国内展開と国際的ポジショニングを考察します。
日本における代表的ステーブルコイン活用事例(JPYCなど)
日本国内のステーブルコインは、制度整備を背景に民間・金融機関の2系統で実装が加速中です。ここでは、代表的なユースケースを見ていきましょう。
1. 民間発行型(資金移転業者による発行)
代表例が、株式会社JPYCによる円建てステーブルコイン「JPYC」です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行主体 | 資金移転業者(2025年登録承認) |
| 通貨ペッグ | 日本円(1 JPYC = 1円) |
| 担保 | 銀行預金および日本国債(JGB) |
| 利用先 | Web3決済、NFT購入、電子ギフト、地域振興など |
スマートフォンやWebアプリへのAPI接続を通じて、オンライン決済・NFT購入・自治体向けポイント制度などに柔軟に組み込めるのが特長です。
また、地方自治体や地域通貨との連携による地方創生型の実証実験も開始されており、「法定通貨 × 地域DX」を促進する役割も期待されています。
2. 金融機関連携型(信託型ステーブルコイン)
信託銀行が発行主体となる「金融機関主導型」のステーブルコインとして注目されるのが、三菱UFJ信託銀行の「Progmat Coin」です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行体 | 三菱UFJ信託銀行(金融機関) |
| 技術基盤 | 独自ブロックチェーン+RWA連携 |
| 特徴 | 証券決済や商取引の即時決済に活用可能 |
| 展望 | 株式・債券・STO市場との統合も視野に入れる |
Progmatは、ステーブルコインに限らず、リアルアセットのトークン化(RWA)や金融商品との連携を目的とした包括的なプラットフォームであり、日本の金融・証券インフラに密接に関わっています。
海外における先進活用事例と日本への示唆
一方で、海外ではすでに多くのステーブルコインが商用段階に達しており、特に米ドル建てのコイン(USDT、USDC)が市場をリードしています。以下に主要な海外事例を整理します。
| 地域 | ステーブルコイン | 主な用途と特徴 |
|---|---|---|
| 米国 | USDC(Circle社) USDT(Tether社) | 大規模決済、DeFi、取引所間送金、国際送金など。高い流通量と利便性。 |
| シンガポール | XSGD(StraitsX) | シンガポールドル連動。政府との連携が進んでおり、CBDC連動構想も存在。 |
| 韓国 | KRT(Klaytn)など | 韓国ウォン連動。スマートコントラクト決済で国内アプリと統合。 |
| 欧州 | EUROC(Circle) | ユーロ建てステーブルコイン。EUのMiCA規制対応を想定。 |
これらのプロジェクトは、単なる送金ツールにとどまらず、デジタル証券、DeFi、Web3ゲーム、クロスボーダー送金などに幅広く使われており、実需との結びつきが強いのが特徴です。
日本と海外の差分分析:なぜ日本は慎重なのか?
日本のステーブルコイン政策は、「慎重かつ制度整備重視」であることが世界的にも知られています。表面上は日本の制度設計が“慎重”に映るかもしれませんが、その裏には「安全性・透明性・安定性」を最優先とする制度思想が存在します。
以下はその違いを制度設計面から整理した比較表です。
| 比較項目 | 日本 | 海外(米国等) |
|---|---|---|
| 規制アプローチ | 先に法制度を整備し、厳格な監督体制下で発行を許可 | 実験的な民間発行を容認し、市場の動向に合わせて後追い規制を導入 |
| 担保・裏付け | 信託預金・JGBなど、堅牢な担保を義務付け | 資産担保型〜アルゴリズム型まで幅広く容認 |
| 中央銀行との関係 | CBDC(デジタル円)との競合・補完が慎重に議論されている | 一部の国では民間主導でステーブルコインが広く普及中 |
つまり、日本のステーブルコインは“実需ありき”ではなく、“制度と金融秩序を守るための準備ありき”で設計されており、長期的には他国より安定した制度的環境で成長することが期待されています。
今後の展望:日本の国際的ポジショニングと展開可能性
日本がステーブルコイン分野で国際競争力を高めるためのポイントは以下の通りです。
- アジア圏との連携強化
ASEANや韓国、インドなどの近隣諸国と通貨連動型ステーブルコインの相互運用性を高める - 貿易実務・SCMとの統合
スマートコントラクトや電子インボイスとの接続により、貿易実務に直接活用できるインフラを構築 - CBDCとの補完的設計
デジタル円(CBDC)との役割分担を明確化し、民間ステーブルコインが商取引の即時性を担う設計に - Web3・メタバースとの融合
国内外のWeb3企業との提携による新たなユースケースの開発(NFT、ゲーム内決済、DAO等)
まとめ
2025年秋、日本初の円建てステーブルコインJPYCの発行は、日本のデジタル金融市場における転換点となるでしょう。貿易決済、資金移動、Web3との連携など、その可能性は多方面にわたります。
一方で、法的整理、技術標準、税務対応など解決すべき課題も少なくありません。企業がステーブルコインの導入を検討する際には、事前に十分な制度理解と実務検討が求められます。
専門家に一度相談してみることをおすすめします。
法務・税務・ITの各側面からリスクを正しく評価し、安定的かつ持続可能な運用を目指しましょう。














