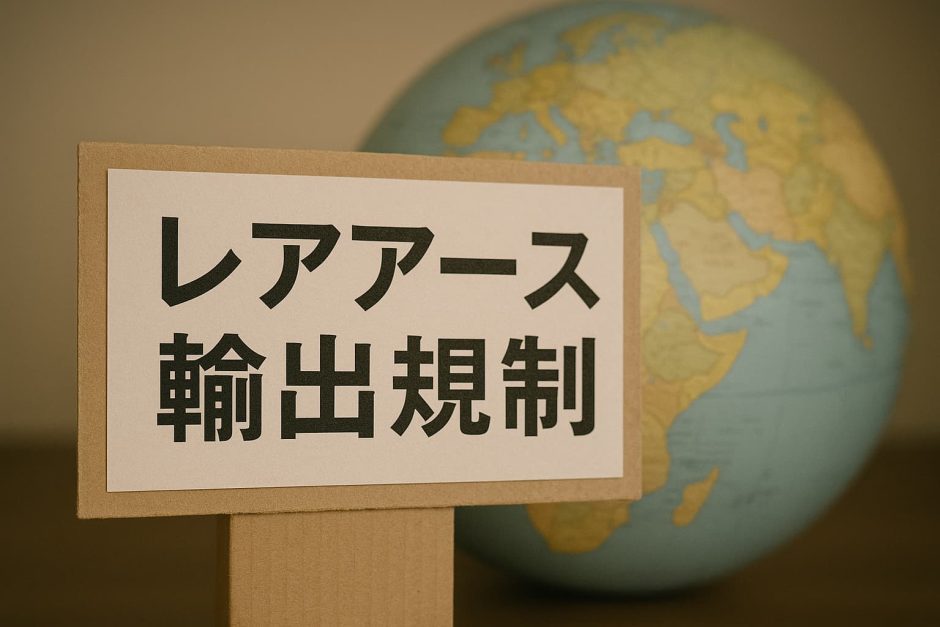レアアースは、スマートフォンやEV、再生可能エネルギーといった先端分野に不可欠な戦略資源です。2025年現在、米中対立の激化やサプライチェーンの再構築を背景に、各国で輸出規制の強化が進んでいます。
特に2025年現在、米中対立やサプライチェーン再構築の動きが、規制強化を加速させています。
本記事では、レアアースに関する輸出規制の最新動向を、国際通商ルールの理解と併せて制度比較から整理。
さらに中小企業の貿易実務を支援する「おまかせ貿易」サービスも取り上げ、現実の支援策を踏まえた視点で解説します。
レアアースと輸出規制――戦略物資としての国際的な位置づけ

現代のハイテク産業やグリーンエネルギー技術を支える素材の一つに、「レアアース(希土類)」があります。レアアースとは、周期表の中でもランタンからルテチウムまでの15元素に、スカンジウムとイットリウムを加えた17種類の元素の総称です。
名前に「レア」と付いているものの、実際には地殻中に広く存在しています。ただし、経済的に採掘・精製が可能な鉱床は限られており、技術的にも処理が非常に難しいため、供給が限られるのが実情です。
特に注目すべきは、その供給源の偏在性です。世界のレアアース精製能力の約9割が中国に集中しており、他国にとっては安定調達が極めて重要な課題となっています。このような背景から、レアアースは戦略物資として位置づけられ、各国が政策的な管理や備蓄、輸出規制の対象とする理由が存在しています。
戦略物資とは何か
国家の安全保障や経済運営に不可欠な「戦略物資」として、レアアースは各国の政策管理対象となっています。
戦略物資の特徴は、以下の3点に集約されます。
| 項目 | 内容 | レアアースとの関連 |
|---|---|---|
| 重要性 | 国家・産業基盤の維持に不可欠 | モーター、磁石、電池、 触媒などの材料に使用 |
| 脆弱性 | 供給停止で深刻な影響 | 主要生産国に依存、 中国が圧倒的なシェア |
| 代替困難性 | 短期的な代替や代用が難しい | 特定用途での 高性能を持つ元素群が多い |
特にレアアースは、単なる金属ではなく「高機能材料」としての役割を担っており、国家レベルでの保有や管理の対象となっています。
なぜレアアースが規制対象になるのか
戦略物資であるレアアースが各国の輸出規制の対象となるのには、いくつかの具体的な理由があります。
高い産業依存度
レアアースは、スマートフォン、電気自動車(EV)、風力発電機、航空機エンジン、ミサイル誘導装置など、先端技術に不可欠な部材に使用されています。ネオジムやジスプロシウムといった元素は、強力な永久磁石に使われ、軽量かつ高性能な製品づくりに貢献しています。
生産の集中と地政学的リスク
現在、世界のレアアースの採掘・精製のほとんどが中国で行われており、同国が政策的に輸出を制限することで、他国の産業に大きな影響を与えることができます。
2010年には、中国がレアアースの輸出枠を大幅に削減し、日本企業が深刻な供給リスクに直面しました(のちにWTOで提訴)。
こうした動きは、いわゆる「資源を使った経済的影響力(リソース・ディプロマシー)」としても位置づけられます。
国家安全保障との関係
軍事・航空宇宙分野で使用される製品にもレアアースは不可欠です。そのため、多くの国では、これらの素材が敵対国に渡ることを防ぐ目的で、輸出に制限をかける動きが強まっています。
特に近年の米中対立の激化や、経済安全保障政策の強化を受け、軍事転用可能な素材の管理はより厳格になっています。
レアアースの規制が与える影響
輸出規制は、単に国内外の取引量を制限するだけではなく、サプライチェーンの再構築や新たな技術革新を促す要因ともなっています。
たとえば、日本は2010年の中国による輸出制限を契機に、オーストラリアやベトナムなどとの資源提携を強化し、リサイクル技術や代替素材の研究を加速させました。こうした対応は、他国にも波及し、レアアースを「一国依存」から「多元供給」に切り替える世界的な流れにつながっています。
また、企業にとってもリスクマネジメントの一環として、調達戦略の見直しやBCP(事業継続計画)への反映が求められるようになっています。

中国のレアアース輸出規制――政策転換と国際への波紋

中国は、世界のレアアース供給の6割以上を占め、さらに精製・加工能力については9割近くを掌握している唯一無二の存在です。この圧倒的なシェアを背景に、同国が取る輸出規制政策は、国際市場に瞬時に波及し、各国の産業や調達戦略に大きな影響を及ぼしています。
特に注目すべきは、2010年と2023年以降の2度にわたる大きな政策転換です。これらの動きは、単なる資源管理ではなく、国際通商・外交の文脈とも密接に関係しており、戦略物資を巡る国際的な緊張の一因ともなっています。
2010年の輸出規制とWTO提訴の経緯
2010年、中国政府は「環境保護」や「資源保全」を理由に、レアアースの輸出量を前年に比べて40%以上削減し、さらに輸出業者に対して厳格な割当制度を適用しました。この措置により、供給が急激に減少し、国際価格は数倍に急騰。日本ではEV部品や磁石材料の調達に深刻な支障が出ました。
この政策に対し、日本・米国・EUは中国をWTOに提訴。2014年、WTOは中国の措置がGATT第11条に違反するとし、「国内供給と輸出に対する差別的管理は認められない」との判断を下しました。
これにより、中国は制度の見直しを余儀なくされました。
2023年以降の規制強化と国家安全の論理
その後、中国は輸出規制の「名目」を変更し、国家安全保障というより強固な論理を用いるようになります。2023年7月には、ガリウムやゲルマニウムといった半導体材料に対して輸出ライセンス制度を導入。
同年末には、一部のレアアースも国家安全リストに加えられ、戦略物資としての管理が強化されました。
また、中国工業情報化部(MIIT)は、「希土類資源の乱掘・過剰生産を防ぐ」ことを目的に、輸出ライセンスの発給にあたっては用途・取引先・最終利用国の確認を必須化。これにより、輸出の自由度は著しく低下し、事実上の数量統制が行われている状況です。
輸出規制が国際市場に与えた衝撃
中国によるレアアース輸出規制は、単なる供給不足以上の問題を引き起こしています。以下は、実際に確認された市場への影響の例です。
| 年度 | 規制対象物質 | 市場の反応 |
|---|---|---|
| 2010 | ネオジム、セリウムなど | 国際価格が3〜5倍に急騰 |
| 2023 | ガリウム、ゲルマニウム | 半導体業界で供給逼迫、代替品調達競争が激化 |
| 2024 | ジスプロシウム等一部希土類 | 日本・韓国の部品メーカーが納期調整に追われる |
2024年には、ジスプロシウムやテルビウムを含む重希土類の供給に関しても、中国のさらなる輸出管理強化が懸念されており、日本や韓国のメーカーが納期調整を迫られるケースも報告されています。
こうした供給混乱は、企業のコスト構造や製品計画にまで波及し、ひいては消費者価格への影響すら招く可能性があります。
中国の政策意図と国際的見解
中国政府は、表向きには「資源の保護」「環境への配慮」「違法採掘の抑制」などを理由に規制強化を正当化しています。一方、国際的には「経済的交渉カード」としてのレアアース活用を警戒する声が高まっています。
実際、アメリカ議会では2024年以降、中国による「戦略的な資源利用」が安全保障上の脅威として議論されており、EUでも「サプライチェーンの強靭化」と「中国依存からの脱却」が政策課題として明示されています。
WTOと輸出規制――国際通商ルールとの摩擦

中国のレアアース輸出規制は、単なる一国の資源政策ではなく、国際通商ルールとどこまで整合するのかという点で、WTO(世界貿易機関)における注目テーマの一つとなっています。
特に、資源ナショナリズムや経済安全保障の高まりを背景に、WTOルールと国家主権との境界線は、より複雑な問題へと発展しつつあります。
WTOにおける輸出規制の基本原則
WTOの基礎となるGATT(関税および貿易に関する一般協定)では、加盟国が恣意的に貿易を制限することを防ぐため、数量制限や差別的措置は禁止されています。
特に重要なのが以下の条文です。
| 条文番号 | 内容 | 輸出規制との関係性 |
|---|---|---|
| GATT第11条 | 輸出入に関する 数量制限の原則禁止 |
国家が一方的に輸出枠を 設けることを制限 |
| GATT第20条 | 公衆衛生、環境、 安全保障などに関する例外規定 |
正当な理由があれば 一部規制を容認 |
| GATT第21条 | 国家安全保障上の例外 | 軍事・安全保障リスクに関しては 例外が可能 |
このように、WTOでは原則として自由貿易を尊重しつつも、特定の理由があれば例外を認める柔軟性も備えています。
中国輸出規制とWTO紛争の経緯(2012–2014年)
レアアースをめぐる最も有名なWTO紛争は、2012年に日本・アメリカ・EUが中国を提訴した事例です。これは、中国が2010年に実施した輸出制限(割当制度と税制強化)が、WTO協定に違反するとして争われたものでした。
WTOは2014年に以下のような判断を示しました。
- 中国の輸出制限はGATT第11条に違反する
- 中国が主張したGATT第20条(環境保護)は正当とは認められない
- 国内供給には規制がなく、輸出のみ制限されている点が問題
この裁定により、中国は一時的に制度を緩和しましたが、その後、国家安全保障という新たな根拠を用いて別の形で管理を強化しています。
国家安全保障例外の濫用リスク
近年では、WTO加盟国が「国家安全保障」や「先端技術の軍事転用防止」を理由に輸出管理を正当化する動きが増えています。レアアースだけでなく、半導体やAI関連技術、バッテリー素材などにもこの論理が適用され始めています。
特に米中対立以降は、以下のようなケースが顕在化しています。
- アメリカ
半導体製造装置の対中輸出制限(2022年) - 中国
ガリウム・ゲルマニウム・希土類のライセンス制導入(2023–2024年) - EU
輸出許可制度の強化と域外持ち出し監視体制の導入
これらの動きは、WTOの基本原則に対して「例外規定」が実質的な常態化をもたらし、国際通商秩序の形骸化を招くのではないかと懸念されています。
WTOの限界と再構築の必要性
WTOはあくまで加盟国同士の合意による運営であるため、例外規定の乱用を法的に厳格に制限することは難しいという現実があります。また、米中の対立によって上級委員会が機能不全に陥っていることも、紛争処理メカニズムの信頼性を低下させています。
そのため、今後は次のようなアプローチが模索されると考えられます。
- 資源関連の貿易に特化した多国間協定の整備
- 透明性のある輸出規制通知制度の導入
- WTO内での「戦略物資」定義と取扱いルールの明確化
- 非関税障壁に関する共有データベースの構築
WTOが「自由貿易 vs 国家主権」という難題にどう対処するかは、レアアースのみならず、次世代エネルギーやAI技術に関する貿易にも大きな影響を与えるテーマとなります。
各国のレアアース輸出規制と対応策の比較

レアアースを戦略物資として位置づける動きは、世界各国で加速していますが、各国のアプローチは政治体制や産業構造の違いによって大きく異なります。資源を国家管理下に置く中国、民間主導と政策誘導を組み合わせるアメリカ、そしてリサイクルや技術革新に重点を置く日本・EU――それぞれの政策には独自の背景と戦略が反映されています。
制度と政策の比較
以下の表は、中国、アメリカ、日本・EUの主なレアアース関連政策とその特徴を比較したものです。
| 国・地域 | 輸出規制の特徴 | 主な制度・政策 |
|---|---|---|
| 中国 | 国家安全保障を名目に輸出管理を強化 | 国家安全リスト、輸出ライセンス制、環境規制 |
| アメリカ | 輸入依存からの脱却、国内生産の再建 | DPA(国防生産法)、鉱山再稼働、資源同盟 |
| 日本・EU | 代替技術とリサイクルで外部依存を緩和 | JOGMEC支援、CRM Act、重要原材料戦略 |
それぞれの国・地域の動向を、以下で詳しく見ていきます。
中国:資源管理を国家戦略に位置づける
中国は、国家資源としてのレアアースを一元管理する体制を強化しています。2023年には希土類資源を「国家安全リスト」に追加し、輸出にはライセンス取得を義務化。また、環境保護の名目で生産量にも上限が設けられています。
主な施策の特徴
- 精製・輸出能力を国営企業に集約
- 環境規制による中小精製業者の統合
- 「国内優先」の供給原則を採用
中国政府は、国内産業の高度化と戦略的交渉力の維持を目的として、レアアースの利用を国家主導で最適化する方針を取っています。
アメリカ:同盟国との連携と国内生産の再構築
アメリカは、長年にわたり中国への輸入依存が続いていたことから、安全保障上のリスクを明確に認識し、レアアースのサプライチェーン再構築を急ピッチで進めています。
主な施策の特徴
- DPA(国防生産法) に基づく戦略鉱物の政府支援
- カリフォルニア州マウンテンパス鉱山の再稼働(MP Materials)
- オーストラリア、カナダ、日本との鉱物協定強化
また、2023年には「戦略的鉱物パートナーシップ(MSP)」を立ち上げ、G7諸国と連携した資源共同開発も進行中です。これにより、同盟国を巻き込んだ多層的な供給網の確立を目指しています。
日本・EU:リスク分散と技術革新に注力
日本とEUは、既存の依存構造からの脱却に向けて、「外部依存を最小化する」戦略を取っています。特に、レアアースを代替する技術やリサイクルシステムの整備に注力している点が特徴です。
日本の対応
- JOGMEC(石油天然ガス・金属鉱物資源機構)による国家備蓄制度
- トヨタや日立によるネオジムフリーモーターの開発
- ベトナム・インド・オーストラリアとの資源連携強化
EUの対応
- 2023年施行の 「重要原材料法(CRM Act)」 により域内採掘・精製比率に目標値を設定
- サーキュラーエコノミー政策と連動し、廃製品からのレアアース回収技術を強化
- アフリカ諸国や南米との資源外交を展開
こうした取り組みは、長期的に見れば「非依存型の産業構造」への転換を促進するものと位置づけられています。
サプライチェーン再構築の動き
いずれの国・地域においても、特定国(主に中国)への過度な依存がリスクであることは共通の認識です。そこで、レアアースのサプライチェーンをより分散化・多層化する動きが進んでいます。
多国間連携による調達多元化の例
| 連携先国 | 主な内容 | 関与国 |
|---|---|---|
| オーストラリア | レアアース採掘と精製の共同投資 | 米国、日本、EU |
| カナダ | ESG対応型の鉱山開発と戦略備蓄の連携 | 米国、EU |
| ベトナム | 資源開発と加工技術の移転、長期供給契約 | 日本、韓国 |
さらに、各国が公的資金を投下することで、民間企業による「脱中国サプライチェーン」への参入も加速しており、特に欧州では地政学リスクへの対応が経済政策の柱となりつつあります。
まとめ
レアアースの輸出規制は、今や単なる素材の供給問題ではなく、国際政治や経済安全保障と密接に結びついた問題です。今後も規制は強化・複雑化が進む可能性があり、それに伴って調達や貿易のリスクは高まる一方です。
本記事で取り上げた制度・動向・事例を踏まえ、企業はより戦略的な視点で供給体制の見直しを進めていく必要があります。中小企業であっても、「おまかせ貿易」のような支援サービスを活用することで、海外市場へのチャレンジをより確実に実現することができます。
必要に応じて、専門家に一度相談してみることをおすすめします。制度や政策の変化が激しい今、正しい情報と支援のもとで判断を下すことが、持続的成長への第一歩です。