日本と米国は、世界有数の貿易相手国同士であり、2025年時点でもその関係は極めて緊密です。2024年の日本の輸出総額は過去最高の約107兆円に達し、そのうち約19.9%(21.3兆円)を米国向けが占めました。これにより、米国は中国を上回り、日本にとって最大の輸出市場となりました。
一方、米国にとっても日本は依然として重要な貿易相手国です。2023年の対日輸出は757億ドル、対日輸入は1,472億ドルに上り、米国側の対日貿易赤字は716億ドルと前年より拡大しています。
自動車や電子機器を中心に、日本からの輸出超過が続いている状況です。
近年は、地政学リスクやパンデミックの影響を受け、サプライチェーンの見直しが進んでいます。これに伴い、先端技術や経済安全保障の観点から、日米間の協力も一層深化しています。
以下では、日米貿易の中でも特に重要な位置を占める「自動車産業」「半導体」「農産物」の3分野に焦点を当て、最新の統計や政策動向、業界ニュースを整理してまいります。
目次 非表示
自動車産業の現状分析

日本の自動車産業は、長年にわたり日米貿易の中核を成しており、2020年代半ばにおいてもその構図には大きな変化が見られません。
日本から米国への自動車輸出は近年増加傾向にあり、2023年には乗用車および部品を合わせた対米輸出額が495億ドルに達しました。これは日本の対米輸出全体のおよそ3分の1を占める規模であり、前年比では13.4%の増加となっています。
背景には、世界的な半導体不足の緩和により輸出台数が回復したことが挙げられます。
以下に、2023年の日米間の自動車貿易に関する主要データをテーブル形式でまとめました:
| 項目 | 数値・内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 日本→米国:自動車関連輸出額(2023年) | 495億ドル | 乗用車および部品の合計 |
| 日本→米国:輸出額の対前年比増加率 | +13.4% | 世界的な半導体不足の緩和が背景 |
| 日本→米国:完成車輸出台数(2023年) | 約148.5万台 | 対米向けの完成車輸出台数 |
| 日本→米国:輸出台数の国内生産に占める割合 | 約16% | 日本国内生産台数(約900万台)に対する割合 |
| 米国→日本:自動車関連輸出額(2023年) | 17億ドル | 自動車および部品の合計 |
| 米国→日本:輸出額の対前年比増加率 | +21.9% | EV市場など新分野の影響と見られる |
実際に、2023年に日本から米国向けに輸出された完成車の台数は約148.5万台に上り、日本国内の年間生産台数(約900万台)の約16%を米国市場向けが占めた計算になります。
一方、米国から日本への自動車輸出規模は依然として小さいものの、2023年には自動車および部品で17億ドル(前年比21.9%増)と増加傾向が見られました。これは、米国メーカーによる日本市場開拓の動きや、電気自動車(EV)など新分野への進出が反映された可能性があります。

関税・貿易政策の影響
他の主要市場と異なり、日本は自動車(完成車)に対して輸入関税を課していませんが、米国は乗用車に2.5%、ピックアップトラックに25%の関税を維持しています。このため、日本の自動車メーカー各社は、米国市場向けの販売の多くを北米での現地生産によってまかなう戦略を取ってきました。
たとえば、トヨタ自動車は2024年に米国市場で約233万台を販売しましたが、そのうち約127万台を米国内で生産し、不足分の約53万台を日本から輸出する体制を敷いています。日産自動車も同様に、米国での販売台数約92万台のうち半数超を現地で生産し、約19万台を日本から北米向けに輸出しています。
このように、日本メーカーによる現地生産投資の拡大は、長年の貿易摩擦の緩和に大きく寄与してきました。なお、米国のトランプ前大統領は在任中、日本車に対して25%の追加関税を課す案を交渉カードとして取り上げた経緯があります。仮にこの関税が発動された場合、日本のGDPを0.2%押し下げるとの試算も報じられていました。
幸い、現時点では自動車への追加関税は回避されていますが、米国側には依然として対日貿易赤字や市場アクセスに対する不満が残されており、将来的な保護主義的な動きには引き続き注意が必要です。
以下にの項目と数値のみをまとめたテーブルを出しています。
| 項目 | 数値・内容 |
|---|---|
| 日本の自動車輸入関税 | 0% |
| 米国の自動車輸入関税(乗用車) | 2.5% |
| 米国の自動車輸入関税(ピックアップトラック) | 25% |
| トヨタ:2024年 米国販売台数 | 約233万台 |
| トヨタ:米国内生産台数 | 約127万台 |
| トヨタ:日本からの輸出台数 | 約53万台 |
| 日産:2024年 米国販売台数 | 約92万台 |
| 日産:日本からの輸出台数 | 約19万台 |
| 追加関税案の影響試算(日本GDP) | GDPを0.2%押し下げる可能性 |
| 現時点の追加関税の状況 | 回避されているが懸念は残る |
日本メーカーのEV投資と米国環境政策への対応
2020年代に入り、自動車業界はガソリン車から電気自動車(EV)への大転換期を迎えています。米国では、2022年に成立したインフレ抑制法(IRA)により、北米で組み立てられ、かつ一定の地域で調達された電池材料を用いたEVにのみ税額控除が適用される制度が導入されました。
この制度に対応すべく、日本の自動車メーカー各社は、米国でのEVおよび電池の生産体制に対して巨額の投資を進めています。
例えば、トヨタ自動車はノースカロライナ州に蓄電池工場を新設し、総額139億ドルを投じて2025年4月の稼働開始を目指しています。さらに、インディアナ州では14億ドルを投資し、2026年からはトヨタ初の米国製EVとなるSUVモデルの生産を予定しています。
ホンダはLGエナジーソリューションと提携し、オハイオ州にEV用電池工場を建設中です。日産もまた、米国工場におけるEVモデルの生産や電池調達体制の強化を進めています。
これらの取り組みは、米国の環境政策への対応に加え、現地生産比率を高めることで将来的な関税リスクを抑え、米国市場での競争力を維持・向上させる狙いがあります。
日米EV市場の構造と貿易関係の深化
一方、米国メーカーによる日本市場への本格的な参入は依然として規模が小さい状況にありますが、テスラをはじめとするEV専業メーカーが日本の輸入車市場で徐々に存在感を高めつつあります。充電インフラの整備状況やEVに対する消費者ニーズの変化によっては、今後市場動向に変化が生じる可能性もあります。
総じて、自動車分野における日米貿易は、日本から米国への自動車輸出と、日本企業による米国での現地生産投資という両面において関係が一層深まっています。両国の経済は相互に不可欠なパートナーとなっていますが、米国側には依然として貿易赤字の是正や市場アクセス改善に対する要求が残っています。
そのため、関税を含む政策動向を注視しつつ、日米間において協調と競争のバランスを的確に取ることが今後ますます重要になっていきます。
日米自動車貿易は、日本からの輸出と米国での現地生産投資の両面で拡大しています。今後はEVシフトや関税政策への対応が、競争力維持のカギとなります。
現在の半導体動向
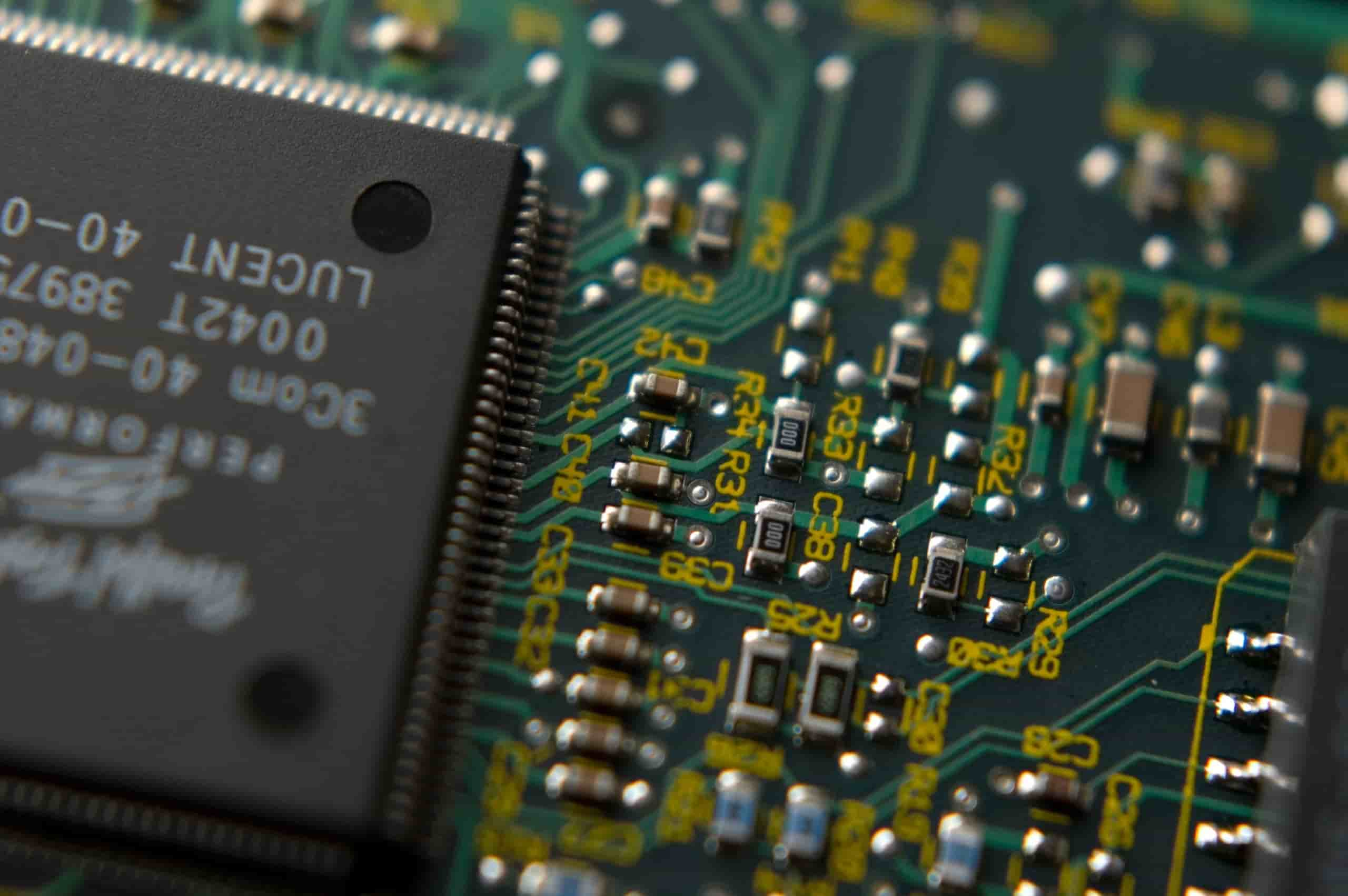
スマートフォンから自動車、AI、軍事技術に至るまで、あらゆる先端産業の中核を担う「半導体」。いまや21世紀の石油とも言われるこの戦略物資をめぐり、米中対立を背景とした地政学的な緊張が高まる中、日米両国は協力体制の強化を急いでいます。とりわけ米国が主導する対中輸出規制や国内製造支援策に対し、日本も歩調を合わせ、技術・投資・人材の面で密接な連携が進んでいます。
米中対立下の対応
21世紀の「石油」とも称される半導体は、経済安全保障の観点から日米の戦略的協力分野となっています。特に米国は、中国への先端技術流出を防ぐため、2022年以降、先端半導体や製造装置の対中輸出を禁止するなど、厳格な輸出規制を導入し、同盟国にも同調を求めてきました。
日本政府もこれに歩調を合わせ、2023年には外国為替及び外国貿易法の政省令を改正し、極端紫外線(EUV)露光装置を含む先端半導体製造装置23品目を輸出管理リストに追加する措置を講じています。この規制強化により、日本企業(東京エレクトロン、ニコンなど)の対中輸出は厳しく制限され、サプライチェーンの「脱中国」や「フレンドショアリング」が進んでいます。
一方、米国や台湾などの友好国向けには安定供給が求められ、サプライチェーンの再構築が進行中です。2023年の米国の対日輸入統計では、半導体製造装置を含む一般機械の輸入額が351億ドル(前年比-6.6%)と減少しており、これは対中輸出規制や半導体市況の変動が影響した可能性があります。
日米連携に半導体開発と投資拡大
他方、日米は半導体分野において前向きな協力関係を強化しています。日本の官民出資で設立された新興企業Rapidus(ラピダス)は米IBMと提携し、2ナノメートル世代の次世代半導体の研究開発・製造に取り組んでいます。
岸田首相も2024年初頭の訪米時に「Rapidusのような日米協力の機会が今後増えるだろう」と述べ、次世代半導体をめぐる連携の広がりに期待を示しました。
政府間でも「日米半導体協力対話」や経済版2+2協議を通じて、先端およびレガシー半導体のサプライチェーン強靱化、人材育成、技術開発などで協力が進んでいます。2024年4月の日米首脳共同声明では、半導体・AI・量子技術などの重要技術分野における連携強化が盛り込まれ、輸出管理の継続的な協力体制も確認されています。
加えて、Resonacを中心とする「US-Japan JOINT」プロジェクトに代表されるパッケージング技術の共同開発や、米マイクロン社による広島工場への大型投資(補助金1,300億円超)など、日米企業間の相互投資も加速しています。

補完関係の深化と中国対応のバランス
総じて、半導体分野では米国の対中規制を契機に、日米が連携してサプライチェーンの再編と強化を進めています。日本は製造装置や素材分野で強みを持ち、米国は設計や先端技術で優位性を有しており、両国間の補完関係は非常に成立しやすい構造です。
2025年時点では、両国政府の支援の下で次世代半導体の共同開発や生産拠点の分散が進みつつあり、今後数年で先端チップの試作・量産化、人材交流の拡大など、具体的な成果が期待されます。
一方で、中国市場への対応という難題も引き続き存在します。企業は収益性と安全保障の両立という難しい舵取りを求められ、政府は同盟国との連携を維持しながら、ルール形成や国際的枠組みづくりをリードしていくことが不可欠です。
日米農産物について

日本の食卓に欠かせないトウモロコシや牛肉、そして果物――その多くは実はアメリカから届いています。農産物分野は、工業製品とは異なる形で日米の経済関係を支える重要な領域です。
日本の食を支える米国産農産物
農産物貿易は、工業製品とは異なる意味で日米関係において重要な位置を占めています。日本は食料自給率が低く、多くの農産物を米国から輸入しており、米国にとっても日本は主要な農産物輸出先の一つです。実際、2024年の米国の対日農産物輸出額は約120億ドルに達し、日本は米国産農産物の輸出市場で第5位となりました。
品目別に見ると、最大の対日輸出品目は飼料用を中心とするトウモロコシで年間27.7億ドル(1,247万トン)、次いで牛肉・牛肉製品が18.7億ドル(約24万トン)、豚肉13.8億ドル、小麦5.8億ドル、大豆10億ドルと続いています。これら上位5品目で輸出全体の大部分を占めており、特にトウモロコシは日本の飼料用需要の大半を米国産が満たしています。
| 品目 | 輸入額(2024年) | 備考 |
|---|---|---|
| トウモロコシ | 27.7億ドル | 飼料用が中心、日本の主原料 |
| 牛肉・製品 | 18.7億ドル | オーストラリア産と並ぶ主供給源 |
| 豚肉 | 13.8億ドル | 加工品含む |
| 大豆 | 10億ドル | 飼料・油脂原料など |
| 小麦 | 5.8億ドル | 主にパン・麺類用 |
これら5品目で、米国からの農産物輸出の大部分を占めています。特にトウモロコシと牛肉は、日本の畜産・食品業界にとって重要な輸入品目です。
また、牛肉はオーストラリア産と並ぶ日本の主要な供給源となっており、2022年の一時的な増加の反動もあって、2023年は前年比13.5%減の31億ドルとなったものの、依然として高水準を維持しています。穀物も2023年には32億ドルで前年比24.4%減と落ち込みましたが、これは国際価格の変動や他国(ブラジルなど)からの調達拡大が影響したとみられます。

関税協定が後押しする米国産農産物の拡大
日本の農業保護政策は長年、日米貿易交渉の争点となってきました。WTO加盟後も、日本はコメに778%の関税を課すなど、国内農業を保護する姿勢を続けてきましたが、近年では経済連携協定を通じた段階的な市場開放が進んでいます。
2020年に発効した日米貿易協定では、TPP離脱により不利益を被った米国に対し、牛肉・豚肉・乳製品・小麦などの関税引き下げや低関税枠の設定が行われました。牛肉関税は発効時に38.5%から26.6%に引き下げられ、最終的には2033年に9%まで下がる予定です。
さらに、2023年には米国産およびCPTPP加盟国の牛肉に対してセーフガードが発動しにくい新ルールも導入され、輸入急増時の関税引き戻しリスクも軽減されています。その結果、米国産農産物の約90%は日本市場で無税または優遇関税の適用を受けており、チーズやワイン、果物など新たな品目でも存在感が高まりつつあります。
双方向に進む農産物貿易と日本の農業支援
ただし、日本の農業側にも一定の配慮がなされています。コメについては日米協定でも市場開放措置が取られておらず、引き続き国家貿易制度の下で最低輸入枠(ミニマムアクセス)内に限られた輸入となっています。小麦についても政府売り渡し制度により、一定のマークアップ(上乗せ)が維持されており、砂糖や乳製品などの高関税品目には関税割当(TRQ)制度が設けられています。
日本政府は国内農業の競争力強化にも取り組んでおり、和牛や果物などの高付加価値品の輸出促進に力を入れています。2024年には日本産農林水産物・食品の輸出額が初めて1.5兆円を超え、最大の輸出先は米国(2,429億円、前年比+17.8%)となりました。
このように農産物分野においては、米国から日本への輸入と日本から米国への輸出がともに拡大しており、日米の農業貿易は双方向での成長が進んでいることが注目されます。
今後の動向について

自動車:北米EV化で関税リスク
2025年に再登場したトランプ政権は、日本からの完成車に対して最大24%の「相互関税」を課す可能性を示唆し、既存の乗用車関税2.5%やピックアップ25%と重なると、実質40%を超える負担が生じます。
こうした圧力に対し、トヨタやホンダ、日産などの日本メーカーは、北米でのEVおよび電池生産投資を前倒しし、USMCA原産地規則を満たす現地生産比率の引き上げを急いでいます。
短期的には2026年に完成車輸出台数が15%程度減少する恐れがありますが、現地化が進めばIRAの税額控除を活用しつつ関税緩和を交渉する余地も残ります。部品サプライヤーや港湾物流まで含めたサプライチェーン全体で対応策を検討し、四半期ごとに計画を見直すことが重要です。
半導体:同盟国除外を勝ち取り競争
米国は安全保障を名目に半導体へセクション232調査を開始し、日本製ロジックICや製造装置に25%超の追加関税を課す案を検討しています。しかし、RapidusとIBMの2ナノ共同開発やマイクロンの広島投資など、日米間の補完関係は深まっており、議会や業界団体からは「同盟国除外」を求める声が強まっています。
除外が実現すれば、日本企業は後工程を米国内に配置しつつ国内の装置・素材生産を維持するハイブリッド型で競争力を保てます。一方、除外が得られない場合には、装置メーカーの現地組立やメキシコ移転が加速し、追加投資と在庫圧縮の両立が課題となります。
企業は補助金制度を活用しながらキャッシュフローを管理し、政策変更に即応できる体制を整える必要があります。
農産物:多角調達で価格高騰
相互関税の対象に牛肉やトウモロコシが含まれるかどうかは、日米双方の農業団体が強い関心を寄せる焦点です。米国農家への打撃を避けるため、最終的には日本が牛肉の低関税枠拡大やセーフガード緩和で譲歩し、農産物は関税回避に落ち着く可能性が五分と見込まれます。
しかし、交渉が長引けば飼料価格が高騰し、畜産コストの上昇が消費者物価に波及するリスクが高まります。商社や飼料メーカーはブラジルや豪州への発注シフト、長期ヘッジ契約の拡充など調達多角化を急いでおり、日本政府も経済安全保障の観点から米国産依存を低減しつつ、高付加価値和牛や果物の対米輸出拡大を図っています。
企業は価格変動リスクを定量的に評価し、サプライチェーンの柔軟性を高めることで、政策不確実性に備えることが求められます。
まとめ
自動車、半導体、農産物の各分野において、日米の貿易関係は2025年時点で一層緊密かつ多角的になっています。
自動車分野ではEVシフトを背景に相互投資が進み、半導体では対中戦略を共有するパートナーとして協力体制が強化されています。農産物では安定供給と互恵的な取引を目指しながら、市場開放と保護のバランスを図ろうとしています。
また、日米両政府は経済版2+2や首脳会談を通じて、サプライチェーンの強化や先端技術開発、気候変動対策、デジタル分野での連携を進めています。一方で、貿易不均衡や通商政策の違いが再び表面化するリスクも残されています。特にアメリカでは政権交代によって通商政策の方向性が大きく変わる可能性があり、日本側にも経済安全保障推進法の運用や対外政策の調整が求められています。
ただし、戦後から続く経済的な相互依存の歴史を考えれば、両国が協調することは国益にかなうものと言えるでしょう。今後も日米が建設的な対話を重ね、公平で自由な貿易関係を発展させていくことが期待されます。貿易戦略を見直す際には、専門家に相談することをおすすめします。












