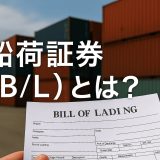2025年4月から10月にかけて開催された大阪・関西万博は、世界中の注目を集めた国際的なイベントでした。華やかな会期を終えた今、中小企業がこの経験をどのようにビジネスに活かすかが問われています。
特に貿易や海外展開に関心のある企業にとっては、万博終了後の動き方が、将来の成果を左右するポイントとなります。
この記事ではまず万博の概要と実績を整理した上で、貿易を考える中小企業に向けて、国際展開へのヒントや具体的なアクションを提案します。
万博終了後から振り返る|大阪・関西万博の全体像と実績

万博の意義や成果を知ることは、その後の展開を読み解く第一歩となります。ここでは、出展国数や来場者数、経済波及効果に加え、出展傾向や注目テーマなど、万博の全体像を多角的に整理します。
出展構成とパビリオンの概要
大阪・関西万博には150を超える国・地域が公式に参加し、国際機関、企業、自治体も含めて多様な主体が出展しました。パビリオンは「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマに沿って構成され、持続可能性、デジタル、医療・健康、食・水、エネルギーといった分野に重点が置かれました。
シグネチャーパビリオンでは、日本が提唱する未来社会像が具現化され、民間パビリオンでは、製造業、建設、IT、再生可能エネルギー、医療・バイオなどの先端技術が紹介されました。特に中小企業の技術展示が目を引き、海外からの来場者が注目するブースも見られました。
また、各国のパビリオンでは、自国の文化や技術をPRするだけでなく、貿易・投資を促進するための企業向けイベントや商談会も随時開催され、ビジネス色の強い交流も数多く実現しました。
来場者数と来場者の傾向
最終的に一般来場者は約2,500万人を記録し、関係者含む総来場者は2900万人を超えたと発表されました。国内来場者が全体の大部分を占めたものの、東アジア・東南アジア・中東などからの海外来場者も数多く訪れ、BtoBマッチングイベントや展示企業への視察が積極的に行われました。
ビジネス来場者の多くは、自国のパートナー企業を探すために訪れ、特に製造業・医療機器・環境分野のパビリオンに対する関心が高い傾向がありました。一方、週末や大型連休には一般の観光客や学生の姿も多く、社会教育の一環としての役割も果たしていたことがうかがえます。
来場者の関心は「体験型コンテンツ」に集中し、技術の実演やデジタル演出を駆使したパビリオンが長い待機列を生むなど、展示手法の進化も明確に表れていました。
経済波及効果と地域への貢献
万博がもたらした経済効果は、直接・間接を含めた多段階にわたります。短期的には、会場建設や関連インフラ整備による建設需要が生まれ、大阪・関西圏の労働市場に雇用と資金循環をもたらしました。
交通網の整備、宿泊施設の稼働率向上、小売・飲食分野の売上増も一時的ながら顕著です。
中期的には、展示を通じて新たな取引先やパートナーを獲得した企業が、商談から契約へと進展することが期待されます。特に国際展示会形式のイベントに慣れていない中小企業にとっては、海外との初接点を築く「導入機会」としての意味が大きかったといえます。
さらに長期的には、会場跡地を活用したイノベーション拠点や国際展示施設への転換が進められており、これが地域の新たな産業集積やスタートアップ育成につながる基盤として注目されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出展国数 | 約150カ国・地域 |
| 参加主体 | 各国政府、自治体、企業、国際機関など |
| 来場者数 | 約2,900万人 |
| 主な来場者層 | 一般市民、海外ビジネス関係者、教育機関等 |
| 注目展示テーマ | 再生可能エネルギー、医療、スマートシティ、食と水 |
| 経済波及効果 | 約2兆円(建設、観光、雇用など含む) |
万博の背景や開催意義をより深く理解しておくことで、終了後のビジネスチャンスの意味がより明確になります。
大阪関西万博の目的と全体像 については、以下の記事をご覧ください。
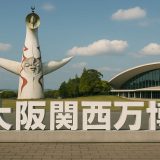
万博終了から見える中小企業の国際展開チャンス

万博は終わっても、国際的な交流の芽は確実に残っています。今回は、その中でも中小企業が“すぐに動ける”チャンスに焦点を当てます。
万博という国際的舞台は、普段は接点が乏しい海外企業やバイヤーと中小企業が顔を合わせる機会を創出しました。ここでは、公開されている支援制度や、実際に国際展開につながった実例をもとに、その可能性を具体的に探っていきます。
海外バイヤーとの商談機会をどう活かす? — “もずやんモール”からの接点
万博期間中、大阪府が提供した「万博商談もずやんモール」は、来阪する海外バイヤーが府内企業を検索し、商談の機会を得られるオンラインプラットフォームでした。
たとえば、金属加工部品を製造するある府内企業は、出展なしでもモールへの登録を通じて欧州のバイヤーから問い合わせを受け、後日オンライン商談を実現。最終的に試作品の輸出が決まったという事例も報告されています。
このように、公的な仕組みを活用すれば、ブースを持たずとも海外との接点を得ることが可能です。とくにIoT、医療、環境技術などに強みを持つ企業は、国際的な注目を集める分野として優位に立てる可能性があります。
展示支援制度の活用と中小企業の展示工夫とは?
中小企業庁や中小機構が実施した展示支援制度では、パビリオン出展や展示方法のアドバイス、広報ツールの提供といったサポートが提供されました。
中でも「大阪街中ものづくりパビリオン」は、地域の町工場が技術力を発信するための企画展示で、多くの事業者が参加。ある工場では、3Dモデルと映像を使って製造工程を紹介することで、海外の来場者からも高い評価を受け、展示会後にメールでの問い合わせが寄せられたといいます。
こうした経験は、企業の展示ノウハウの蓄積にもなり、今後の展示会・商談会参加への自信や実行力につながる点も重要です。
展示実績がもたらす信用と今後の波及効果
万博のような公的な国際イベントへの参加は、企業の対外的な信用を高める材料となります。たとえば「大阪代表商品プロジェクト」では、府内の優れた製品・技術を認証し、出展企業の信頼性を高める仕組みが導入されました。
展示実績のある「TSTジャパン株式会社」は、簡易IoT端末を活用したソリューションを提案し、「社会実装事例」として展示。こうした実績は、展示後の商談や提携交渉の際に「公的な場での実績」という説得力のある武器として機能します。
一度の出展が、信用の積み上げや情報発信の材料になり、それが新たなビジネスの起点となる。そんな好循環が、万博の場をきっかけに生まれています。
万博をきっかけに海外市場へ展開する際、どの産業が今注目されているかを知ることが重要です。日本の輸出品については、以下の記事をご覧ください。

大阪・関西万博は、展示や交流を通じて中小企業に新たな国際的接点をもたらしました。得られたつながりや経験を次の取引や販路拡大にどう生かすかが、今後の成長を左右する重要な鍵となります。
万博終了が示した輸出入ビジネスの新たな潮流とは?

万博で発信された技術・テーマ・企業連携の動きは、輸出入ビジネスにおける新潮流を示す指針ともなり得ます。この章では、実際の展示テーマや連携イベントから得られる示唆をもとに、輸出・輸入双方の可能性を見ていきます。
注目された技術・産業分野
エネルギー、スマート技術、再生可能資源といったテーマが、各パビリオンで強く打ち出されました。例えば、オランダパビリオンはクリーンエネルギーや再生可能エネルギー技術に重点を置いた展示を行っており、持続可能なエネルギーへの関心を可視化していました。
また、バス乗降ターミナルの屋根に、ペロブスカイト型太陽電池を薄膜形状で設置する技術も披露されており、このような先端素材技術の展示は、中小企業が技術輸出を狙う分野として関心を集めています。
こういった分野は、多くの国がエネルギー転換や脱炭素を政策目標とする中で、輸出のニーズが見込まれる領域と重なります。
輸入ビジネスの視点とニーズ
万博では、多様な国・地域の文化・産品が紹介されているため、従来注目されにくかった地域の特産品や伝統工芸品に対する関心も浮き彫りになりました。例えば、ウズベキスタンの「Garden of Knowledge(知識の庭)」パビリオンでは、持続可能性とデジタル技術融合を掲げつつ、伝統的な建築技術・文化資産を展示しており、今後の輸入品アイテムとしての可能性を示唆しています。
また、展示会周辺で行われる「テーマウィーク」などのプログラムでも、エネルギー・環境の議論が積極的に展開されており、輸入においてもエコ素材、サステナブル商品、リサイクル技術といった環境価値を備えた商品が注目される傾向があります。
たとえば、「SMART ENERGY WEEK」が再生可能エネルギー・脱炭素をテーマに議論を行う期間として設けられていることが公表されています。
こうした傾向を捉えることで、海外からの素材・部材の輸入戦略を練るヒントを得ることができます。
スタートアップと国際協業の可能性
万博と連携して実施されるスタートアップ向けイベントの存在も、国際協業の流れを示す重要な手がかりです。たとえば、「Global Startup EXPO 2025」は、Expo会場と連動して世界中のディープテックスタートアップ、投資家、大学、研究機関を結びつける国際カンファレンスとして計画されています。
このような場で、技術提供やプロトタイプ展示、共同開発提案などを通じて、スタートアップ企業が海外との協業を模索する動きが現実に起こりえます。
また、大阪を拠点とする “Tech Osaka Summit 2025” は、医療、グリーンテクノロジー、デジタル技術を中心に、スタートアップと企業・投資家のマッチング機会を提供しています。
これらの取り組みは、技術を持つ中小企業が輸出や共同開発によって国際競争力を持つ可能性を示すものと捉えられます。
万博終了後の今だからこそ|販路拡大に活かすネットワークとレガシー

万博終了後も、展示や制度を通じて構築されたネットワークや施設、支援体制をうまく生かすことで、企業の販路拡大に結びつける戦略が可能です。ここでは、支援機関・跡地利活用・フォローアップ活動という3つの視点から整理します。
1.支援機関との連携と活用
万博開催を前提に、各支援機関が海外ビジネス支援体制を強化しており、これを利用する余地は大きいです。
たとえば、JETROは「大阪・関西万博を契機とした海外ビジネス支援」プロジェクトを公表しており、大阪本部は「大阪海外ビジネスワンストップ窓口」を運営するなど、在阪企業と海外関係者との商談支援や相談対応を図る体制を整えています。
また、JETROと大阪商工会議所は、万博を契機に中小企業の海外ビジネス支援の協力を強めるという連携を報じています。
これらの支援機関は、展示未参加の企業にも門戸を開いていることが多いため、まずは相談窓口やセミナー・マッチング支援サービスをチェックすることが有効です。
2.会場跡地の再活用と将来展望
万博会場跡地(夢洲エリアなど)は、将来的に再開発され、国際展示施設、研究開発拠点、ホテル・商業施設など多様な活用が検討されています。報道では、跡地の一部をレースサーキットやリゾート施設、ホテル複合型施設などとする案も選定候補となっていることが伝えられています。
また、大阪市も「大阪イノベーションハブ」を中心とし、万博後を見据えたスタートアップ支援体制や企業立地施策を強化する方針を掲げています。これにより、跡地を活用した企業交流や展示機会を地元企業が取り込む可能性が高まります。
こうした施設や拠点の構想を把握しておくことは、将来的な展示機会や海外との接点を継続するための戦略立案に役立ちます。
3.フォローアップイベントの動き
バイラルな効果を維持するため、万博終了後のフォローアップイベントや商談プラットフォームの継続が重要です。出展企業や自治体は、報告会、分野別展示会、オンライン商談会といった継続的な活動を計画・実行しています。
また、中小企業庁・中小機構は、万博期間中に「未来航路」という体験型展示を行い、国内中小企業の魅力発信を支援しました。展示後も、こうしたプログラムやその延長としての発信活動が継続される動きが想定されます。
さらに、大阪府の将来構想資料には、万博後に府内中小企業と原材料メーカーなどとのマッチング支援、海外ビジネス展開を支える支援デスク整備などの施策が記載されています。これを活用することで、地域を超えた販路展開を後押しできます。
万博終了後の今こそ始めたい|具体的アクションと実行ステップ

万博をきっかけに海外との接点を得た企業や、万博を通じて海外市場に興味を持ち始めた企業にとって、次に何をすべきかを明確にすることが大切です。ここでは、貿易の実務に直結するステップを、段階的に具体的なアクションとして整理します。
ステップ1:情報収集と整理
まずは、自社にとって関係性のある国・業界・企業について情報を集め、万博で得られた資産や資料を再確認しましょう。ここでは、展示された企業の情報、過去に名刺交換や問い合わせがあった来訪者など、すでに接点がある相手を起点とするのが効果的です。
また、自治体や商工団体の発行する「万博関連展示企業一覧」や「業種別海外展開レポート」も活用できます。すでに万博を活用した販路開拓に成功した企業の事例集なども入手可能です。
確認すべき具体的情報の例
- 万博で関心を持たれた製品や技術は何だったか
- 自社製品が当てはまるカテゴリやターゲット国
- 展示会来場者の名刺や記録(担当者・所属・関心分野)
- 万博関連の商談会やセミナーの開催記録(地元商工会議所などで取得可能)
既存資料の活用例
- 出展パビリオンの公式記録
- 名刺スキャン履歴(Sansanなど)
- 担当営業による来場対応記録
ステップ2:相談機関へのアクセス
次に、支援制度の活用に向けて、JETROや商工会議所、自治体などの相談窓口にアクセスします。支援制度は時期や内容が頻繁に変わるため、必ず最新情報を確認し、自社に合うものを見極めることが重要です。
多くの機関では、初回の相談に限り無料対応しているほか、必要に応じて専門家とのマッチングサービスも用意されています。営業担当・開発担当が同行する形で相談することで、現場に即した支援を受けやすくなります。
| 機関 | 主な支援内容 |
|---|---|
| JETRO | 海外展示会・商談会支援、現地市場調査、翻訳・通訳対応 |
| 商工会議所 | 無料貿易相談、輸出入実務セミナー、商談会参加案内 |
| 自治体 | 地場産品の海外展開支援、ブランディング支援、補助金情報 |
| 中小機構 | 越境EC支援、デジタルマーケティング補助、販促支援 |
※支援を受けるには申請手続きが必要な場合があるため、早めの確認をおすすめします。
ステップ3:小さな実行からのスタート
最初から大きな取引や海外進出を狙う必要はありません。まずは「小さく始めて、経験を積む」ことが重要です。現在は越境EC(Amazon、Shopee、楽天グローバルなど)を活用することで、小ロットの輸出を手軽に始められます。
また、JETROや各国商工会のオンライン商談会に参加し、テスト的に製品紹介を行うのも有効です。実際に参加した企業の中には、韓国・台湾の中小商社とのオンライン面談を通じて、現地市場の評価を得たうえで試験販売に進んだ例もあります。
具体的な「小さな実行」例:
- 越境ECに1製品を登録し、反応を見る
- 翻訳済みの製品紹介PDFを用意し、配信先をリストアップ
- 海外バイヤーとのZoom面談を1件でも設定する
- 小規模な現地展示会に視察参加し、競合・価格帯を観察する
こうした「動き出し」によって、初期段階で見えてくる課題や改善点が、次の行動のヒントとなります。
まとめ
大阪・関西万博は、多くの国や地域との接点を生み、中小企業が国際的な舞台に立つきっかけを与えてくれました。特に貿易に関心を持つ企業にとっては、商談や展示、情報発信のあり方など、多くの学びを得ることができた場です。
重要なのは、この万博を「一度きりの機会」として終わらせず、得られた接点や経験をいかに今後の事業に活かすかです。支援機関や自治体の制度を活用しながら、小さな一歩を積み重ねていくことで、持続的な国際展開の道が開けていきます。
まだ何から始めればいいか迷っている方は、まずは貿易や海外ビジネスに詳しい専門家に一度相談してみることをおすすめします。自社に最適な選択肢を見つけることで、次の一歩がより確かなものになるはずです。