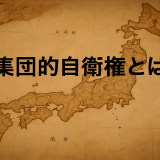2025年、南アフリカがアフリカ大陸で初めてG20の議長国を務めるという歴史的な転換点を迎えました。人口動態や開発需要の急増に直面するアフリカが、国際経済の意思決定の場でどのような役割を果たすのか。南アフリカは「連帯」「平等」「持続可能な開発」という理念を掲げ、グローバル・サウスの代表として新たな国際的枠組みの構築を目指しています。
今回のG20では、デジタル公共インフラやAIの公平性といった先進的テーマが議論される一方で、アメリカと中国の首脳が欠席するなど、地政学的な緊張も色濃く反映されています。
本記事では、G20と南アフリカをめぐる戦略、外交、技術政策に焦点を当て、国際秩序と協調の行方を読み解きます。
G20と南アフリカが担うアフリカ代表としての責任と意義

アフリカで初めてG20の議長国を務めることになった南アフリカには、象徴的な意味だけでなく、具体的な政策形成の責任が課されています。本セクションでは、南アフリカの国際的立場、議長国としての政策軸、そしてBRICSやアフリカ連合(AU)との連携を通じた外交戦略を整理し、2025年サイクルにおける意義を明らかにします。
アフリカとG20の関係は、2025年の南アフリカ議長国就任によって新たな局面を迎えています。この歴史的な位置づけや議論されたテーマ、各国の反応については、以下の記事で詳しく解説しています。

アフリカ初のG20議長国が意味するもの
南アフリカが2025年のG20議長国を務める意義は、国際経済秩序における構造的な転換を象徴するものです。これは一国の政治的栄誉にとどまらず、アフリカ大陸全体が世界経済の制度的な枠組みにおいて、初めて明確な発言権を持つ段階へと移行したことを意味します。
アフリカ連合(AU)がG20に正式加盟した直後に南アフリカが議長国となった背景には、アフリカの人口動態的優位性、経済成長の可能性、そしてグローバル・サウスの政治的台頭があります。これまでのG20において、アフリカはしばしば「開発の対象」として議論の俎上に載せられてきましたが、今回は議論を主導する側に立つという構図の転換が見られます。
また、南アフリカはG20におけるアフリカ唯一の恒常的メンバーであり、2010年の初参加以来、その外交的立ち位置を一貫して強化してきました。今回の議長国就任は、その積み重ねの延長線上にある成果でもあります。
南アフリカが掲げる議長国テーマと政策軸
南アフリカは、「連帯、平等、持続可能な開発」というテーマのもと、G20のアジェンダをこれまでの金融安定や貿易円滑化から、社会的包摂や技術的不平等といった開発的課題にシフトさせようとしています。とりわけ、デジタル公共インフラ(DPI)と人工知能(AI)の公平性は、議長国が最も重視する中核的テーマと位置づけられています。
DPIでは、技術導入による短期的なコスト削減だけでなく、汚職防止、税収拡大、社会サービスの普及といった広範な社会的効果が重視されています。これは、従来の費用便益分析(CBA)による評価枠組みから脱却し、より長期的・構造的な視点を国際議論に持ち込む試みでもあります。
また、AIについては「AI in Africa」イニシアチブを通じて、先進国中心で構築されてきたAIガバナンスの枠組みに対し、アフリカの視点を導入することが目指されています。南アフリカは、AIの倫理性、公平なデータアクセス、地域文化への適合性といった要素を国際基準として定着させるための議論をリードしようとしています。
BRICSとAUを結ぶ外交ハブとしての南アフリカ
南アフリカは、BRICSとアフリカ連合という二つの多国間枠組みにおいて戦略的なハブの役割を果たしています。この地政学的ポジションを活かし、2025年G20サイクルでは「南南協力」の要としての動きが顕著です。
BRICSの中で唯一のアフリカ国家である南アフリカは、開発金融、インフラ投資、技術移転などの分野で共通課題を持つ各国との政策協調を強化し、それをG20のアジェンダに反映させています。さらに、AUとの連携においては、アフリカ大陸全体の立場を代表する形で、統一的な政策提言をG20に持ち込む体制を構築しています。
このように、南アフリカは単なる地域代表ではなく、グローバル・サウスの集合的利益を世界経済の意思決定に統合する「交渉の架け橋」として機能しつつあります。議長国としてのこの戦略的役割は、今後のG20の性格そのものに変化をもたらす可能性を秘めています。
G20と南アフリカに影を落とす米中不在と国際秩序の再編

2025年のG20サミットには、アメリカと中国という世界の二大経済大国の首脳が出席を見送りました。これは、サミットの機能や意義に対して大きな疑問符を投げかけるとともに、議長国である南アフリカの外交的役割と調整力が試される事態でもあります。
本セクションでは、こうした不在の意味、南アフリカの対応、そして日本を含む各国の動きから読み取れる国際秩序の変化を考察します。
2025年G20サミットにおける主要国の出席状況
| 国名 | 首脳出席の有無 | コメント |
|---|---|---|
| アメリカ | 欠席(バンス副大統領も出席取りやめ) | 南アへの政治的反発を背景に不参加を決定 |
| 中国 | 習近平主席は欠席(李強首相が代理出席) | 米国との調整と南アへの距離感を調整 |
| 日本 | 高市早苗首相が出席 | 初の現地訪問で多国間外交を強化 |
| 南アフリカ | ラマポーザ大統領が主催 | 批判に対し冷静に対応し、議論継続を主張 |
米中首脳の欠席が映す地政学的現実
2025年11月、ヨハネスブルクで開催されるG20首脳会議には、アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席がいずれも出席しない見通しとなりました。とくにアメリカ側は、当初代理出席を予定していたバンス副大統領までもが参加を取りやめたことで、事実上の「全面的な欠席」となっています。
この背景には、トランプ政権による南アフリカへの強硬な政治姿勢があります。同政権は、南ア政府が「白人を迫害している」と繰り返し批判し、国際会議の場から距離を取る姿勢を明確にしています。2025年11月5日に行われた演説では、トランプ大統領が「南アはG20のようなグループに属すべきではない」とまで発言し、対立の構図が浮き彫りとなりました。
一方の中国も、表面的には穏健な対応を維持しつつも、首脳不参加という形で慎重な距離を取っています。李強首相の代理出席という判断は、米中対立を意識した外交的均衡を保ちつつ、南アとの関係悪化を避ける意図が見て取れます。
このような二大国の不在は、G20が持つ調整機能と国際的正統性に影を落とすものであり、南アフリカがいかにリーダーシップを発揮するかが重要な焦点となりました。
南アフリカの反応と首脳外交の重層化
こうした大国の欠席に対し、南アフリカのラマポーザ大統領は冷静かつ明快なメッセージで対応しました。「ボイコット政治は効果がない」「不在は彼ら自身の損失だ」と述べ、首脳会議の意義や方向性は変わらないという姿勢を強調しました。
実際、南アフリカはこのサミットに向け、欧州やアジア諸国との二国間外交を精力的に展開しています。大国が欠席することでむしろ南アの調整力が際立ち、グローバル・サウスと先進国の間で建設的な議論の場を維持するための戦略が問われる局面となっています。
また、議長国としての南アフリカの対応は、G20という枠組みが単なる大国主導ではなく、より多様な声を受け入れる場であることを国際社会に示す機会ともなりました。首脳会議の焦点を、AIやDPIといった未来志向の課題に据え直すことで、外交的な空白を議題の深化によって埋めるという選択がなされています。
日本と南アフリカの接近と新たな外交軸の形成
アメリカと中国の欠席が注目される一方で、日本は今回のG20サミットに高市早苗首相が出席し、現地での多国間外交を展開する方針を明らかにしています。これは日本の首相として初の南アフリカ訪問であり、アフリカとの政治的距離を縮める動きとして大きな意味を持ちます。
特に、日本はアジアの民主主義国家として、南アフリカと共通の価値観を持つ数少ない先進国の一つと位置づけられ、気候変動、債務問題、デジタル技術などの分野で協力を進めることが期待されています。
高市首相はサミット期間中、欧州各国の首脳との二国間会談を積極的に調整する予定であり、米中が外交的空白を生んでいるこの時期において、G7の一角として南アとの関係強化を図る構えです。
こうした日本の動きは、アフリカとの経済協力の深化だけでなく、国際会議における実務的外交の再評価にもつながります。米中不在の中で、多国間枠組みにおける中堅国の役割がより重要になるという、新たな国際秩序の兆しとも言えるでしょう。
G20と南アフリカにおけるデジタル公共インフラの新潮流

G20の2025年サイクルでは、デジタル公共インフラ(DPI)が中心議題の一つとして据えられています。南アフリカは、DPIを単なる技術導入の手段ではなく、社会包摂や経済近代化を実現するための国家戦略として捉えており、これまでの費用対効果中心の評価手法を超える新たな視点をG20に持ち込もうとしています。
このセクションでは、DPIをめぐる国際的な議論の変化、南アフリカが提示する新しい価値評価枠組み、そして国際開発金融機関(MDBs)への影響に焦点を当てます。
従来型と南ア型のDPI評価アプローチの比較
| 評価項目 | 従来のアプローチ(CBA中心) | 南アフリカの提案 |
|---|---|---|
| 分析軸 | 短期的な費用対効果 | 長期的・社会的リターン |
| 評価対象 | 財務指標・直接的な効率 | 包摂性、透明性、アクセス性 |
| 目的 | 技術導入の効率性判断 | 社会資本の強化と構造改革 |
この表は、南アフリカが従来のDPI評価手法に対してどのような見直しを提案しているかを簡潔に示したものです。
従来のCBA(費用便益分析)は、主に短期的な収益性や効率に焦点を当てていましたが、南アフリカはこれを超え、DPIの社会的・構造的影響を包括的に評価すべきだと主張しています。このアプローチの転換は、単に開発の指標を変えるだけでなく、政策判断や資金配分の根拠にまで深く関わる問題であり、国際的なインフラ整備の考え方に大きな再編を促す可能性があります。
DPIを通じた開発戦略の再定義
デジタル公共インフラ(DPI)は、これまで発展途上国においてもIT導入の一環として扱われてきました。しかし、南アフリカがG20で主導する今回の議論では、DPIが単なる技術インフラではなく、社会構造を根底から再設計する「公共財」として位置づけられています。
具体的には、デジタルID、政府系決済システム、電子税務、公共医療情報の統合といった多様な機能が一体となり、行政の透明性を高めると同時に、金融包摂や貧困対策にも直接寄与するというビジョンが打ち出されています。こうした枠組みのもと、南アフリカはDPIを国家発展の「基盤インフラ」と定義し、技術ではなく制度の中核として扱っています。
この発想は、従来の「技術的に優れているか否か」ではなく、「社会的に何を達成できるか」という評価軸への転換を意味しています。そしてこの転換こそが、南アフリカの議長国としてのアジェンダ形成能力を象徴するものとなっています。
費用便益分析から社会的価値評価への転換
南アフリカが国際社会に提起しているのは、DPIの評価方法そのものの見直しです。従来の国際援助や開発投資では、CBA(Cost-Benefit Analysis=費用便益分析)に基づいて、短期的な投資効果や直接的な効率改善に焦点が当てられてきました。
しかし、南アフリカが提示するのは、「目に見えにくいが本質的に重要な便益」を評価に組み込む枠組みです。たとえば、行政サービスのデジタル化によって得られる汚職削減、税収の安定化、教育・医療アクセスの改善、そしてそれらがもたらす社会的信頼の向上といった非財務的リターンを定量・定性の両面で測定することが求められます。
この新しい評価枠組みは、単なる理論提言にとどまらず、G20デジタル経済作業部会の中で実務的な議論の対象となっており、2025年9月のG20研究・イノベーション大臣会合では、DPIの国際標準評価指標に関する合意形成が目指されています。
南アフリカはこの新手法を通じて、DPIを持続可能な開発のための制度的インフラとして制度化することを狙っており、各国に対しても従来の評価手法からの脱却を促しています。
国際開発金融機関への制度的影響
南アフリカのDPI評価モデルは、国際開発金融機関(MDBs)にとっても無視できない挑戦となっています。世界銀行、アフリカ開発銀行、アジア開発銀行などは、従来CBAに準拠した融資評価プロセスを維持してきましたが、南アの新提案がG20の合意文書に組み込まれれば、これら機関の資金配分ロジックそのものが見直しを迫られることになります。
たとえば、汚職防止や社会サービス改善といった「長期的な非市場的価値」を重視する南ア型の評価手法が採用されれば、収益性に乏しいとされてきたDPI関連プロジェクトも、優先的な融資対象となる可能性が高まります。これは、アフリカのみならず、アジアやラテンアメリカの新興国にとっても、デジタル開発資金の新たな調達ルートとなり得る重要な変化です。
また、こうした枠組みの見直しは、資金だけでなく、評価指標の策定、報告義務のあり方、成果測定方法など、制度全体に波及効果を及ぼす可能性があります。南アフリカはこの点を明確に意識し、「DPIは国家の社会的資本である」と繰り返し主張しています。
このように、技術と財政の枠組みを接続する形で、南アフリカはデジタル政策と国際開発戦略を統合し、G20全体に長期的影響を与えることを目指しています。
G20と南アフリカが推進するAIの公平性と大陸主導のガバナンス構築

人工知能(AI)は今や、経済成長、産業構造、国家安全保障にまで影響を及ぼす中核的な技術とされています。しかしその発展は、欧米や中国といった技術大国に大きく偏っており、アフリカ諸国を含むグローバル・サウスはその恩恵から取り残されつつあります。こうした「技術的格差」を是正するために、南アフリカは2025年のG20議長国として、「AIの公平性」という新たな国際課題を全面に押し出しました。
本セクションでは、南アフリカの「AI in Africa」イニシアチブの内容、アフリカ連合との戦略的連携、そして高性能インフラと人材投資を通じた長期的ビジョンを詳しく解説します。
AI in Africaイニシアチブの中核目標
「AI in Africa」は、南アフリカが提唱するAI分野における戦略的構想であり、主に以下の3つの課題に対応するものです。
第一に、AIモデルの訓練に使用されるデータが偏っていること。多くのAIは欧米圏の言語・文化・生活様式を前提に設計されており、アフリカ特有の社会構造や言語、多様な文化的文脈を十分に反映できていません。これにより、アフリカでAI技術を活用しても、的確に機能しない、あるいは不適切な判断を行うといった問題が生じます。
第二に、技術開発へのアクセス格差です。AIの研究・開発を担う施設、データセンター、計算資源(HPC:高性能コンピューティング)は先進国に集中しており、アフリカではそのインフラ自体が未整備のままです。この構造的格差が、AIを取り巻く国際競争において不利な立場を固定化しています。
第三に、倫理的・法的枠組みへの関与不足です。国際的なAIガバナンス議論では、欧州連合(EU)を中心に倫理やプライバシーの議論が進んでいますが、アフリカ諸国の意見や価値観が十分に反映されているとは言い難い状況です。
こうした課題に対応するため、「AI in Africa」イニシアチブは、データの公平性、アクセスの民主化、そして倫理的多様性の確保を柱とした新たなAI政策の形成を目指しています。南アフリカはこの構想を、アフリカ全体の共通課題としてG20に持ち込み、国際的合意形成を主導する立場を取っています。
アフリカ連合との連携と地域戦略の強化
このイニシアチブを実現可能なものにするために、南アフリカはアフリカ連合(AU)と緊密に連携しています。AUは現在、アフリカ全体で統一的なAI戦略を構築する動きを強めており、各国間でばらつきのある技術政策や法制度を統一的に整備することが求められています。
具体的な連携の一例として、地域言語に対応したAIモデルの共同開発が挙げられます。アフリカには2,000を超える言語が存在しており、こうした多言語性に対応できるAIの開発は、欧米やアジア諸国が得意とする分野ではありません。したがって、アフリカ発の研究機関が主導するAIモデルの開発が、地域社会に即したサービス提供の鍵となります。
また、AU主導で進められているアフリカ大陸自由貿易圏(AfCFTA)のデジタル基盤整備と、AIの開発・活用戦略は不可分の関係にあります。越境的なデータの流通、サイバーセキュリティの基準、AI倫理の整合性などを確保するには、AU全体での政策調整が欠かせません。南アフリカはこれをG20の議題として可視化し、支援と協力の枠組みを国際社会に要請しています。
インフラと人材への戦略的投資
AIの公平性を担保するためには、倫理や制度といった“ソフト”の整備に加えて、技術基盤そのものの強化が不可欠です。南アフリカは、HPC(高性能コンピューティング)インフラの整備を急務と位置づけ、これをアフリカ全体の「技術主権」の出発点と見なしています。
すでにNVIDIAなどのグローバル企業が、南アをアフリカ拠点として位置づけ、データセンターやAI開発支援で協業を進める動きも見られます。これにより、南アフリカは「アフリカのAIハブ」としての地位を確立しつつあります。ただし、このような国際連携には、外資依存のリスクやデータ主権の課題も伴います。
そのため、南ア政府は「公平性」や「自律性」といった価値を重視し、単なる外資導入ではなく、現地人材の育成と知識移転を伴う投資モデルを提示しています。大学や研究機関と連携し、AIエンジニアやデータサイエンティストの育成に力を入れることが、持続可能な成長への道筋とされています。
G20と南アフリカのまとめ
2025年のG20サイクルにおいて、南アフリカはアフリカ大陸で初めて議長国を務めるという歴史的な役割を果たしています。これにより、アフリカが国際経済の意思決定に本格的に関与する道が開かれただけでなく、グローバル・サウスの集合的な利益がG20の議題に反映される契機となりました。
地政学的には、アメリカと中国という主要国の首脳不在がサミットの構図に大きな影を落としましたが、南アフリカは「ボイコット政治は効果がない」との姿勢を崩さず、G20の枠組みを維持・活用する外交的手腕を見せました。日本をはじめとする他の参加国は、南アフリカとの連携を通じて、多極化する国際秩序の中で新たな外交軸を模索しています。
政策面では、DPI(デジタル公共インフラ)の長期的価値評価、そしてAIの公平性確保に向けた「AI in Africa」イニシアチブが注目を集めました。これらのアジェンダは、単なる技術導入ではなく、社会的包摂や制度改革と直結するものであり、南アフリカの構想は国際的な政策議論に新たな視座を提供しています。
G20は今後もその役割と形を進化させていくことが予想されますが、2025年サイクルは、グローバル・サウスが単なる「参加者」ではなく、「方向性を定める当事者」として台頭しつつある現実を明確に示しました。こうした変化の中で、各国政府や企業、研究機関がどのような立場と行動を取るかが、次の国際秩序の形を左右することになるでしょう。
引き続き動向を注視しつつ、必要に応じて専門家に一度相談してみることをおすすめします。