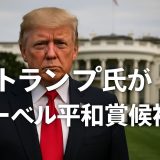請求書のやりとりや船積書類の送信など、日々の業務でデジタルデータを扱う貿易現場。最近、その業務が「ランサムウェア」というサイバー攻撃によって脅かされています。
実際に、港湾システムの停止や請求書の改ざんといったトラブルが発生し、納期の遅れや信用問題に発展したケースも少なくありません。
本記事では「ランサムウェアとは何か」を貿易実務の視点からわかりやすく解説し、現場で取るべき対策までを具体的に紹介します。
ランサムウェアとは?基本からわかりやすく解説

ランサムウェアとは、攻撃者が企業や個人のデータを暗号化し、それを元に戻すための「身代金(ランサム)」を要求するサイバー攻撃の一種です。感染した企業は、業務ファイルが開けなくなるだけでなく、情報流出や信頼失墜など多大な影響を受けます。
ランサムウェアの基本的な仕組み
ランサムウェアは、メールの添付ファイルや不正なリンク、社内の脆弱なネットワーク機器などを通じて社内システムに侵入します。感染後は、PCやサーバー上の業務データを一斉に暗号化し、ユーザーがアクセスできなくなるようにします。
多くの場合、画面上に復元の条件として仮想通貨による支払い要求が表示され、金額は数百万円から数億円にのぼるケースもあります。さらに、近年は暗号化に加えて情報を抜き取る「二重脅迫型」も増えており、仮に支払っても完全な復旧が保証されない点が問題です。
狙われやすい業界や業務の特徴とは ― 貿易実務も例外ではない
ランサムウェアの標的は、業界を問わず広がっていますが、特に狙われやすい業種には共通点があります。それは「業務停止に弱い」「重要データを扱っている」「IT人材が限られている」といった特徴です。
たとえば、医療機関や自治体、製造業、教育機関、そして中小企業などは継続的な被害報告があります。
貿易実務も同様です。請求書やB/L(船荷証券)、契約書など、機密性の高い文書を日常的に扱い、しかも取引先や通関業者、フォワーダーなど多くの外部関係者と頻繁にメールでやり取りしています。
こうした業務特性が、標的型攻撃にさらされやすい土壌となっており、感染の温床になりやすい現場と言えます。特に最近は、通関データの送信停止やB/Lの発行遅延といった、サプライチェーン全体に波及する被害も報告されています。
貿易業務は請求書・B/L・契約書など重要データを扱ううえ、海外とのメール連携が多いことから、サイバー攻撃の標的になりやすい構造にあります。攻撃の目的は情報窃取よりも「業務停止」にあり、被害は一瞬でサプライチェーン全体に波及します。
最近の感染手口とその巧妙化
以前は、不審なメールの添付ファイルを開かないことで一定の防御が可能でした。しかし現在は、攻撃の手口が高度化・巧妙化しており、実務現場での見極めが難しくなっています。
代表的な感染手口には以下のようなものがあります。
- 実在の取引先を装った請求書や輸送確認メールに不正ファイルが添付されている
- DropboxやGoogle Driveなど、クラウドストレージ経由の偽リンクで感染を誘導する
- すでに感染した海外取引先の正規アカウントからマルウェアが転送されてくる
特に貿易実務では、「締切が迫っている」「出荷が近い」といった状況で、ファイルの確認を急いでしまうことが多く、攻撃者はそうした心理的隙を巧みに突いてきます。
ランサムウェアの脅威は、技術的な脆弱性だけでなく、日々の業務フローや人の判断ミスに起因するケースが多いため、まずは正しい知識を共有し、リスクを可視化することが対策の第一歩になります。
実際に起きたランサムウェア被害事例と教訓

2025年もランサムウェアの脅威は収まる気配がありません。警視庁によれば、今年上半期だけで国内企業の被害は116件にのぼり、過去最悪水準に迫るペースと報じられています。
実際、2025年10月には大手飲料メーカーのアサヒグループがランサムウェア攻撃を受け、受注や出荷に大きな影響が出ています。影響を最小限にとどめるため手作業への切り替えを余儀なくされるなど、現場のオペレーションにも深刻な支障が出ています。
この影響で、一部製品の供給が遅れ、店舗や自動販売機で飲料の在庫が不足するなど、私たちの生活にも影響が広がっています。
以下に、貿易や製造、サプライチェーンに影響を与えた実在の事例を3つ紹介します。それぞれから、貿易実務者が学ぶべき具体的な教訓を整理します。
自動車メーカーの工場停止 ― サプライチェーン全体に及ぶ生産リスク
2020年、国内の大手自動車メーカーがランサムウェア攻撃を受け、国内外9か所の工場で出荷停止が発生しました。社内ネットワークに侵入した攻撃者が中枢サーバーを制御し、通信を遮断。本社PCの使用も制限されました。
この被害は、完成車・部品の輸出業務にも波及し、納期の遅れや契約トラブルが懸念されました。自社の感染だけでなく、取引先の業務停止が輸出入全体に影響する点に注意が必要です。
食品メーカー(日清製粉グループ)への攻撃 ― データ暗号化で業務全体が停止
2021年、大手食品メーカーがランサムウェアに感染し、基幹業務システムとバックアップが暗号化されました。データ復旧に時間がかかり、決算発表も3ヶ月遅延。攻撃は巧妙な手口でセキュリティ対策を突破したとされています。
食品業界では、輸出向け商品の生産・検査・書類発行が不可欠です。こうしたインシデントが起きた際に、社内のどのデータが貿易書類に関係するかを把握し、復旧手順を明文化しておく必要があります。
米国物流テクノロジー企業への攻撃 ― 世界の小売・配送が麻痺
2024年、物流支援システムを提供するアメリカのIT企業がランサムウェア攻撃を受け、倉庫管理・配送システムが停止しました。その影響で、英国の食品小売業では入荷・配送が止まり、店頭で品薄状態が続く事態となりました。
このような間接被害は、輸出入業務にも影響を与えます。B/Lの発行や通関書類の準備ができなければ、出荷の遅延・損害賠償のリスクも高まります。委託先のセキュリティ水準の把握や、緊急時の運用ルールの整備が求められます。
ランサムウェアが貿易業務に与える影響とは

一見すると、ランサムウェアはIT部門の問題に思えるかもしれません。しかし、実際に感染が発生した場合、通関や出荷、決済といった貿易の中核業務がストップし、社内だけでなくサプライチェーン全体に深刻な影響を及ぼします。
出荷・通関手続きへの影響
ランサムウェアにより社内ネットワークやファイルサーバーが暗号化されると、インボイスやB/L(船荷証券)、パッキングリストといった出荷に必要な書類が作成・送信できなくなります。これにより、通関手続きが進まず、出荷スケジュールに遅れが発生します。
書類の不備や送信の遅延が続くと、輸入先からの信頼を損ない、最悪の場合キャンセルや違約金請求の対象になる可能性もあります。輸出入は書類が命とも言える業務であり、書類が1枚でも止まれば、貨物は動きません。
決済業務・送金トラブルの発生
ランサムウェアの感染は、決済業務にも直接的な影響を与えます。近年は、攻撃者が企業内のメールを監視し、取引先を装って支払い口座情報を偽装する「BEC(ビジネスメール詐欺)」と組み合わせた手口が増えています。
特にL/C(信用状)による決済など、期日が厳格に決められている取引では、1件の遅延が大きな契約リスクにつながります。送金後に口座情報が偽物だったと判明しても、国際送金の場合は資金の回収がほぼ不可能です。
業務上「メールベースの指示」が多い企業ほど、こうした被害に遭いやすく、管理体制や確認プロセスの見直しが急務となります。
「L/C決済とは何か」「何がトラブルになりやすいのか」については以下の記事をご覧ください。送金や信用状管理に関わる方は必見です。

サプライチェーン全体への波及
自社が万全なセキュリティ対策を講じていたとしても、通関業者、フォワーダー、船会社、港湾施設など、外部パートナーがランサムウェアに感染すれば、結果的に自社の業務も止まることになります。
たとえば、港湾システムが止まれば、貨物の引き取りも船積みもできません。フォワーダーの通関申告が止まれば、出荷は予定通りに進みません。つまり、1社の被害が物流全体に連鎖的に波及する構造にあるのが貿易業務の特性です。
このような間接的リスクを見越し、単に「自社を守る」だけでなく、取引先の体制確認やBCP(事業継続計画)の共有も含めた対策が求められています。
ランサムウェアの感染経路とは?わかりやすく解説
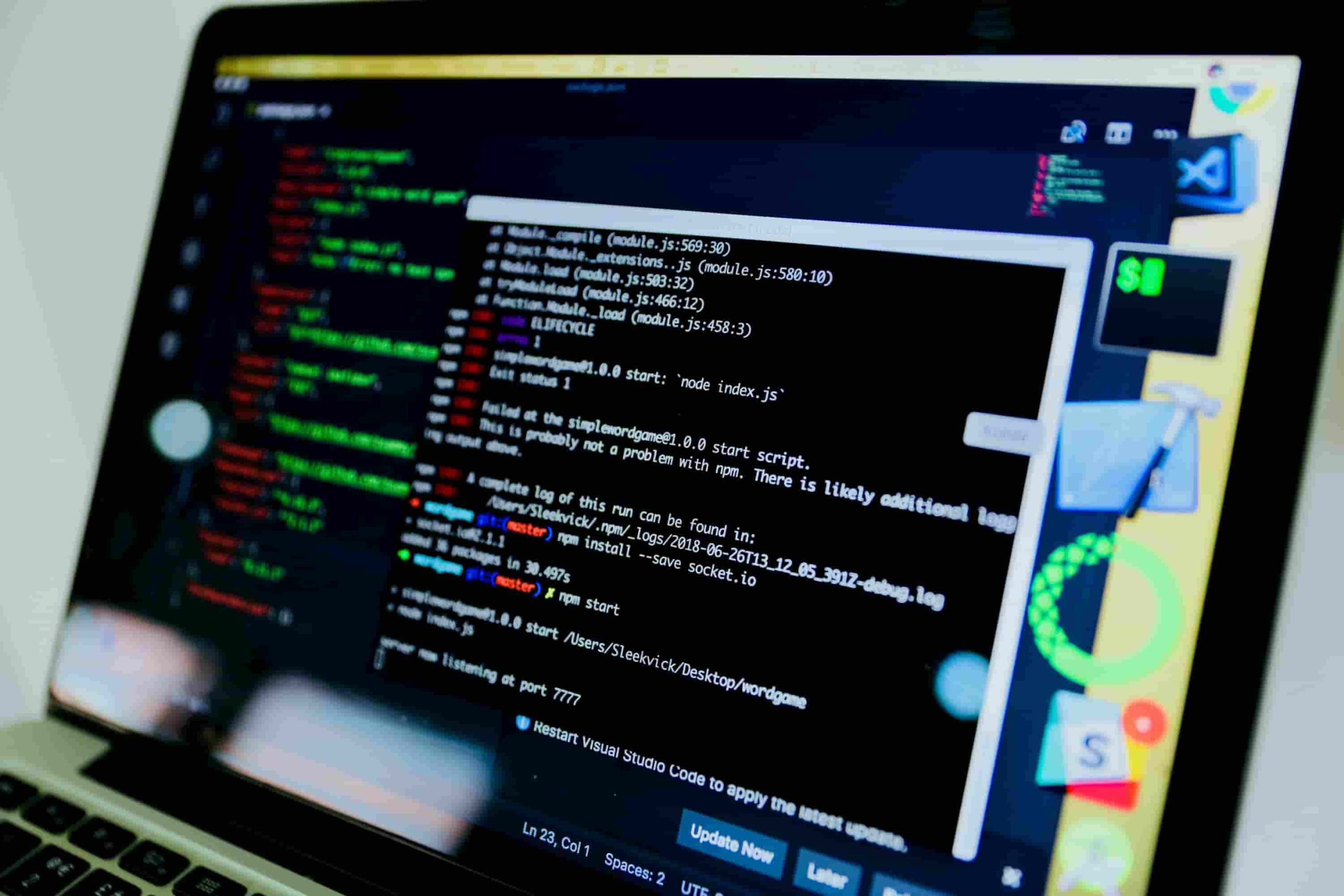
ランサムウェアの感染経路は多岐にわたりますが、共通しているのは「日常業務の流れの中に違和感なく紛れ込む」点です。特別な操作や意識をしなくても、日々のルーチン作業の中で感染してしまうケースがほとんどです。
偽の請求書や輸送確認メール
もっとも典型的かつ多いのが、請求書やインボイスに偽装された添付ファイルを含むメールです。攻撃者は、実在する取引先名や過去のやり取りを模倣して、いかにも「業務上のやり取り」のように見せかけた内容でメールを送ってきます。
件名には「送金確認」「新規発注書」など、急ぎで開きたくなる文言が使われることが多く、実務担当者がそのまま添付ファイルを開いてしまうことで感染が始まります。
特に、繁忙期や決算期など、業務が立て込んでいるタイミングを狙って送られるケースが目立ちます。
ファイル共有リンク・クラウド経由
最近では、Google Drive、Dropbox、OneDriveなどのクラウドストレージを利用した攻撃も増加しています。メールには添付ファイルがなく、「こちらから確認ください」と書かれたリンクが記載されており、それをクリックすると不正ファイルがダウンロードされる仕組みです。
クラウド型のリンクは業務でも日常的に使われるため、添付ファイルほどの警戒心が働きづらく、セキュリティチェックの対象外となることも多いため、実務担当者が無意識に開いてしまうリスクが高くなっています。
海外取引先からのメール転送
貿易業務に特有の感染経路として、海外のパートナー企業が感染源となるケースがあります。相手側の社内システムがすでに感染しており、彼らの正規アドレスからマルウェアが仕込まれたメールが送信されてくるため、通常のセキュリティチェックでは見逃されやすいのが特徴です。
長年取引のある企業や、頻繁にやり取りしている担当者からのメールであればあるほど、疑いなくファイルを開いてしまい、社内ネットワーク全体に感染が広がる危険があります。
このように、ランサムウェアの感染経路は「業務上当然の動き」に巧妙に偽装されており、特別なスキルがなくても誰もが感染の入り口になり得ます。対策の第一歩は、「よくある業務フローにこそリスクが潜んでいる」と全社員が意識することです。
貿易企業が取るべきランサムウェア対策とは

ランサムウェアの脅威を完全に防ぐことは現実的ではありません。しかし、感染リスクを抑え、被害が発生した際の影響を最小限にとどめる体制を構築することは可能です。
特に貿易業務では、書類やデータが止まれば取引そのものが成立しなくなるため、技術・運用の両面から備えが必要です。
現場レベルの初動対策
日常的にメールやファイルを扱う実務担当者にとって重要なのは、「不用意に開かない」という当たり前の行動を徹底することです。具体的には、以下のような対応が有効です。
- 添付ファイル付きメールは、送信元や文面に違和感がないかを必ず確認する
- 「急ぎの対応」を促すメールこそ、一度立ち止まって上長に相談する
- メールに記載されたリンクを安易にクリックしない
- B/Lやインボイスなど重要書類の送信を受けた際は、相手に電話など別経路で真偽を確認する
感染の多くは、こうしたほんの一瞬の判断ミスから始まります。現場での教育と注意喚起を継続的に行うことが最も基本的かつ効果的な対策です。
管理者が検討すべきセキュリティ体制
現場任せの対策には限界があります。システム部門や経営層には、組織としての防御力を高める取り組みが求められます。特に次のようなポイントが重要です。
- EDR(Endpoint Detection and Response)の導入や、セキュリティソフトの自動更新設定
- 業務システムやファイルサーバーのバックアップを「複数地点・世代別」に確保
- バックアップデータは社内ネットワークと切り離して保存(ランサムウェアはバックアップも暗号化する)
- クラウドとオンプレミスの併用による「二重保存」の活用(特にインボイスや契約書などの書類データ)
さらに、取引先や委託先を含めたセキュリティ基準の見直しも重要です。フォワーダーや港湾会社の被害が自社業務に波及するため、委託先とのセキュリティ運用ルールを共有しておくことが求められます。
セキュリティ対策とあわせて、「HSコードの分類や関税対応を安全に進めるにはどうするか」も重要です。実務担当者向けに整理した以下の記事をご参照ください。

被害時に備えた初動マニュアルの整備
どれだけ備えても、攻撃を完全に防ぐことはできません。だからこそ、「万が一の時にどう動くか」を事前に明文化しておくことが重要です。
- 感染が疑われた際の社内連絡フロー(誰に、どう報告するか)
- システム停止時の業務継続方法(代替手段の確認)
- 取引先や顧客への影響説明テンプレートの準備
- 外部のセキュリティベンダーや法律事務所との連絡体制の構築
- CSIRT(Computer Security Incident Response Team)体制の立ち上げ、または外部委託の契約
対応の初動が早ければ早いほど、被害の拡大を防ぐことができます。年に1回程度でも、模擬訓練を行うことで「想定外の混乱」を最小限にとどめることが可能です。
まとめ
ランサムウェアとは、単なるITの問題ではなく、今や貿易業務全体を止めかねないリスクです。出荷・通関・決済というビジネスの根幹を支える業務が狙われる以上、現場・管理者ともに高い意識が必要です。
メールひとつ、ファイルひとつが感染のきっかけになる時代。だからこそ、「気づかないリスク」を前提とした備えが企業の信頼を守る鍵になります。自社だけでなく、取引先や委託先まで含めたセキュリティ体制を見直し、現実的な運用とマニュアル整備を進めましょう。
もし自社のサイバー対策や対応方針に不安がある場合は、専門家に一度相談してみることをおすすめします。