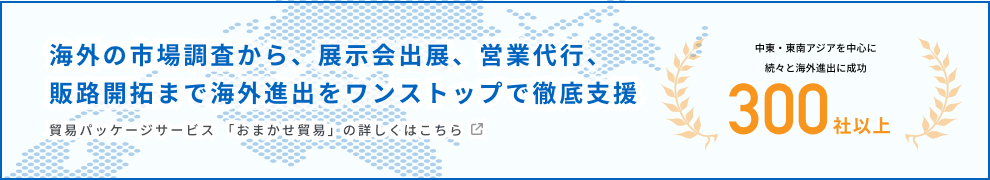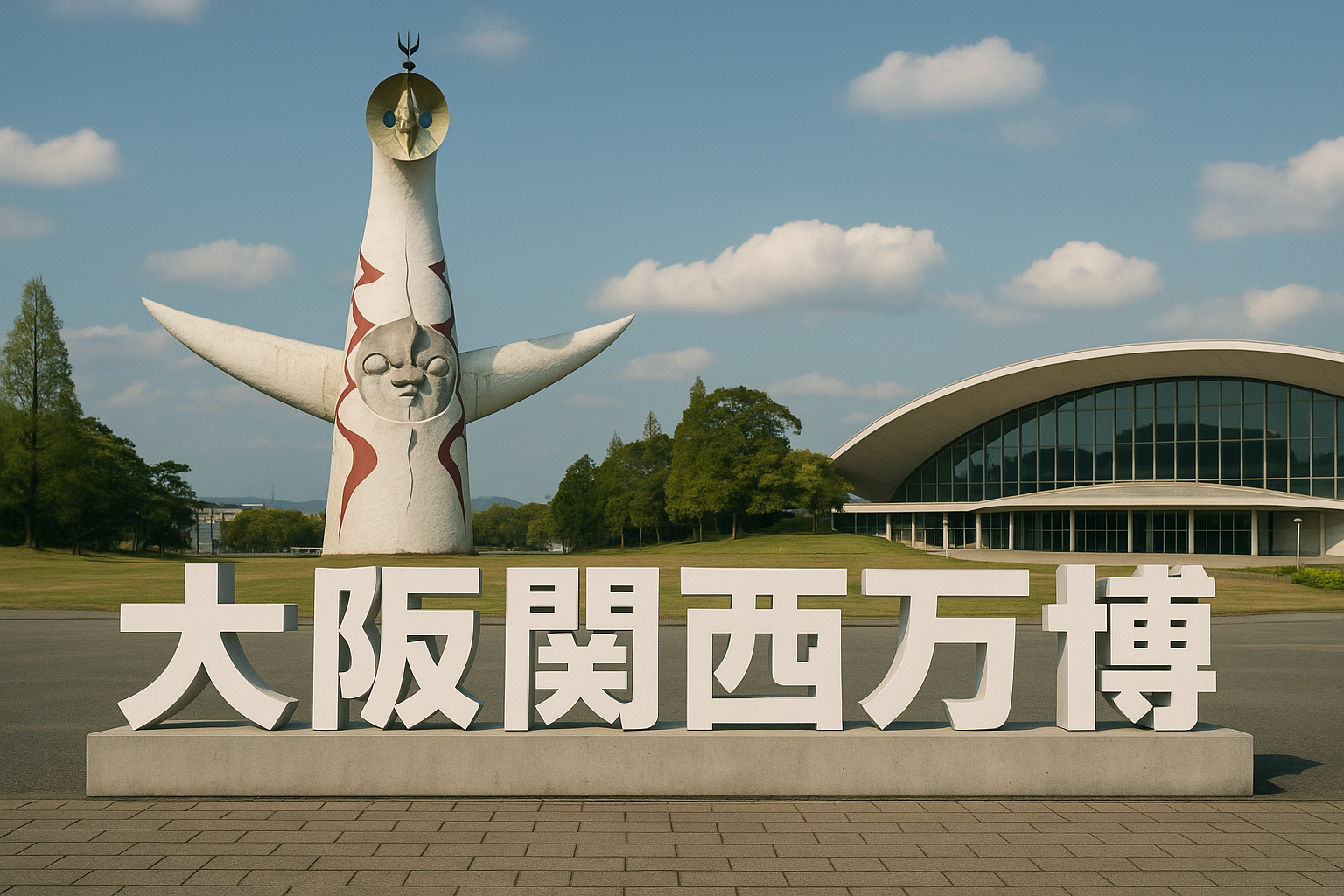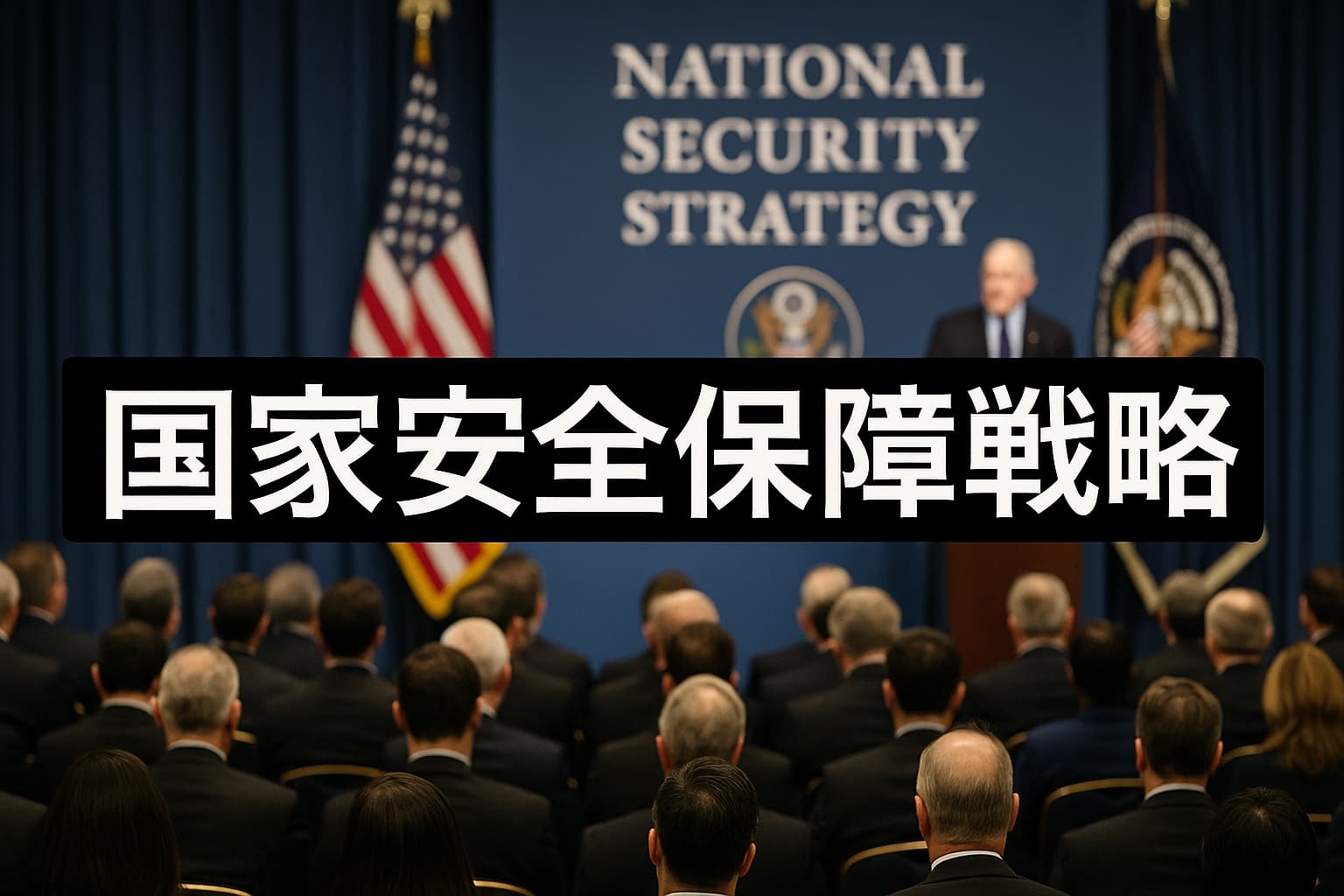2025年7月に予定されている参議院選挙は、私たちの生活や将来に直結する政治の大切な節目です。
今回の選挙では、経済安全保障、産業支援、外交姿勢などが主要な争点として注目されており、これらは日本の貿易政策の方向性や海外展開支援にも大きく影響を及ぼします。 与野党間で、対外経済戦略や通商交渉へのスタンスにも違いが見られるため、グローバル経済の視点からも注目すべき選挙となっています。
しかし「仕組みがよく分からない」「どう投票すればいいのか不安」という声も少なくありません。
この記事では、参議院選の基本的な制度から、今回の選挙の注目点までを一つひとつ丁寧に解説します。
最新の貿易実務・政策動向については、X(旧Twitter)でも随時発信中です。ぜひ @bouekidotcom をフォローして、海外展開に関わる情報をチェックしてください。
参議院選の仕組みとは?―衆議院との違いを押さえよう

日本の国会は、衆議院と参議院からなる二院制を採用しています。
それぞれが異なる役割を持ち、制度設計にも違いがあります。参議院選の仕組みを理解するには、まず衆議院との違いを知ることが大切です。
衆議院と参議院の違い
| 項目 | 衆議院 | 参議院 |
|---|---|---|
| 任期 | 4年(解散あり) | 6年(解散なし、3年ごとに半数改選) |
| 定数 | 465名 | 248名 |
| 主な役割 | 内閣の信任・不信任 予算審議など | 慎重な審議 長期的視点での政策検討 |
| 選挙制度 | 小選挙区比例代表並立制 | 選挙区制+比例代表制(非拘束名簿式) |
衆議院は「政権選択選挙」と呼ばれることがある通り、内閣の信任・不信任に直接関与します。一方、参議院は内閣の信任制度がなく、政権の直接的な影響は受けません。
そのため、衆議院が「民意の即時反映」に向いた制度であるのに対し、参議院は「長期的かつ安定的な政策審議」に重きを置いた制度となっています。
参議院の定数と改選の仕組み
参議院の定数は248名で、6年の任期を持ちます。しかしすべての議員が一度に選ばれるわけではなく、3年ごとに半数(124名)が改選される仕組みになっています。これは議会の継続性と安定性を保つためであり、仮に衆議院で政権交代があった場合でも、参議院が急激に変化することを防ぐ意図があります。
二院制の役割分担
衆議院と参議院の両院が法律案や予算などを審議しますが、最終決定権は衆議院にあります(いわゆる「衆議院の優越」)。ただし、参議院が否決した法案でも、衆議院で再可決すれば成立することが可能です。
この制度設計は、迅速な政策決定を促す一方、参議院によるチェック機能も確保しています。
特に近年は、与野党の勢力が拮抗しているため、参議院の動向が政策の方向性に与える影響が大きくなっており、選挙の重要性が再認識されています。
2025年参議院選挙では、参議院の定数248名から半数124名が改選対象となり、有権者は「選挙区」と「比例代表」の2票を使って投票する仕組みになっています。比例代表制では非拘束名簿方式を採用し、政党名・個人名どちらでも投票可能で、名簿上の順位と個人得票によって当選者が決まる点が特徴です。
2025年参議院選の選挙制度―選び方のルールを理解しよう

参議院選挙では、「選挙区制」と「比例代表制(全国単位)」の二つの方式が併存し、有権者はそれぞれに一票ずつ投票します。制度面の理解は、投票行動の意味を深く知るための第一歩です。
選挙区制:地域代表を選ぶしくみ
日本全国は45の選挙区に分けられ、都道府県ごとに定数が割り当てられています。人口の多い地域では複数人が選出される一方、小規模県では1名のみということもあります。
- 投票の対象:各地域で立候補している候補者の中から1名を選ぶ
- 方式:相対多数制(最多得票者が当選)
- 合区の継続:人口減少を背景に、鳥取・島根や徳島・高知では2県で1つの選挙区が設けられています。
この制度では、地元課題や候補者の人柄・実績が重視される傾向にあり、「地域密着型」の選択が行われやすくなっています。
比例代表制:全国規模で政策・理念に投じる票
比例代表制では、日本全体を一つの大きな選挙区とみなして、政党や個人に票を投じます。
- 投票の対象:政党名または候補者名(どちらも有効)
- 方式:ドント式で各党の得票数に比例して議席を分配
- 名簿方式:非拘束名簿式(有権者の個人名投票で順位が決まる)
この制度により、政党全体の政策や理念への評価、あるいは特定の候補者への支持を直接反映することができます。
ドント式とは、政党ごとの得票数を「1、2、3……」と順に割っていき、その割り算の結果が大きい順に議席を配分する方法です。例えば、ある政党が10万票を得た場合、その得票数を1で割った10万、2で割った5万、3で割った約3.3万……という数値を出し、すべての政党の割り算結果を並べて、得点の高い順に議席が与えられます。
この方式の特徴は、比例性を保ちつつも「大きな政党にやや有利」になる傾向がある点です。そのため、少数政党が議席を獲得するには、ある程度まとまった票数が必要になります。
一方で、名簿順位が個人得票で決まる非拘束名簿式と組み合わされているため、有権者は個人名でも政党名でも投票でき、候補者個人の支持が議席獲得につながる仕組みになっています。
2025年選挙での注目制度
2025年の参議院選挙では、比例代表枠で50議席が改選される予定です(選挙区74+比例50=計124議席)。この選挙制度を通じて、全国的な政党支持の傾向がより明確に表れます。
なかでも注目されるのが「特定枠」の制度です。これは、政党があらかじめ名簿上位に指定した候補者を、個人名の得票数にかかわらず当選させる仕組みで、障害者や介護従事者など選挙運動が難しい人材の政治参加を後押しする目的があります。
比例代表の公平性を保ちつつ、多様性ある議会形成をめざす制度として注目されています。
投票の流れと実務 ― 有権者としての準備と当日の対応

選挙制度を理解することに加えて、「実際の投票行動」がスムーズにできるかどうかは、有権者にとって非常に重要です。ここでは、投票所での具体的な流れや、投票前後に確認しておくべき実務的なポイントを詳しく解説します。
投票に行く前に準備しておくこと
- 投票所入場券の確認
- 各自治体から郵送される「投票所入場券」は、当日の受付でスムーズに本人確認を行うための大切な書類です。
- 事前に届いているか確認し、紛失しないよう保管しておきましょう。
- 候補者や政党の公約チェック
- 投票所に行く前に、どの候補や政党に投票するかを決めておくと、現地での迷いがなくなります。
- 新聞・公式Webサイト・SNS・政策比較サイトなどを活用しましょう。
- 投票日と投票所の場所・時間を把握
- 自治体によっては投票所が変更になっていることもあるため、入場券の案内を必ず確認。
- 基本的には朝7時〜夜8時まで開いていますが、地域によって若干の違いがある場合もあります。
投票当日の流れ
- 受付で入場券を提示(または氏名確認):紛失していても、本人確認ができれば投票は可能。身分証が求められることがあります。
- 種類の投票用紙を順に受け取る:白い投票用紙(選挙区)と黄色い投票用紙(比例代表)を別々のタイミングで受け取ります。
- 記載台で記入 :投票用紙に鉛筆で記入。記入間違いがあった場合は係員に申し出れば新しい用紙に交換してくれます。
- 投票箱に投入:記入が済んだら、所定の箱にそれぞれ投票します。順番は案内係の指示に従いましょう。
よくある注意点とQ&A
Q.「政党名」と「候補者名」、どっちを書くの?
→ 比例代表ではどちらでもOK。ただし、両方はNG(無効票になる可能性あり)。明確にどちらか一方だけ記入しましょう。
Q. 名前を間違えたら?
→ 記入前なら訂正可能。係員に申し出て交換用紙をもらってください。無理に修正しないことが大切です。
Q. 読みやすく書けていないと無効?
→ ひらがな・カタカナでもOK。判別できれば有効票として扱われますが、同姓同名など紛らわしい場合には注意が必要です。
投票に行けない場合の対処法
- 期日前投票(理由不要)
- 選挙期間中、全国の期日前投票所で投票可能です。仕事・旅行・体調など理由は問われません。
- 不在者投票
- 遠方で生活している学生や単身赴任者、入院中の方などは、申請により他の自治体で投票できます。
- 郵便等投票
- 重度の身体障害などで外出が困難な方は、郵送での投票も可能(申請期限あり・自治体対応)。
電子投票試験の進展
電子投票機器の導入は、一部自治体で投票所内タッチ端末などによる試験的な実証実験が進められています。在外投票の利便性向上や、障害者・高齢者の投票環境改善を目的としているものの、実施されるのはごく限られた地域にとどまります。
一方、インターネットを通じた在宅ネット投票はセキュリティ面での課題も大きく、2025年7月の参院選では導入されていません。今後は実証結果を踏まえた制度整備の動きが注目されます。
2025年参議院選の注目ポイント―争点と主要政党の動き

2025年の参議院選挙は、経済不安、地政学的リスク、エネルギー転換といった複合的な課題が交錯する中で実施されます。こうした環境の中、政党ごとに重点を置く政策分野が異なり、有権者の選択肢も多様化しています。
以下では、政策別の争点と政党の姿勢、さらに今回特に注目すべきテーマについて整理します。
各政党のスタンス比較
| 政策分野 | 主な争点 | 各党の基本的立場 |
|---|---|---|
| 経済政策 | 物価上昇 実質所得減少 賃上げ | 与党は物価高対策、 賃上げ支援、給付金実施。 野党は消費税減税やベーシックインカム、 分配強化を主張。 |
| 安全保障 | 台湾有事 防衛費増額 日米同盟 | 与党は防衛力強化を推進。 立憲は外交重視の抑制路線、 共産・社民は専守防衛と平和外交を強調。 |
| エネルギー政策 | 原発再稼働 電力価格 | 与党は原発再稼働を含む現実路線。 野党は脱原発と再エネ強化を掲げ、 価格安定と環境重視を両立させる方針。 |
| 通商・経済外交 | 経済安全保障 FTA/EPAの活用 | 与党は自由貿易推進と 経済安全保障の両立を掲げ、 対中依存の見直しや 重要物資の国内確保を重視。 野党は中小企業の海外展開支援や 地域連携を強調。 |
| デジタル・AI政策 | 行政DX 教育分野へのAI導入 規制整備 | 与党はAI活用による生産性向上と ルール整備の両立を重視。 野党は格差是正や 教育分野での慎重導入を訴える。 |
| 社会政策 | LGBTQ+ 同性婚 差別禁止法 ジェンダー平等 | 野党は法整備と権利拡充を推進。 与党内では一部慎重論も根強く、 党内議論が分かれるテーマ。 |
| 地方創生 | 人口減少 インフラ老朽化 地域経済 | 与党は地方交付金や観光支援、 インフラ更新を進める。 野党は自治体主導の活性化や 地方への分権強化を掲げる。 |
経済政策の違い
与党(自民・公明)は、物価上昇に対して給付金支給や企業への賃上げ要請を通じた支援策を打ち出し、景気回復と分配の両立を目指しています。消費税については当面維持する方針を示しています。
一方、立憲民主党は消費税減税による可処分所得の回復を重視し、共産党は富裕層・大企業への課税強化とベーシックインカムの導入を訴えています。
日本維新の会は成長戦略と規制改革の推進を中心に据え、民間主導の経済活性化を掲げています。
安全保障の論点
防衛費をGDP比2%水準に引き上げた現政権に対し、野党各党は慎重な姿勢を示しています。
与党は台湾有事への備えや、安保三文書に基づく抑止力強化を進めています。
立憲民主党は、外交努力を優先しつつ現実的な安全保障政策の必要性も認めており、共産党や社民党は専守防衛と非軍事的手段の強化を一貫して主張しています。
エネルギー政策の方向性
エネルギー政策では、原子力発電の再稼働を容認する与党と、再生可能エネルギーへの全面的移行を目指す野党の間で方針が分かれています。
自民党は電力の安定供給と経済性の観点から原発の活用を含む「現実的エネルギーミックス」を掲げ、公明党は再生可能エネルギーとのバランス重視を主張しています。
立憲民主党や共産党は、原発ゼロを将来的な目標とし、再エネ投資拡大による脱炭素社会の構築を優先課題に据えています。
通商・経済外交政策の違い
与党(自民・公明)は、米国やCPTPP参加国との自由貿易体制の強化、対中依存の是正、重要物資の国内回帰を柱とする「戦略的通商政策」を推進。すでに政府は、「経済安全保障推進法」(2022年成立)を通じて、半導体や電池、医薬品などの供給網強化や輸出管理体制の整備に取り組んできました。
また、日EU経済連携協定(EPA)やCPTPPの発効・運用を主導し、多国間での貿易自由化と経済圏拡大にも積極的です。インド太平洋地域との経済連携や資源確保も政策の重点に据えています。
一方、野党(立憲民主党、維新、共産党など)は、中小企業の海外展開支援やFTA再交渉時の透明性確保、地域経済と国際経済の橋渡しとなる制度設計を重視。特に中堅・中小企業の輸出機会創出や人材・資金支援の強化を訴えています。
さらに、経済制裁や技術輸出管理など、安全保障と通商が交差する領域の重要性が増す中、各党の政策には違いが見られます。輸出規制や経済的威圧への対応などを含め、経済安全保障と貿易政策の一体運用をどう進めるかが、今回の選挙でも重要な論点となっています。
こうした政策の違いは、国際交渉での立場や、企業が輸出や海外進出を行う際の支援制度にも直結します。
有権者の選択が、将来の通商ルールや国際経済の中での日本の立ち位置を左右する可能性があるのです。
今回の選挙で浮上する新たな焦点
2025年の選挙では、従来の経済や安全保障に加え、以下のような新たな課題も争点化しています。
- 生成AI・デジタル政策の整備
- 行政DXや教育分野へのAI導入を巡る議論が活発化しており、各党の姿勢に注目が集まります。
- LGBTQ+・多様性政策
- 同性婚や差別禁止法の整備について、政党ごとに賛否が分かれており、若年層を中心に関心が高まっています。
- 地域間格差と地方創生
- 人口減少やインフラ老朽化に直面する地方での政策提案が問われ、合区選挙区における発言力も注目されています。
注目の選挙区と候補者
今回の選挙では、SNSを活用した候補者の発信力やデジタル広報の巧拙が支持拡大に直結する構図が顕著です。特に以下のような傾向が見られます。
- 激戦区の増加
- 神奈川、愛知、大阪、福岡などの複数人区では、与野党・新人・無所属が入り混じる混戦模様となっており、選挙終盤まで予断を許しません。
- 新人候補の台頭
- 民間出身や若手弁護士、医師など、実務経験を背景に政策発信力を強める新人候補が増えており、無党派層や若年層からの支持が期待されています。
- 女性候補の増加
- 各党が候補者のジェンダー・バランスに配慮し、女性候補の擁立を強化。政策の多様性に反映されるかも注目です。
投票行動に影響を与える要因
2025年の選挙では、以下のような要因が投票率や結果に大きく影響を与えると予測されます。
| 要因 | 内容 |
| 若年層の動向 | SNSや動画配信を通じた候補者情報の取得が活発。 関心層の可視化が進む。 |
| メディア報道 | テレビ討論や政策比較報道が浮動票に影響を与える可能性 |
| 有権者教育 | 学校や自治体での模擬選挙・主権者教育が投票行動のきっかけに |
今回の参院選では、政党支持よりも個人の資質や政策内容への注目が高まっている傾向にあり、有権者が「誰に投じるか」だけでなく「何に共感するか」が投票の決め手になると見られています。
まとめ
参議院選の制度や仕組みを理解することで、自分の一票がどのように政治や社会に反映されるのかを具体的にイメージできるようになります。2025年の参院選では、「選挙区制」と「比例代表制」の2票を通じて、地域課題と全国的な政策課題の両方に意思を示すことが可能です。
また、今回の選挙では、物価高や雇用といった日常生活に直結するテーマに加えて、経済安全保障、産業支援、外交姿勢といった中長期的な国家戦略も重要な争点となっています。
これらの方向性は、日本の貿易政策や国際経済における立ち位置にも影響を与えるため、海外ビジネスや輸出入、国際協力に関心のある方にとっても見逃せない選挙です。
また、選挙によって政権や政策の方向性が変われば、為替市場も大きく動く可能性があります。特に円高・円安は、企業の輸出入や投資に直結する重要なファクターです。
以下の記事は、為替の基本と、今の経済情勢における円相場の動きを知りたい方におすすめです。

海外販路開拓をゼロから始めるなら『おまかせ貿易』
『おまかせ貿易』は中小企業が、低コストでゼロから海外販路開拓をするための"貿易代行サービス"です。大手商社ではなしえない小規模小額の貿易や、国内買取対応も可能です。是非一度お気軽にお問い合わせください。