2025年現在、台湾は日本産食品の輸入規制を全面撤廃し、従来求められていた産地証明書や放射性物質検査証明の提出が不要となりました。これにより、福島・茨城・栃木・群馬・千葉といった特定5県を含む品目でも、追加的な提出を求められない“平常条件”での輸入が可能となり、日本企業にとって大きな追い風となっています。
ただし、規制撤廃=すべての手続きが簡略化されたわけではありません。台湾は依然として食品安全・表示制度(TFDA)を厳格に運用しており、品目によっては成分証明・ラベル表示・輸入者登録などの事前準備を誤ると、通関保留・返品・販売差止めといった実務的なトラブルが発生します。
本記事では、規制撤廃後の最新動向を踏まえつつ、「自社の商品は台湾に輸出できるのか?」という疑問に対し、判断軸と次のアクションを実務視点で整理します。食品カテゴリ別の対応、必要書類、よくある現場トラブル、輸入者との調整ポイント、初回輸出と継続輸出の違いまで網羅し、この記事だけで台湾向け食品輸出の全体像と落とし穴を理解できます。
台湾への食品の輸出に必要な規制対応と手続きの基本

台湾に食品を輸出するには、単に商品を海外に送るだけでは不十分です。台湾には独自の食品安全基準、表示ルール、書類要件があり、それらに対応した準備が必要です。
このセクションでは、食品ごとに異なる台湾の輸入規制と、それに対応するための実務フロー、必要書類、表示整備の内容をわかりやすく解説します。
輸出に必要な主な書類と準備項目
台湾への食品輸出では、以下の書類がほとんどの品目で求められます。品目の特性や輸入者側の判断により、追加書類が必要となる場合があるため、自社製品の条件に合わせて事前確認することが重要です。
| 書類名 | 概要 | 特記事項 |
|---|---|---|
| 原産地証明書 | 商品が日本国内で製造・加工されたことを証明 | 台湾では都道府県レベルの原産地表示が求められるケースがあり、記載内容と申請元の不一致は差し戻しの原因となる |
| 放射性物質に関する検査資料 | 食品が台湾の基準値(セシウム134+137合計100 Bq/kg以下)を満たすことを示す | 2025年11月に日本5県(福島・茨城・栃木・群馬・千葉)に対する特別規制は撤廃。ただし、輸入者の判断や品目のリスクに応じてサンプリング検査や証明提出を求められる場合あり。 |
| 成分証明書 | 食品添加物や成分の含有量を示す資料 | 成分名の翻訳・単位表記(g/mgなど)・日本語原文との整合性で不備が発生しやすい。TFDAが認める形式を使用。 |
| ラベルサンプル | 台湾で販売する際のパッケージ見本(現物またはPDF) | 表示内容は繁体字で記載。表示項目の順序・栄養成分表・保存条件・原産地(都道府県)などTFDAの要件に準拠する必要あり。 |
これらの書類は台湾側輸入者に任せるのではなく、輸出元が正確なデータと根拠に基づいて準備することが重要です。提出経路は輸入者経由となる場合が多いものの、内容の正確性に対する責任は輸出側にある点に注意しましょう。
台湾通関を通すための実務フローと注意点
台湾での通関は、単に書類が揃っているだけでは完了しません。現地でのラベル確認や輸入者登録、検査対応まで含めた一連のフローを把握しておく必要があります。
以下は、食品輸出時に必要となる標準的な手続きの流れです。
- 台湾側輸入者がTFDAに登録済であるかを確認する
- 原産地証明、検査証明、成分証明、ラベルなどの必要書類を輸出元で事前に準備する
- サンプルラベルの内容について台湾側と事前にすり合わせを行う
- 商品を出荷し、現地到着後に通関と検査が行われる(抜き取り検査の可能性あり)
- 問題がなければ通関完了となり、市場での流通が可能になる
台湾の通関では、形式的な記載ミスでも保留・差し戻しとなるケースが多く見られます。特にラベル内容の誤記や順序の違い、翻訳ミスなど、細部の不備が通関の遅延につながることがあります。
検査や書類の提出順序についても、輸出前に台湾側の輸入者と確認を取ることが大切です。
TFDAが求める食品表示とラベルの整備
台湾ではTFDA(台湾食品薬物管理署)が食品の表示制度を厳しく管理しています。
日本と異なる規則が多数あるため、台湾向けの商品ラベルは専用に設計する必要があります。
| 表示項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 商品名 | 台湾で一般に使用される名称を繁体字で記載 | 日本語やカタカナのままでは不可。誤訳や意訳も通関で指摘されやすい |
| 原材料名 | 含有量の多い順に、食品添加物を含めて記載 | 表記順・記号・単位などに規定があり、統一性が求められる |
| 栄養成分表示 | 熱量、たんぱく質、脂質、糖質、ナトリウムなど | 単位(g/kcal)や表示順が日本と異なる場合がある |
| 保存方法 | 常温、冷蔵、冷凍などの管理方法を明確に表記 | 曖昧な表現(例:「涼しい場所」)は不可とされることがある |
| 原産地表示 | 製造地または主原材料の都道府県を明記 | 「日本」など国名のみの記載は不十分とされ、差し戻されることがある |
ラベルは、繁体字で印刷された現物またはPDF形式の提出が必要です。翻訳の誤りや栄養成分の誤表記は、TFDAのチェックで止められる理由として特に多く報告されています。
商品ごとに表示すべき項目を一覧化し、日本語版と台湾向け版の差異を明確にしたうえで設計することが推奨されます。
台湾食品の輸出可否をカテゴリ別に判断するための実務ガイド
台湾への食品輸出において重要なのは、自社製品が輸出条件を満たしているかを正しく判断することです。
制度の全体像を把握したうえで、次に確認すべきは商品ごとのリスクと対応の違いです。
本セクションでは、食品カテゴリごとの規制傾向、必要な検査、表示の難易度を整理し、輸出の可否を判断する材料を提供します。
特に初回輸出を検討する企業にとっては、これらの整理がコストや準備工数の見積もりにも直結します。
商品カテゴリ別のリスクマップと対応の難易度
以下の表は、実際の輸出現場でよく扱われる商品群をもとに、台湾輸出時に直面しやすい主な規制リスクや対応項目をまとめたものです。
| 商品カテゴリ | 主な規制対象 | 要求される検査 | 表示の難易度 | 総合評価 |
|---|---|---|---|---|
| 和菓子 | 添加物、寒天 | 成分証明 | 中(繁体字要) | 中程度 |
| 飲料 | 糖度、pH | 成分分析 | 高(糖度表示) | 中程度 |
| 冷凍食品 | 加熱条件、保存状態 | 放射線検査 | 高(温度帯明記) | 高リスク |
| 健康食品 | 機能性成分、効能表記 | 成分+放射線検査 | 非常に高い(効能NG) | 高リスク |
和菓子や飲料などの加工品は比較的対応が容易ですが、健康食品や冷凍食品は制度面・実務面ともに難易度が高く、事前準備が不可欠です。自社商品がどのカテゴリに該当するかを正確に分類し、それぞれに必要な検査や表示整備の内容を明確にしておきましょう。
規制対象地域・品目の指定と最新動向に注意
台湾は長年、原発事故の影響を受けた日本の一部地域からの食品に対し、特別な輸入規制や検査証明の提出を要求してきました。しかし、 2025年11月に福島・茨城・栃木・群馬・千葉の5県に対する特別規制は全面撤廃され、 現在は他国食品と同様にリスクベースの一般管理に移行しています。
その一方で、台湾は食品全般に対して セシウム134+137の合計100 Bq/kg以下という放射性物質基準を維持しており、 輸入者の判断や品目のリスクに応じて、 サンプリング検査や証明資料の提出を求められる場合があります。
特に水産物、生鮮農産品、乾物などは実務上チェック対象となりやすい傾向があります。
規制撤廃=「完全に書類が不要」という意味ではないため、 品目・製造地域・輸入者の運用をもとに、都度最新の条件を確認することが重要です。 誤った前提で出荷すると、通関遅延や再検査、保管費用の発生につながる恐れがあります。
初回輸出における判断の落とし穴と注意点
制度自体は全ての輸出者に共通ですが、 初回輸出では準備工数・確認項目が大幅に増えるのが実務上の特徴です。 以下に特に見落とされやすいポイントを整理します。
- 台湾向けラベル表示が初めての場合
事前に台湾側輸入者と校正確認が必要。翻訳誤り・原産地表記の不備は通関差し止めの主要因。 - 台湾側輸入者の食品業者登録(TFDA)が未完了
初回登録には数週間〜1か月程度かかることがあり、出荷スケジュールを圧迫。 - 放射性物質や成分分析に関する証明が準備されていない
検査の依頼から証明書の取得までに2〜4週間かかるケースもあり、特に新規品目で遅延が発生しやすい。
これらの準備が欠けていると、予定した納期に間に合わない恐れがあります。 「どの工程が初めてなのか」を洗い出し、必要日数を逆算したうえで計画することが、 初回輸出を成功させる最短ルートです。
台湾食品市場の制度や税制・需要構造を把握することで、長期的な輸出戦略を描けます。台湾貿易の基本情報については以下の記事をご覧ください。

台湾への食品輸出で実際に起きた現場トラブルとその対策
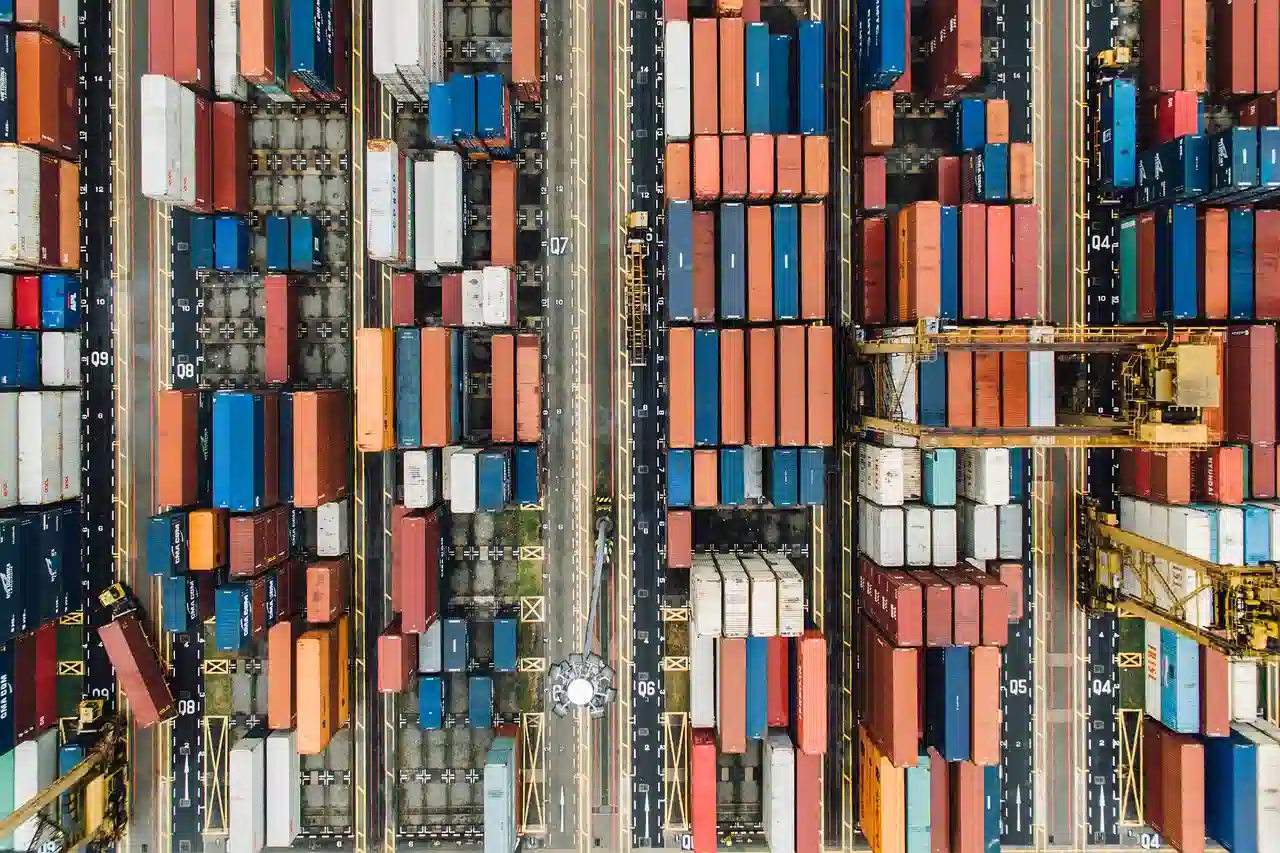
台湾への食品輸出では、制度を順守して書類を整えたつもりでも、現場では思わぬトラブルが発生することがあります。
本セクションでは、実際に起きたトラブル事例をもとに、輸出担当者が事前に備えておくべきポイントを整理します。
ラベル表示ミスによる通関保留
輸出時に最も多いトラブルが、ラベル不備による通関の保留や修正要求です。制度上は正しい内容でも、ラベル表示の形式や翻訳内容に不備があると、税関で差し戻される可能性があります。
以下は、実際によくあるラベル不備の例です。
- 商品名が日本語表記のままで繁体字に変換されていなかった
- アレルゲン情報が不足していた、または強調表記が不十分だった
- 原産地表示に都道府県名がなく、「日本」など曖昧な表記だった
- 含有量の単位(mg、mlなど)が台湾の基準と一致していなかった
このようなミスがあると、再印刷の手間に加え、通関遅延や保管費用の発生につながります。実際の現場では、修正と再印刷に1〜3週間を要するケースも報告されています。
検査書類の不備による再提出・再検査
書類が揃っていても、内容に形式的な不備があると再提出が求められることがあります。特に、放射性物質検査や成分分析に関する証明書は、以下の点で問題が発生しやすいです。
- 検査を実施した機関が台湾側で承認されていなかった
- 証明書の翻訳に誤記があり、内容が正確に伝わらなかった
- 記載された検査日が、実際の出荷日と一致していなかった
こうした不備がある場合、現地での検査再実施が必要になることもあり、7〜21日程度の納期遅延が発生する可能性があります。結果的に取引先からの信頼を損なうリスクもあるため、書類のダブルチェック体制が重要です。
輸入者登録の未対応で輸出が不可に
台湾では、輸入を担当する企業がTFDAに事前登録しておくことが義務付けられています。この登録が未完了だと、書類や商品がすべて揃っていても通関できず、輸出自体が不可能になるケースがあります。
とくに新規取引先との初回輸出では、次の点を必ず確認しましょう。
- 輸入者がTFDAへの登録申請を済ませているか
- 登録の有効期限が切れていないか
- 必要な更新手続きを完了しているかどうか
これらを確認せずに出荷を進めると、商品の返品や通関不可による損失が発生する恐れがあります。
事前に台湾側と登録番号や登録状態を共有することが、リスク回避につながります。
このようなトラブルは、書類や制度の知識だけでは防げない部分も多く、社内の手続きチェックリストや輸入者とのコミュニケーション体制の整備が鍵となります。
トラブルが発生した場合の影響は、納期だけでなく、販売機会や信用にも及ぶため、未然に防ぐ体制づくりが輸出実務の重要な要素となります。
台湾への食品輸出における輸入者との連携と通関成功の実務対応

台湾向けの食品輸出では、書類や検査の準備だけでなく、台湾側輸入者との連携体制が成功の可否を左右します。
輸入者がTFDAの登録を適切に完了しているか、ラベルの役割分担が明確かどうかといった事前のすり合わせが、通関時のトラブル回避に直結します。
このセクションでは、輸出元が把握すべき連携ポイントと、実務で使える交渉テンプレートを紹介します。
TFDA輸入者登録の確認方法と注意点
台湾側の輸入者は、TFDA(台湾食品薬物管理署)に対して、食品の種類ごとに事前登録を行う必要があります。
輸出元としては、出荷前に以下の項目について確実に確認しておくことが求められます。
- 登録番号が発行されているか(正式なTFDA番号)
- 登録された企業情報と連絡先が正しいか
- 登録の有効期限が切れていないか
これらを確認しないまま出荷を行うと、通関時に「輸入資格なし」と判断され、輸送コストをかけて送った商品が輸入不可となるリスクがあります。
とくに新規取引開始時は、輸入者登録の進捗状況をこまめに確認し、証憑の提示を依頼することが重要です。
ラベル・成分表示の責任分担を明確化する
ラベルの準備は輸出実務の中でも誤解が起きやすいポイントです。
誰が翻訳を行い、誰がチェックし、誰が印刷を担当するのかを曖昧にしたまま進めると、不備の責任が不明確なまま通関トラブルに発展することがあります。
実務上、以下のような分担が一般的ですが、取引ごとに役割の確認は不可欠です。
- ラベル翻訳
台湾側輸入者が担当するケースが多い - 校正・整合性のチェック
輸出元と輸入者の双方で実施するのが望ましい - 印刷・貼付
輸出元が行う場合、修正・再印刷のコストと日数を考慮する
また、翻訳ミスや規定違反によるラベル差し戻しが発生すると、印刷費用の再負担や納期遅延につながります。
事前にラベルのPDFや校正シートを共有し、最終版の合意を取ることで大きなトラブルを防ぐことができます。
台湾側取引先にメールで確認すべき主な内容
台湾への食品輸出をスムーズに進めるには、事前に台湾側取引先と重要事項をメールで共有しておくことが欠かせません。初回輸出や新規商品では、認識のズレが通関遅延やラベル修正につながるリスクがあります。
以下は、輸出前に確認・依頼しておくべき代表的な項目です。必要に応じて、自社商品の特性に合わせてカスタマイズしてください。
- 輸入者登録に関する確認
・TFDAへの輸入者登録が完了しているか
・登録番号の有無と正確な記載(半角英数字)
・登録の有効期限・更新状況
・登録名義(法人名)の表記と実在確認 - ラベル表示・パッケージに関する確認
・使用予定のラベル(繁体字)のドラフト確認希望
・成分表示・アレルゲン表示の翻訳支援可否
・栄養成分、保存方法、原産地表記の台湾基準への適合可否
・校正・チェックのスケジュール共有 - 成分証明・検査に関する情報共有
・成分分析や放射性物質検査が必要な場合の認識共有
・台湾側が求める証明形式(英文/中文/指定書式など)
・分析書類に関する注意点(翻訳・単位・発行日など) - 輸送・通関に向けた実務確認
・出荷予定時期と希望納期のすり合わせ
・輸送方法(海上/航空)と台湾側での受け入れ体制
・通関時の書類提出フローと連絡体制(輸入者 or 輸出者主導) - その他の調整事項
・商品説明書・販促物に関する翻訳方針
・台湾市場でのラベル表示に関する過去の対応事例
・新商品・改良品の場合の追加確認事項有無
これらの項目を事前に整理し、メールで明確に伝えておくことで、無用な手戻りや通関リスクを減らすことができます。特に初回輸出の場合は、準備に想定以上の時間がかかるため、早めの確認と合意形成がカギとなります。
台湾食品輸出における初回対応と継続時対応の違いとは
台湾への食品輸出における制度や規制は基本的に共通ですが、初回輸出と2回目以降では必要な準備・工数・コストに大きな差があります。初回は書類の整備や制度理解だけでなく、初回特有の登録や調整も発生するため、スケジュールと予算に余裕を持って対応する必要があります。
以下に、主な項目ごとの違いを表でまとめました。
初回と継続輸出の比較表
| 項目 | 初回輸出 | 継続輸出 |
|---|---|---|
| TFDA 食品業者登録(輸入者) | 必須(初回に登録。手続きに数週間〜1ヶ月程度かかる場合あり) | 不要(登録済/更新のみ) |
| 特定食品の品目登録 (健康食品・錠剤/カプセル・特殊用途食品など) | 必要(品目ごとの審査・資料提出) | 原則不要(同一商品・同一仕様で継続時) |
| ラベル確認・校正 | 必須(翻訳・法定表示の整備・印刷対応) | 軽微な修正で済むケースが多い |
| 放射性物質に関する検査・証明 | 必要となる場合あり (台湾基準100 Bq/kg以下の確認。輸入者の判断や品目リスクで提出要求) | 同一商品で安定取引の場合、省略されるケースあり ただし抜き取り検査の可能性は残る |
| 成分分析 | 新規品目では証明書取得が必要(翻訳精度重要) | 同一商品であれば省略可能 |
| 納期への影響 | 登録・検査・校正により2〜4週間以上の余裕を推奨 | 通常リードタイム(約7〜14日)で対応可能 |
台湾向け食品輸出では、初回輸出の検査・書類・登録の手間が大きく、準備工程に不安を感じる企業が多いです。食品輸出の基本的な流れについては以下の記事をご覧ください。

初回輸出では「想定外の工数と遅延」が起きやすい
初回対応において見落とされがちなポイントは、次のような点です。
- 台湾側でのTFDA登録が完了するまで出荷できない
- ラベル誤記や翻訳トラブルで再印刷となり、印刷納期が延びる
- 検査証明書の発行までに予想以上の時間がかかる
- 初めてのやり取りで台湾側の段取りと時間感覚が読めない
こうした理由から、初回輸出では「想定以上に手間がかかる」ことを前提に、納期やコストの計画を立てることが重要です。
あらかじめ工程を逆算し、スケジュールに2〜3週間のバッファを設けることで、社内外の混乱や遅延リスクを最小限に抑えることができます。
また、一度初回輸出を完了すれば、次回以降は多くの書類や工程が簡略化できるため、初回にどれだけ丁寧に対応しておくかが継続輸出の安定性にも直結します。
まとめ
台湾への食品輸出を進めるには、制度の理解だけでなく、自社の商品が実際に対応できるかを判断する実務的な視点が重要です。商品カテゴリごとの規制や検査、ラベル要件を整理し、必要な書類や表示の準備が整っているかを事前に確認することで、通関トラブルの多くは回避できます。
特に初回輸出では、登録・検査・翻訳などに想定以上の時間と手間がかかるため、スケジュールや予算には十分な余裕を持たせる必要があります。一度流れを作っておけば、継続輸出は格段にスムーズになります。
最終的な判断に迷う場合や、自社内で対応が難しいと感じる場面では、早めに専門家に相談することをおすすめします。














