高市早苗総理は2025年11月7日の国会答弁で、「(中国が)戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になり得る」と発言しました。この発言は従来の戦略的曖昧さを超えるもので、中国側は強く反発。
外交的緊張が高まる中、ビザや通関といった実務面への影響も懸念されています。特に、中国と取引を持つ日本企業では、出張や駐在、現地採用といった実務にどのような影響が及ぶのか、現場レベルでの懸念が高まっています。
本記事では、高市総理の対中発言をめぐる動向が、中国のビザ運用や企業の実務にどう波及する可能性があるのかを整理し、現地対応や代替戦略について実務的視点から解説します。
高市氏の対中発言と中国ビザ制度の関係を解説

日本国内の政治発言は、直接的に制度を変更するものではありませんが、外交関係を通じてビザや通商制度の「運用」に影響を及ぼすことがあります。
2025年11月の国会審議において、高市早苗総理は「(中国が)戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になり得る」と発言しました。これは、日米同盟に基づく安全保障観の表明としてなされたものであり、政府としての防衛方針を明確にする意図があったと見られますが、中国側は強く反発し、対日姿勢に硬化の兆しが出始めています。
こうした発言が即座に制度変更をもたらすわけではないものの、審査対応や現地行政における“空気の変化”として表れることで、企業の実務現場に摩擦が生じるリスクが高まります。
本セクションでは、現在の中国ビザ制度の基本構造と、今回の発言が触れている領域の違いを整理し、企業が判断する際の出発点を明確にします。
中国ビザ制度の現状(一次情報)
中国ビザ制度は用途ごとに複数のカテゴリーに分かれており、それぞれに発給条件と審査プロセスが決められています。特に商用(M)ビザや就労(Z)ビザは、日本企業にとって現地での事業継続に不可欠な制度であり、制度が変わらなくても「運用の揺らぎ」が生じるだけで企業の活動に影響が出ます。
以下は代表的なビザ区分の概要です。(審査期間は目安)
| ビザ種類 | 主な用途 | 発給条件 | 標準審査期間 |
|---|---|---|---|
| Mビザ | 商談・展示会出席 | 招聘状など必要 | 約4~7営業日 |
| Zビザ | 現地駐在・就労 | 労働許可証など | 約10営業日以上 |
| Sビザ | 家族帯同 | 戸籍証明・在職証明 | 約5~10営業日 |
| Lビザ | 観光 | 渡航目的に応じて要件あり(免除措置対象国あり) | 3~5営業日 |
※Lビザ(観光)は、国籍や期間により免除措置が適用される場合があります。短期滞在であっても目的・回数・現地活動内容によっては取得が必要になるため、常に最新の大使館・中国ビザセンターの案内を確認してください。
審査期間は平常時の一般的な水準であり、外交的な緊張や安全保障環境の変化によって、突発的な遅延や追加書類の要求が発生することがあります。特にMビザは、審査を担う地方の公安当局の判断によって基準が変わりやすく、申請者の業種・訪問先・滞在日数により対応が揺れるケースがあります。
今回の発言が触れている領域
高市総理の発言は、中国ビザ制度そのものを対象としたものではなく、対中外交・安全保障のスタンスを示した政治的メッセージです。現時点では、日中間のビザ発給ルールに公式な変更は確認されていません。
ただし、中国側が発言を政治的シグナルとして受け取った場合、制度改正ではなく「運用」を通じて調整する可能性があります。過去の対立局面でも、制度が変わらないまま審査の速度や要求内容が変化した事例があり、次のような影響が生じ得ます。
- 審査期間の長期化(とくにM・Zビザ)
- 追加書類の要求や照会の増加
- 特定業種・地域に対する非公式な審査強化
制度そのものに変更がなくても、在外公館の審査対応が遅れたり、地方公安局での書類差し戻しが増えたりすることは過去にも観測されています。企業は「制度が変わったか否か」だけで判断するのではなく、審査・運用の揺らぎをいち早く察知する視点が求められます。
高市総理の発言は制度を直接変えるものではないものの、運用レベルでの“揺らぎ”が発生しやすくなります。企業は公式発表だけでなく、審査現場での変化を早期に察知し、出張・駐在・通関のリスクに備える体制が求められます。
高市氏の発言が企業の中国ビザ実務に与える具体的影響とは?
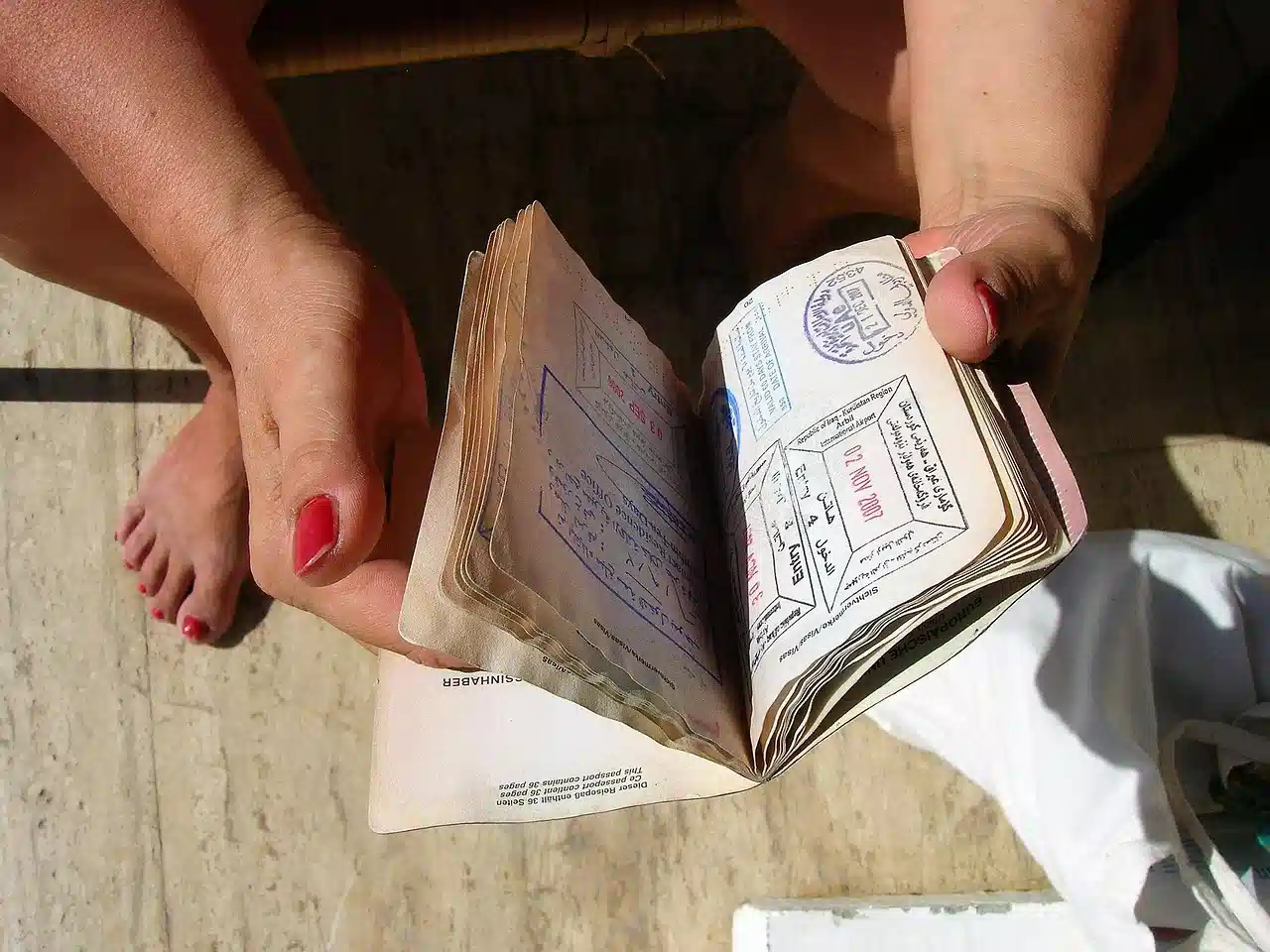
高市総理の発言そのものが中国ビザ制度や通関ルールを直接変更したわけではありません。しかし、外交的な緊張の高まりが審査運用や現地の行政対応に反映されることは過去にも見られました。制度は不変でも、手続きの速度や要求事項が変化することで実務負担は急増します。
こうした「空気の変化」は、出張計画・駐在管理・サプライチェーンに思わぬ形で影響するため、早期察知と備えが重要になります。
出張・展示会・商談 —— 発給遅延や追加照会の増加
商用(M)ビザの申請では、招聘状の内容確認や追加照会により、取得までの期間が想定以上に伸びるケースが散見されます。業種・訪問先・滞在日数といった条件に応じて審査が細かくなり、省ごとの公安局によって判断が異なることもあります。
特に「Canton Fair」や「中国国際輸入博覧会(CIIE)」など、政策的に注目されやすい展示会では、審査官がより慎重な対応を取る傾向があり、質問の細分化や書類再提出が求められるケースが報告されています。こうしたリスクに備え、以下の対策が有効です。
- 招待状を早期に取得し、申請スケジュールを前倒しする
- 渡航者を単一担当者に依存させず、複数名でカバーする
- 現地代理店・パートナーを活用し、手続きや現地対応を分散する
駐在員・現地採用への影響
就労ビザ(Zビザ)や在留許可の更新では、近年の安全保障関連法制強化を背景に、事業内容や業務範囲についてより詳細な説明を求められる事例があります。特にインフラ、通信、医療、先端製造など、戦略性の高い分野に携わる企業は審査期間が長くなる可能性があり、更新タイミングの遅れが組織運営に影響することも考えられます。
家族帯同ビザ(Sビザ)においても、子どもの就学先や居住証明などがより厳密に確認されるケースがあります。住居契約・教育サポート・保険といった生活面の手当ても、単なる福利厚生ではなく「リスク管理の一部」と捉える必要があります。
サプライチェーンの“見えない遅延”
ビザ発給や更新が遅れると、現地での検品、仕様調整、試作評価といった工程が後倒しになり、結果として納期遅延や品質トラブルが発生することがあります。こうした影響は直接的に「ビザ問題」とは認識されにくく、社内報告では要因が分断されがちです。
さらに、通関・検査・輸送においても、臨時的な追加検査や手続き確認が行われることで、物流全体のリードタイムが伸びる場合があります。中国市場に依存度が高い企業ほど、以下の対処を早めに検討する必要があります。
- 現地プロセスの進行管理をデジタル化し、遅延の兆候を早期把握する
- 代替調達先や並行ロジスティクスを確保し、単一ルート依存を避ける
- 契約上の納期、検収条件、不可抗力条項を明文化し、責任分担を明確化する
中国でのビジネス継続性を確保するには、サプライチェーン攻撃への備えも重要です。サプライチェーン攻撃については以下の記事をご覧ください。
指定された投稿が見つかりません。
中国がビザ運用を変えた過去3つの事例

高市総理の発言が企業活動にどう影響する可能性があるのかを判断するには、過去に中国が外交・保健・安全保障上の理由で入国管理を調整した事例を参照することが有効です。制度そのものを改正しなくても、審査の厳格化や追加書類の要求、行政裁量の拡大を通じて実務に影響が出たケースは複数存在します。
以下では、過去15年間で代表的な3つの事例を取り上げ、企業活動にどのような波及が生じたのかを整理します。
北京五輪(2008):政治イベントに伴う一時的な審査強化
2008年の北京五輪前後、中国当局は治安維持と国際イメージ保護を目的に外国人の入国管理を一時的に厳格化しました。Mビザ(商用)やLビザ(観光)では、発給対象業種の制限や追加確認が行われ、商談・展示会参加・短期出張の実務に影響が出た企業もありました。
建設、インフラ、メディア関連などの分野では審査項目が増え、当局から追加書類や照会が求められるケースも確認されています。
このような「大規模政治イベントに伴う管理強化」は、中国特有の対応として過去にも観測されており、現在の高市総理発言に対する反応を評価するうえで、比較対象となり得ます。
ゼロコロナ(2020–2023):健康安全に基づく包括的規制
新型コロナ対策により、中国は2020年から約3年間にわたり、ほぼすべての外国人に対する新規入国を停止し、既存のビザや在留許可も一時的に無効化しました。結果として、駐在員の交代・帰任が極めて困難となり、現地法人の組織運営や人材配置に大きな影響が出ました。
物流面でも、検疫や通関審査が強化され、納期遅延や輸送コストの上昇が長期化しました。健康を理由にした措置は企業側も受け入れやすいものの、実際にはサプライチェーンと人材面の双方で最も深いダメージを残した事例といえます。
尖閣・THAAD(2010 / 2016):外交対立に伴う“見えない摩擦”
2010年の尖閣諸島衝突、2016年の韓国THAAD配備を巡る対立では、中国は公式な制度改定を行わず、審査運用を通じた圧力を選択しました。入国管理や税関での手続きが不透明に長引き、追加確認や審査保留が増えたことで、出張者の渡航計画や輸出入工程に影響が生じました。
こうした対応は「制度変更がないため表面化しにくい」が、実務上は確実に摩擦を発生させる点に特徴があります。外交的緊張が高まる局面では、法令の改正よりも“行政裁量の変化”が先に現れることが多く、高市総理の対中発言に対する反応を考えるうえでも念頭に置く必要があります。
高市氏の発言後の中国ビザ対応に備える企業の実務対策

政治発言や外交的緊張は、制度変更よりも先に「運用」へ影響します。中国とのビジネスに深く関与する企業ほど、発給遅延・突然の不承認・通関の滞留といった“見えない摩擦”に備える必要があります。重要なのは、問題が発生した後に対応するのではなく、平時に代替ルートと判断基準を組み込んだ体制を整えておくことです。
出張・在留が詰まった際のオペレーション
MビザやZビザの審査が長期化、あるいは一時的に制限される可能性に備え、「現地で人が動けない状態でも業務が継続する設計」が必要です。単なる担当者の代替ではなく、組織レベルでボトルネックを切り離すイメージです。
有効な整備例は以下の通りです。
- 現地責任者への権限委譲
決裁権・支払権限・契約締結範囲を明文化 - 法人招待状(PUレター)の発行体制
書類保管・提出プロセスを標準化し、担当者不在でも可動 - 代替派遣ルート
第三国経由の渡航、複数の申請窓口・申請者を確保
併せて、駐在員本人・家族が急な一時帰国に直面した場合に備え、住居・教育・保険などの契約を短期解約可能・柔軟契約にすることで、想定外の出費や長期不在に伴う混乱を抑制できます。
展示会・商談の代替
中国国内の展示会や商談が機能しない局面でも、販売接点を分散しておけば需要を取りこぼしません。オンライン・地域代替・代理店の三層で捉えるのが基本です。
- オンライン商流
Alibaba, JD.comなど越境EC、B2Bプラットフォームを併用 - 地域代替
タイ・ベトナム・インドネシアなどASEAN圏の商談会・展示会へシフト - 現地パートナー委託
中国国内の代理店に顧客接点と受発注を任せ、渡航依存を下げる
特にASEANは、調達(部材)と販売(顧客)を同時に移す発想と整合性が高く、近年は“ポートフォリオ分散”として活用する企業が増えています。
サプライチェーンのバックアップ
中国への製造・調達依存が高いほど、摩擦の発生は物流・検査・サプライヤー交渉など広い範囲へ波及します。バックアップは「移転」ではなく平時からの冗長性です。
- 東南アジアの部品供給網
ベトナム・タイ・インドでの部分工程・補完製造 - メキシコ・北米向けライン
米中摩擦の影響を回避する“対米輸出の裏口” - 在庫・リードタイム調整
拠点間リードの計算を見直し、最低在庫を増やす
さらに、契約面での防御力を高めることが重要です。
不可抗力条項(force majeure)や遅延時の責任分担条項を整備し、「遅れが発生した場合の損失を誰が負うのか」を明確化しておけば、サプライヤーや顧客との摩擦を最小化できます。
行政裁量による遅延は、明文化されない分だけ後処理が難しいため、契約に逃げ道を用意すること自体が最大の防御です。
高市氏の発言が中国ビザ制度へ与える影響と判断ポイント

今後、制度自体の変更やビザ審査運用の厳格化が発生するかどうかは、日本・中国双方の外交判断、国内政治の安定度、経済情勢など複数の要因に左右されます。重要なのは、発表された変更に反応するのではなく、「制度が変わる前の揺らぎ」を捉えることです。行政対応の微妙な変化は、公式アナウンスより先に実務へ表れます。
以下は、企業が半年〜1年先を見据えて把握すべき判断軸です。
| 判断軸 | チェックポイント |
|---|---|
| 外交関係 | 日中首脳会談・外相会談の頻度とトーン、米中関係の緊張度(台湾問題・制裁措置の有無) |
| 中国国内事情 | GDP成長率、都市部失業率、不動産市場の安定性、社会統制と治安状況 |
| 政策シグナル | 公安・外交部の発言、地方政府の行政通達、ビザセンターの審査基準や受付説明の変更 |
制度の条文よりも、運用面に現れる“非公式な変化”をどれだけ早く把握できるかが実務上は決定的です。現場では以下の情報ルートを常時確認しておく体制が有効です。
- JETRO・在中国日本大使館が発信する現地情勢レポート
- 商工会議所(CCBJ、日中経済協会等)が共有する実務事例
- 中国大使館・ビザセンターの通知・FAQ更新・提出要件の変更
特に、外交イベントの発言や制裁の動向 → 中国政府の政治的反応 → ビザ・通関などの行政裁量という流れは過去の事例と一貫性があります。それらを個別に眺めるのではなく、「自社のどの機能に最初に影響が来るか」を結び付けて考える視点が、中長期的なリスク管理に直結します。
中国輸出の制度や主要な品目についてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。基本的な仕組みを押さえておくことは、制度変更への備えにもつながります。

まとめ
現時点で、高市早苗氏の発言が中国のビザ制度に直接的な変更を与えている事実は確認されていません。ただし、企業の実務レベルでは審査や対応の「空気」が変わることで、出張や駐在、契約に影響を及ぼす可能性があります。ビジネスを継続的に運営していくためには、代替調達先の確保や現地オペレーションの強化が鍵となります。
なお、中国との関係性が複雑化する中で、企業の状況によって最適な対応策は異なります。具体的な影響を判断するためにも、専門家に一度相談してみることをおすすめします。














