米国の関税政策が大きく揺れ動き、各国がサプライチェーン再編を急ぐなか、メキシコは“北米の新たな製造・物流ハブ”として世界的な注目を浴びています。アメリカ市場への近接性に加え、USMCA・日墨EPAを含む広範なFTAネットワーク、そして国内産業を守りつつ投資を引き寄せる戦略的な通商政策が重なり、メキシコは多国籍企業にとって不可欠な拠点へと変化しつつあります。
その中で重要性が急上昇しているのが、メキシコの関税制度と貿易コンプライアンスです。2025年以降の政策変更は、単なる税率の話ではなく、企業のコスト構造、調達戦略、規制遵守体制に直結する“経営課題”となっています。
本記事では、2025年11月時点の最新制度を踏まえ、TIGIE改革・IMMEX/PROSEC・デジタル通関要件など、日系企業が押さえるべき実務ポイントを体系的に整理します。
メキシコの関税制度の基本構造とは?

メキシコの関税制度は、TIGIE(一般輸出入税法)をベースに、WTOルールとUSMCA・日墨EPAなどのFTAネットワークによって構成されており、輸入時に発生する税金や手数料を通じて、国内産業の保護と財政収入の確保を目的としています。
1995年のWTO(世界貿易機関)加盟以降、メキシコの関税政策は多国間ルールに沿いつつ、近年は非FTA諸国に対する高関税と、FTAパートナーに対する優遇税率という「二層構造」がより鮮明になっています。
関税制度の全体像を理解するうえで、まずは次の三点を押さえておくと整理しやすくなります。
- 関税の種類(従価税・従量税・混合税)
- TIGIE一般税率とFTA・追加関税を含む税率水準
- 関税の算定方法と、税関・経済省・デジタル通関システムの役割
関税の種類と特徴
メキシコでは、TIGIEにもとづき次の3種類の関税形態が採用されています。
- 従価税
輸入品のCIF価格(運賃・保険料込み)に対して一定の割合で課税される方式で、メキシコの輸入関税の大半を占める最も一般的な税目です。TIGIE上の一般税率も、この従価税として定められています。 - 従量税
重量や数量など、物理的な単位あたりで課税される方式で、一部の農産品や特定品目に限定的に適用されます。価格変動が大きい品目に対し、一定の保護効果を発揮するために利用されます。 - 混合税
従価税と従量税を組み合わせた方式で、制度上は規定されていますが、実務では適用例は限られています。
一般的には、機械部品や自動車部品などの工業製品には従価税が適用され、一部農産品などで従量税が用いられます。ここに、後述する追加関税やFTA優遇税率が上乗せ・上書きされるイメージです。
平均関税率と品目別傾向
メキシコのTIGIEにもとづく一般関税率は、国際統計上おおむね1桁台前半(6〜7%程度)の水準とされており、工業製品については比較的低めに設定されています。一方、農産品など一部品目では、依然として2桁台の税率が適用されるケースもあります。
さらに2025年時点では、TIGIE改革により非FTA諸国(とくに中国など)からの輸入品に対して15〜50%といった高率の関税が上乗せされる一方、USMCAや日墨EPAなどの協定を満たすFTAパートナーからの輸入は、無税または低税率での輸入が可能です。
たとえば、日墨経済連携協定(EPA)の原産地規則を満たした日本製の多くの工業製品は、メキシコ向け輸出時に関税が撤廃または大幅に軽減されます。一方、同じ品目でも非FTA諸国から輸入した場合には、TIGIE一般税率に加え、高い追加関税が課される可能性があります。
関税の算定方法と手続き
メキシコにおける関税額の算出は、基本的には次の要素にもとづいて行われます。
- 関税課税対象となる価格(通常はCIF価格)
- 適用される税率(TIGIE一般税率、追加関税、またはFTA優遇税率)
- 関税以外の賦課(付加価値税、特別税、税関手数料など)
制度の実務運用は、経済省(SE)および税関庁(SAT)が所管しており、輸入者は、HSコード(TIGIE分類)の適切な特定、原産地証明書の取得・管理に加え、近年はVUCEM(単一窓口システム)を通じた電子申告や、バリュエーション申告などのデジタル要件にも対応する必要があります。
このように、メキシコの関税制度は、TIGIEによる基本税率、USMCA・日墨EPAなどのFTA優遇税率、非FTA諸国向けの追加関税、そしてデジタル通関ルールが重なり合う多層構造となっており、「どの国から・どの原産地で・どの制度を使うか」によって実際の税負担が大きく変わる点が特徴です。

メキシコの関税が注目される背景

近年、世界の貿易構造は激変しており、その中心に位置づけられる国としてメキシコが急速に注目を集めています。
これは単なる地理的条件だけでなく、地政学的リスク回避の観点、各国との関税政策の違い、そしてメキシコ政府による積極的な制度支援といった複合的な要因が絡み合っているためです。
米中対立とサプライチェーンの地殻変動
中国に依存した製造・物流体制は、米中の関税対立や安全保障リスクにより、今や大きな不確実性を抱えるようになっています。これを受けて多くのグローバル企業が実行に移しているのが、「チャイナ+1」戦略や「ニアショアリング(近隣国への生産移管)」です。
とりわけ米国市場を主戦場とする企業にとって、メキシコはその代替先として圧倒的に有利な選択肢とされています。
メキシコの地理的・物流的なアドバンテージ
- 米国と国境を接し、陸路での輸送が可能(24〜72時間以内に主要都市に到達)
- メキシコ湾と太平洋の両岸に港湾を持ち、アジアおよび欧州との輸送にも柔軟に対応
- 米国とタイムゾーンが重なるため、リアルタイムでの調達・製造・販売連携が容易
これらの条件が、単なる「近さ」ではなく、効率性と低リスクなサプライチェーンの構築可能性という点で評価されているのです。
グローバルなFTAネットワークを背景にした柔軟な通商戦略
メキシコは、世界最多クラスの自由貿易協定(FTA)を締結している国の一つであり、その数は60か国以上にのぼります。日本企業にとって重要な協定は以下の通りです。
①USMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)
北米市場への無関税アクセスが可能。自動車産業を中心に、多くの企業がこの制度を前提にメキシコでの生産体制を構築しています。
USMCAについては以下の記事で詳しく解説しています。

②日墨経済連携協定(EPA)
工業製品、部品、化学製品の大半が関税免除対象であり、日本からの部材供給とメキシコでの最終製品化を支援する強力な仕組みです。
③EU・メキシコFTA
欧州市場との安定的な貿易基盤を提供し、メキシコをハブとして三極間(日本・北米・欧州)戦略を描くことが可能になります。
これらの協定を適切に組み合わせることで、関税コストを抑えつつ、複数市場への同時展開という高度な通商戦略が実現可能となります。
メキシコ政府による産業誘致政策の本気度
メキシコ政府は、外資企業の誘致を国家戦略の一環として位置づけており、以下のような制度的支援を整備しています。
- IMMEX制度
輸出向けの製造企業に対して、原材料・部品の一時的な関税免除を提供 - PROSEC制度
国内販売にも対応できる関税優遇スキームで、自動車・電機・化学品分野に適用 - インフラ開発と工業団地整備
とくに中部・北部地域で日系企業向けの工業団地が急速に整備されており、物流効率と人材確保を両立
さらに税制インセンティブ(法人税減免、機械設備投資控除)や、デジタル通関の整備など、進出後の運用負担軽減にも力を入れています。
実際の進出企業と業種の広がり
近年では、トヨタ自動車やパナソニック、村田製作所をはじめとする大手日系企業が、メキシコでの新工場開設や既存拠点の拡張を進めています。その波は自動車関連にとどまらず、医療機器、電子部品、化粧品、食品加工など多様な業種に及んでいます。
メキシコの関税が注目される背景

近年、世界の貿易構造は大きな転換期を迎えており、その中心に位置づけられているのがメキシコです。特に2025年は、米国の普遍的関税・デミニミス廃止、メキシコのTIGIE改革など、大規模な制度変更が相次ぎ、北米サプライチェーン全体の設計が根底から見直されています。
注目度の高まりは地理的優位性だけでなく、地政学リスク回避、国別関税政策の分断、メキシコ政府の積極的な産業誘致政策が複合的に作用しているためです。結果として、メキシコは「単なる製造拠点」から、北米市場に向けた関税最適化の戦略拠点として再評価されています。
米中対立とサプライチェーンの地殻変動
米中対立の長期化により、中国依存の調達・生産モデルは大きな不確実性を抱えるようになりました。米国はIEEPAに基づく普遍的10%関税やセクション232の強化など、保護主義に舵を切っており、中国由来の部品・原材料を含むサプライチェーンには高いコスト負担が生じています。
これにより加速しているのが、「チャイナ+1」や「ニアショアリング」の動きです。特に米国市場向けビジネスにおいて、メキシコは「地理的近接性 × FTA活用による関税ゼロ」という圧倒的優位性を持つ代替候補として選ばれています。
メキシコの地理的・物流的アドバンテージ
- 米国と陸路で接し、主要都市へ24〜72時間で輸送可能
- 太平洋・大西洋の双方に港湾を持ち、アジア・欧州との物流にも対応
- 北米とタイムゾーンが近く、リアルタイムでの生産・調達連携が可能
こうした特徴は、単なる「距離的近さ」ではなく、リードタイムの短縮、在庫圧縮、物流リスク低減といった経営メリットにつながる点が高く評価されています。
グローバルなFTAネットワークが生む通商戦略の自由度
メキシコは世界最多クラスとなる60か国以上とのFTA・経済連携協定を持つ国であり、そのネットワークは企業の関税コスト最適化に大きく貢献します。日本企業にとって重要な協定は以下の通りです。
- USMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)
北米市場への無関税アクセスを可能にする最重要協定。自動車産業はこの協定のROO(原産地規則)を前提にメキシコ拠点を構築しています。 - 日墨経済連携協定(EPA)
日本からの工業製品・部品の大半が関税免除となり、日本→メキシコ→米国の三段階サプライチェーン構築を強力に後押しします。 - EU・メキシコFTA
欧州市場との関税メリットを確保し、メキシコを起点に日・米・欧の三極展開が可能になります。
これらの協定を組み合わせることで、複数市場へ同時に展開しつつ関税負担を最小化する高度な通商戦略が実現します。
メキシコ政府による積極的な産業誘致政策
メキシコ政府は外資誘致を国家戦略と位置づけ、以下のような制度的支援を整備しています。
- IMMEX制度
輸出向け製造企業に対し、原材料・部品の一時輸入時の関税を免除する制度。(※2024〜2025年の改革で監視強化・対象品目の絞り込みあり) - PROSEC制度
国内販売向けにも適用可能な関税優遇制度で、自動車・電機・化学品など戦略セクターを中心に活用されています。 - インフラ開発・工業団地整備
中部・北部を中心に工業団地が急速に拡充。電力・物流ネットワークへの投資も進み、日系企業の進出基盤が強化されています。
加えて、税制インセンティブ(固定資産投資の即時償却など)やデジタル通関の整備が加速しており、進出後の運用負担軽減にもつながっています。
進出企業の広がりと産業多様化
トヨタ、パナソニック、村田製作所などの日系大手だけでなく、近年は医療機器・電子部品・化粧品・食品加工など幅広い業種で進出が進んでいます。背景にあるのは、米国市場向けに「関税ゼロ+短納期」で製品供給できるという競争優位です。
「関税戦略の再設計」としてのメキシコ進出
従来は中国など低コスト国の調達が優先されていましたが、2025年の国際環境では、調達コストだけでなく、輸出時の関税・物流リスク・規制リスクが企業戦略の中核要素となっています。
メキシコはこれらすべての要素を高いレベルで満たし、企業が「調達・生産・輸出」を最適化するための戦略拠点として、関税戦略の再設計における重要な選択肢となっています。
特に注目されるのは、アメリカ市場向け製品を「関税ゼロ+短納期」で供給できるという競争優位です。これは、他の生産国では容易に得られないメリットとなっています。
「関税戦略の再設計」としてのメキシコ進出
従来は中国などの低コスト国からの調達が中心でしたが、現在では「調達コスト」だけでなく、「輸出時の関税コスト」や「サプライチェーンのリスク耐性」が重要な評価軸となっています。
メキシコは、これらの要素すべてにおいて高いスコアを持ち、「調達・生産・輸出」の最適化を目指す企業にとって、関税戦略を抜本的に再設計する上での中核的な拠点といえるでしょう。
メキシコの関税の最新動向
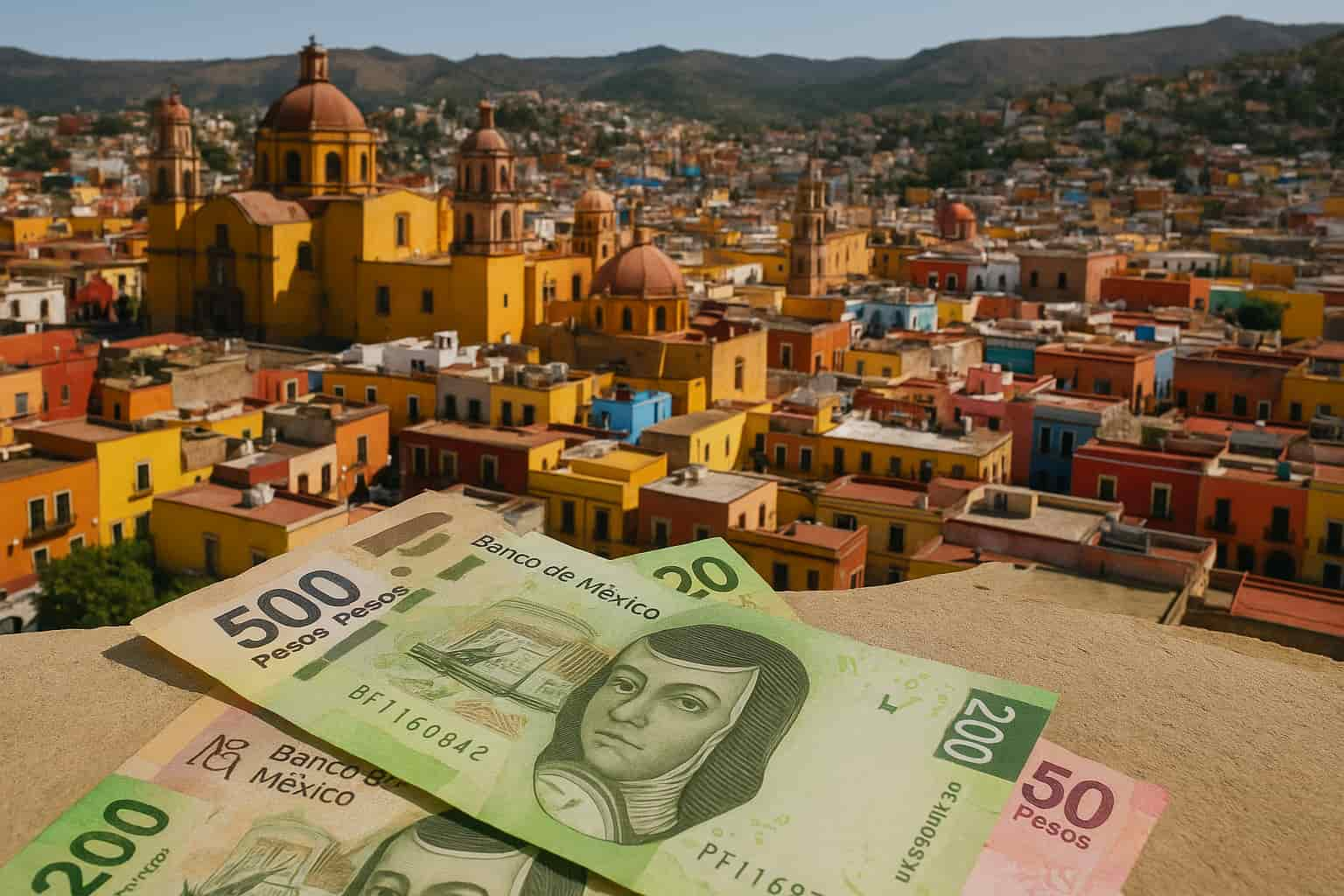
2024〜2025年にかけて、メキシコの関税制度は大きな転換期を迎えています。背景には、国内産業の強化や特定国への依存見直しがあり、政府は関税率や通関制度の見直しを段階的に進めています。
これらの変更は、日本企業のコスト・実務プロセス・調達戦略に直接影響する点で非常に重要です。
2024年の主な改正ポイント
2024年は、メキシコの関税制度が大きく見直された年でした。政府は輸入依存の高まりに歯止めをかけるため、追加関税の導入・関税分類の厳格化など、国内産業を保護する方向で政策を強化しています。
- 追加関税の導入(2024年4月)
鉄鋼・繊維・革製品・プラスチック・化学品など352品目に対して、5〜50%の追加関税が新設されました。中国や東南アジアからの安価な輸入が急増している分野を中心に、国内メーカー保護が目的です。
特に中小企業が多い分野では影響が大きく、「国内産業の空洞化防止」が改正の主要テーマとなっています。 - 繊維製品への特別保護(2024年12月予定)
繊維・アパレル製品には最大35%、原材料には15%の関税が新設予定です。FTA未締結国からの輸入を抑えることで、国内縫製業の保護を狙っています。
この改正により、日墨EPAなど既存のFTAを活用するメリットがさらに高まります。 - HSコード再分類と税関監査の強化
HSコード誤用による関税軽減が多発していたことから、2024年にTarifa(関税分類)が改訂され、分類基準が厳格化されました。
税関監査も強化され、2024年前半の監査件数は前年同期比150%増。輸入申告の精度が従来以上に求められています。
2025年に向けた制度動向と新たな課題
2025年は、通関のデジタル化と、環境・安全保障分野との制度連携が進む年となります。制度は「単なる課税」から「包括的な規制枠組み」へ進化しつつあります。
- 電子通関システム「VUCEM」の信頼性強化
2025年2月にVUCEMで大規模障害が発生し、全国の通関が停止。政府は以下の改善策を公表しています。
電子化が進む中、申告内容には高い透明性と正確性が求められます。- AIによるHSコード自動分類
- 電子署名の完全義務化
- 書類提出前のエラーチェック機能
- 非自動輸入ライセンス制度の適用拡大
安全保障・環境保護の観点から、2025年には特定品目に非自動ライセンス制度(事前許可制)が拡大導入されます。
こちらは事前審査が必要となり、リードタイム増加が避けられません。
対象分野は以下の通りです。- 半導体・電子部品
- 医療機器・化学薬品
- エネルギー関連設備
- 技術・環境認証の通関要件化
従来は任意だったRoHS、ISO、COFEPRIS登録などが、事実上の通関条件として扱われる動きが強まっています。- 電機・電子製品(電磁波・有害物質規制)
- 自動車部品(安全・環境基準)
- 医薬品・食品(品質・衛生規制)
関税政策は「安全・環境・サステナビリティ重視」への移行が明確です。
日本企業への影響と必要な対応
メキシコの制度改正は、日本企業の実務に次のような影響を及ぼします。
- 輸入コストの上昇
追加関税により原価計算の見直しが必須に。 - 通関業務の高度化
VUCEM対応や分類精度向上など、専門実務負担が増加。 - 認証・許可の追加負担
技術・衛生基準への適合が通関前提になるケースが増加。 - サプライチェーンの再検討
FTA活用、調達先切り替え、現地生産比率の拡大など戦略見直しが重要。
2024〜2025年のメキシコの関税制度は、制度対応・実務プロセス・調達戦略の全面見直しが必要となる転換点です。
日本企業は制度変更を「知識」として捉えるだけでは不十分で、早期の行動計画への落とし込みが不可欠です。
352品目を対象に5〜50%の追加関税が導入されたほか、HSコードの分類見直し、電子通関システム「VUCEM」の強化、非自動輸入ライセンス制度の拡大といった制度改正が進んでいます。
日本企業が知っておくべきメキシコの関税リスクと注意点
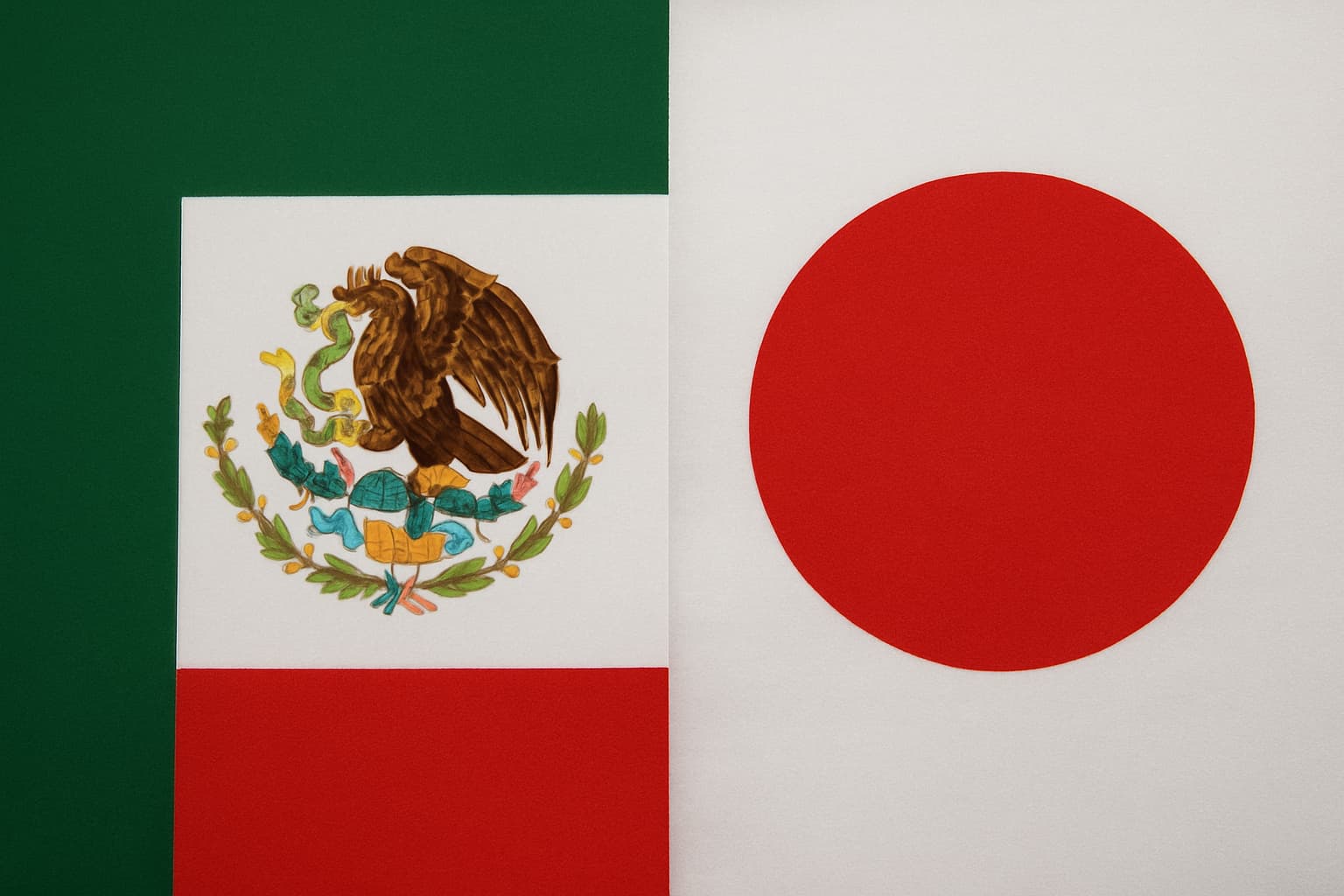
メキシコ市場に参入する、あるいはすでに取引を行っている日本企業にとって、関税制度はコストだけでなく事業全体の安定性にも影響する重要な要素です。
制度は一見シンプルに見えても、実際の運用には多くのリスクが潜んでおり、対策を講じないまま進出すると、想定外の追加コストや通関遅延、最悪の場合は取引停止につながることもあります。
以下では、日本企業が特に注意すべき関税リスクと、その対策をわかりやすく整理します。
主な関税関連リスク
- HSコードの誤分類
製品の分類が誤っていると、適切でない税率が適用され、追徴課税や罰金の対象となります。メキシコ税関では分類監査が厳格に行われており、正確な判断が不可欠です。 - 原産地証明書の不備
日墨EPA・USMCAなどのFTAを利用するためには、正しい形式の原産地証明書が必要です。記載漏れや形式の誤り、提出遅れがあると無税措置が否認されます。 - 関税評価の誤り
輸入価格に含めるべき費用(運賃・保険料・ライセンス料など)を適切に反映しないと、税関で評価修正が入り、追加課税の対象となります。 - VUCEM対応の不備
電子通関システム「VUCEM」に不慣れなまま申告すると、送信エラー・書類不備が発生し、通関遅延につながります。 - 必要な許認可の取得漏れ
医療機器・食品・電気製品などには、NOM規格・COFEPRISといった認証が必須です。未取得の場合、貨物が保留・拒否されるリスクがあります。
実際に起きた日本企業の失敗事例
- 電機部品メーカーA社
他国で使用していたHSコードを流用し誤分類。差額関税に加え、15万ペソの罰金が発生。 - 医療機器企業B社
使用していた原産地証明書が旧書式で、FTAが適用されず、1年分の輸入関税が全額課税に。 - 食品関連商社C社
NOM規格取得を失念し、税関で貨物が45日間保留。保管料・検査費用が追加発生し、納品遅延による取引トラブルに発展。
日本企業が講じるべき具体的な対策
- 分類と評価の精度向上
現地通関士や専門家と連携し、HSコードを正しく分類。輸出入価格の算定ルールを社内で明確化し、マニュアル化しておきましょう。 - FTA運用体制の整備
原産地証明書の取得・管理フローを標準化し、書式の更新・署名権限・有効期限などをデジタルで一元管理する仕組みを整備します。 - 非関税規制への対応
製品ごとに必要な認証(NOM、COFEPRISなど)を事前に確認し、認証取得スケジュールを輸入計画と連動させて管理します。 - VUCEM利用の社内体制整備
電子通関に精通した担当者を配置または育成し、外部通関業者とも連携しながら、事前入力・添付書類の精度を確保します。
これらの対策を継続的に行うことで、関税トラブルの未然防止だけでなく、通関処理の効率化や現地での信頼向上にもつながります。
日本企業がメキシコ市場で安定的に事業を展開するには、これらのポイントを戦略的に整えることが不可欠です。
メキシコの関税を有利に活用する方法

メキシコとの貿易では、関税リスクを避けるだけでは不十分です。むしろ、制度を積極的に“使いこなす”ことが、コスト削減や競争力強化のカギになります。
なかでも、日本企業が押さえておくべき重要制度が FTA(自由貿易協定) と IMMEX制度 です。これらを適切に組み合わせることで、関税負担を最小化し、柔軟な生産体制を構築できます。
メキシコが締結するFTAを活用する
メキシコは60か国以上とFTAを締結しており、世界でも有数の自由貿易ネットワークを持つ国です。日本企業が特に活用しやすいFTAは次のとおりです。
- 日墨経済連携協定(EPA)
日本から輸出される多くの工業製品が無税または段階的に関税撤廃。部品単位でも適用可能。 - USMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)
メキシコで生産した製品を米国に輸出する場合に有効。原産地規則を満たすことで無税取引が可能。 - EU・メキシコFTA
欧州向けビジネスで、メキシコを経由した無税輸出ルートを構築できる可能性がある。
FTA活用のポイント
- 原産地証明書(Form J・USMCA認定証など)の管理体制を整える
- 原材料や部品の供給元が協定対象国に該当するかを確認
- HSコードの整合性と技術仕様が原産地規則と一致しているか精査
- 証憑の更新・管理ルールを社内で標準化
FTAは「対象国同士の貿易であれば使える」という単純なものではなく、原産性の証明・証憑管理・定期更新といった細かな実務対応が不可欠です。
IMMEX制度とは何か? その仕組みと活用法
IMMEX(Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación)制度は、外資系製造業向けに設計されたメキシコ独自の輸出促進スキームです。原材料・部品・設備を「関税ゼロ」で一時輸入し、加工後に輸出することができる制度です。
IMMEX制度の基本的な仕組み
- 対象企業
メキシコ国内で加工・組立などを行い、完成品を海外に輸出する企業。 - 一時輸入の特典
原材料や機械設備を関税ゼロで輸入可能(一定期間内に再輸出が必要)。 - 条件
売上の一定割合以上を輸出に充てること、VUCEMでの厳格な記録管理、生産プロセスの申告などが義務。
IMMEXを活用するメリット
- 原材料段階での関税をゼロにでき、生産コストを大幅削減
- 設備投資の負担を軽減
- 柔軟なサプライチェーン構築が可能で、JIT(ジャストインタイム)生産にも対応しやすい
IMMEX利用時の注意点
- 一時輸入品は指定期間内に輸出、または適切な手続きを行う必要あり
- 管理台帳(Anexo 24)や在庫記録をVUCEMで提出する義務
- 規定違反があると、免除されていた関税・税金が遡って課税されるリスク
制度を組み合わせた最適戦略
先進企業の多くは、FTAとIMMEX制度を同時に活用し、以下のような流れで関税メリットを最大化しています。
- 日本から部材を IMMEX制度で一時輸入(関税ゼロ)
- メキシコで加工・組立
- 完成品を USMCAの要件を満たして米国へ無税輸出
このように、「調達 → 加工 → 販売」までを制度と連動させて設計することが、コスト最適化と関税管理の両立につながります。
まとめ
本記事では、メキシコの関税制度の基本から最新動向、実務への影響、そして戦略的な活用法までを幅広く解説しました。
変化の激しいグローバル経済において、関税制度の理解はコスト管理・リスク回避・競争力強化のために欠かせない要素です。
また、制度運用は時に複雑で、現地の実務や法令改正にも精通しておく必要があります。メキシコとの貿易を成功させるためには、自社内だけでの対応に限界がある場合もあります。
そのため、関税制度に不安がある場合は、専門家に一度相談してみることをおすすめします。














