日本人の食卓で古くから親しまれてきたウナギ。特に夏の風物詩である「土用の丑の日」には欠かせない存在として、多くの人に愛されてきました。しかし今、この身近な食材が国際的な規制対象となるかもしれないという現実に直面しています。
2025年11月、ウズベキスタンで開幕したワシントン条約の第20回締約国会議(CoP20)では、ヨーロッパ連合(EU)などが提案する「ウナギ属全種の附属書Ⅱへの掲載」が正式に議題となりました。もしこの提案が採択されれば、ニホンウナギを含むすべてのウナギ製品の国際取引において、輸出許可書が義務化されることになります。
日本政府はこの提案に反対の立場を示していますが、背景には資源の減少、密輸の横行、評価基準の食い違いなど、さまざまな論点が複雑に絡み合っています。
本記事では、今回の規制提案が注目される理由から、条約の仕組み、日本の対応、そして今後の展望までをわかりやすく解説します。
なぜ今、ウナギの国際取引が問題視されているのか
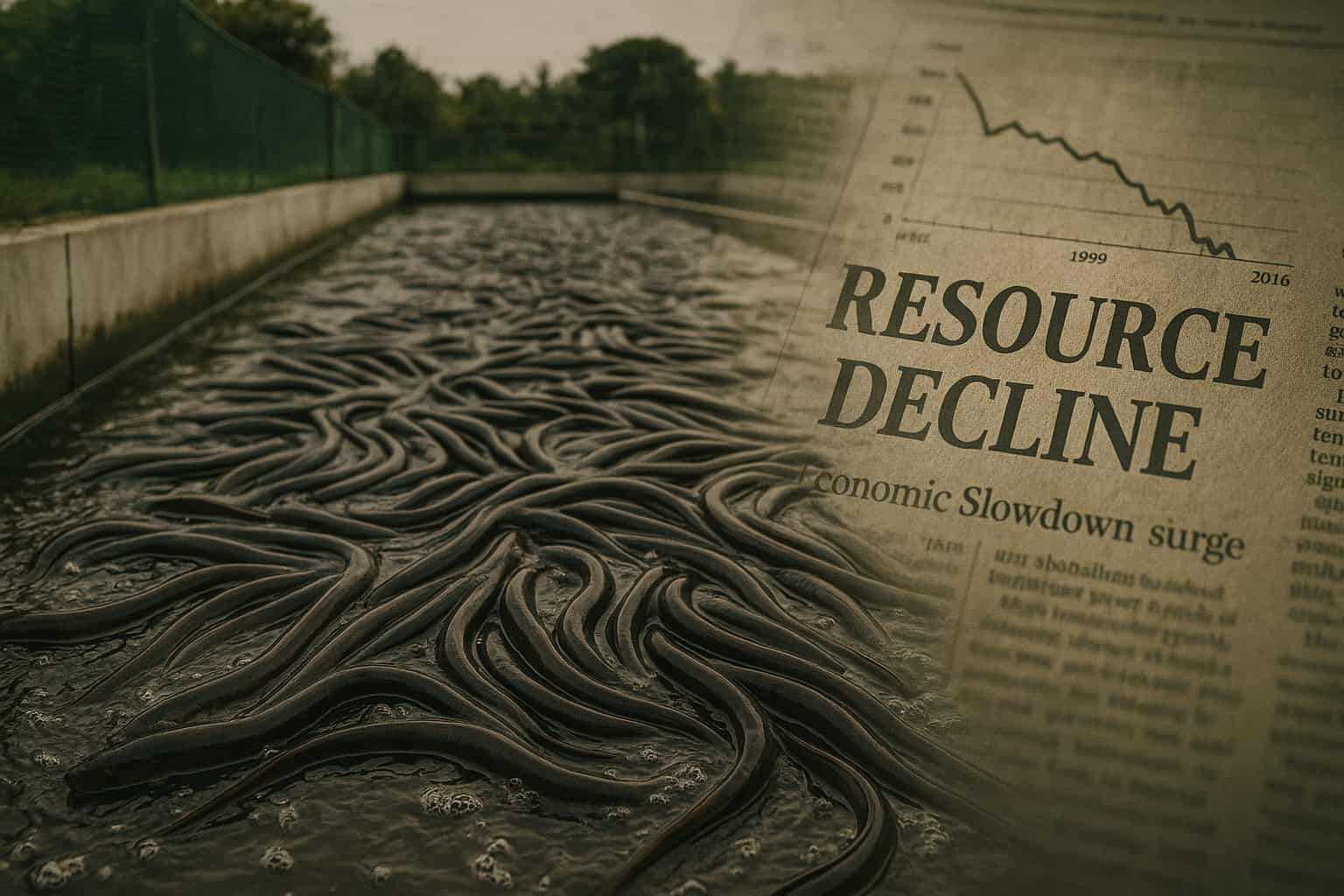
ウナギは長年にわたり、各国で食用として利用されてきましたが、その需要の高まりとともに資源の減少と違法取引の深刻化が進行しています。今回のワシントン条約締約国会議では、ニホンウナギを含むすべてのウナギ属(Anguilla属)を附属書Ⅱに掲載するという提案が注目されています。その背景には、資源保護と国際取引管理の双方に関する危機感があります。
EUによる「ウナギ属全種」規制提案の目的
今回の附属書Ⅱ掲載提案は、ヨーロッパ連合(EU)とホンジュラスによって共同提出されました。提案の内容は、すでに附属書Ⅱに掲載されているヨーロッパウナギ(Anguilla anguilla)を除く、すべてのウナギ属魚類(計18種)を新たに附属書Ⅱに追加するというものです。
この提案がなされた主な理由は以下のとおりです。
- ニホンウナギ、アメリカウナギの個体数が大幅に減少している
- 加工品や稚魚などの国際取引で、種の識別が困難であり、偽装が横行している
- 一部の種だけを規制しても、需要が他の種に流れる「代替消費」が起きる
実際、過去にはヨーロッパウナギが附属書Ⅱに掲載されたことにより、中国や東南アジアを経由した密輸入の増加が確認されており、抜け道の存在が深刻な課題となっています。
資源の悪化とIUCNのレッドリスト評価
ウナギ属の多くは、すでにIUCN(国際自然保護連合)のレッドリストで高リスクのカテゴリに分類されています。
- ヨーロッパウナギ:CR(深刻な危機)
- ニホンウナギ、アメリカウナギ:EN(絶滅危惧種)
ニホンウナギについては、日本、台湾、IUCNのいずれの評価でも絶滅の危険性が高いとされており、保全の必要性が広く認識されています。
ただし、IUCNの評価基準に対して、日本政府(特に水産庁)は異論を唱えており、これが国際社会との科学的認識のギャップを生む要因となっています。
偽装・密輸リスクと「類似種」規定の重要性
ウナギの取引では、外見上の種の判別が極めて困難であることが、取引規制を複雑化させています。特に、シラスウナギ(稚魚)や蒲焼などの加工品においては、見た目から種を特定することは不可能です。
このような状況を受け、ワシントン条約では「類似種(look-alike)」という規定を用いて、対象種の偽装取引を防ぐ目的で、類似したすべての種をまとめて附属書Ⅱに掲載することが可能とされています。
今回の提案も、この「類似種規定」に基づき、ウナギ属全体を対象とする包括的な措置をとることが妥当であるとされました。
以下の表は、主要な3種について、主な分布地域、IUCNの評価、そしてCITESでの掲載状況を整理したものです。
| 種名 | 主な分布地域 | IUCN評価 | CITES掲載状況 |
|---|---|---|---|
| ニホンウナギ | 日本・韓国・台湾など | EN(絶滅危惧種) | 提案中(附属書Ⅱ) |
| アメリカウナギ | 北米東部・カリブ海沿岸 | EN(絶滅危惧種) | 提案中(附属書Ⅱ) |
| ヨーロッパウナギ | ヨーロッパ・北アフリカ | CR(深刻な危機) | 掲載済(附属書Ⅱ:2009〜) |
このように、現在のウナギ取引を取り巻く状況は、単なる絶滅リスクを超えた制度的・構造的なリスクを含んでおり、国際的な規制強化の動きはその対応策のひとつと位置づけられています。
ワシントン条約の仕組みと規制されるとどうなるのか

ワシントン条約(CITES)は、絶滅の恐れがある野生動植物を保護するために、その国際取引を規制することを目的とした国際条約です。1975年の発効以降、180を超える国と地域が加盟しており、輸出国と輸入国の両方が協力して違法取引を防ぐという枠組みをとっています。
今回のウナギ属の規制提案も、このCITESの枠組みに基づいて行われています。では、この条約の仕組みとは具体的にどのようなものなのでしょうか。以下で詳しく見ていきます。
附属書とは何か?ウナギ規制の前提となる分類制度
CITES最大の特徴は、「附属書(Appendix)」と呼ばれるリストに規制対象の種が分類されており、その附属書の種類によって取引の規制レベルが異なる点にあります。附属書は次の3種類に分けられています。
附属書の分類と規制内容
| 附属書 | 種の状態 | 規制内容 | 取引条件 |
|---|---|---|---|
| I | 絶滅のおそれが高い | 商業目的の国際取引は原則禁止 | 科学研究など例外的な目的でのみ許可 |
| II | 絶滅のおそれがある可能性 | 国際取引を管理しなければ危険 | 輸出国による許可書が必要 |
| III | 一部の国が保護を希望している種 | 特定国の要請に基づく規制 | 出所証明書などの書類が必要 |
現在、議論の対象となっているのは「附属書Ⅱ」へのウナギ属全種の掲載です。附属書Ⅱは附属書Ⅰほど厳しくはなく、一定条件を満たせば商業取引が可能ですが、輸出国による許可制度が導入され、国際取引が大きく制限されます。
附属書Ⅱ掲載で何が求められるのか
附属書Ⅱに登録された種については、取引ごとに輸出国が発行する「輸出許可書」が必要となります。許可書が発行されるためには、以下のような条件が求められます。
- その取引が資源に悪影響を与えないこと
- 科学的なデータに基づいて判断されること
- 輸出量や捕獲状況が管理されていること
つまり、条約そのものが科学的根拠と行政手続きに基づいた持続可能な利用を前提としており、許可制度の運用に大きな責任が伴うのです。許可書が出なければ、たとえ合法な取引であっても国際流通は不可能になります。
加工品も対象に——規制の広がりと現実的な背景
今回の規制提案では、ウナギの稚魚(シラスウナギ)や成魚(活鰻)に加え、蒲焼、白焼き、冷凍・真空パックなどの加工品もすべて対象とされています。これは、CITESが「動物そのもの」だけでなく、「その一部や派生製品」も規制の対象とする原則に基づいています。
この点が特に重要なのは、ウナギの国際流通において最も大きな割合を占めるのが加工品だからです。外見で種を特定できないため、偽装や密輸のリスクが高いと判断され、包括的な規制が提案されています。
制度の運用と実効性の課題
附属書Ⅱによる規制は「禁止」ではなく「管理強化」ですが、実際の効果を左右するのは各国の制度運用能力です。
たとえば、
- 科学的な資源評価ができない国
- 違法取引の温床となる中継国
- 許可書を正しく発行しない体制
などが存在すれば、規制は形骸化しかねません。特に今回のウナギ属は、外見での種判別が困難で、密輸を防ぐには検査体制や流通トレースの強化が不可欠となります。
持続可能な取引への転換点としての意味
附属書Ⅱへの掲載は、ウナギの国際取引を一律に否定するものではなく、「合法で持続可能な取引」への転換を促すものです。そのためには、以下のような対応が求められます。
- 科学的データに基づいた資源評価の強化
- 輸出国・輸入国双方の認証体制の整備
- 取引データの透明化と国際的な情報共有
ウナギの未来を守るためには、「禁止」か「自由取引」かの二択ではなく、その中間にあるルールある持続的利用こそが現実的な道といえるでしょう。
日本の立場と業界の懸念——反対の背景を探る

ウナギの国際取引規制に対して、日本政府は一貫して慎重な立場を取っています。とりわけニホンウナギについては、「資源量は十分確保されており、国際取引による絶滅の恐れはない」と主張しており、今回の附属書Ⅱ掲載提案には反対を表明しました。背景には、科学的な評価の相違に加え、輸入依存や価格上昇、密輸増加への懸念といった実務的・経済的要因があります。
水産庁の主張:「資源は十分」「科学的根拠が不十分」
農林水産省や水産庁は、ニホンウナギの資源管理は日本を含む関係国によって適切に行われており、ワシントン条約による国際取引の制限は「時期尚早」だと主張しています。
とりわけ、2025年6月に水産庁が提示した資料では、「ニホンウナギの絶滅確率は0.02%未満」とする未公開の「田中2025」論文を根拠に、「絶滅リスクは無視できる水準にある」と結論づけられていました。この論文は、過去に同庁が引用してきた「Tanaka 2014」の更新版である可能性が高く、漁獲データなどを用いた資源量モデルに基づいて推計が行われています。
一方、IUCNや国際研究者の間では、資源量の実態に対してより厳しい見方がなされており、水産庁の評価とのギャップが生じています。
また、2025年3月に公表された「国際漁業資源の現状」レポートの英語版から一部の文が削除されていたことも問題視されています。これにより、「資源が長期的に減少基調にある」といった表現が海外の読者に届かず、情報の不透明性が指摘されました。
業界関係者の見解:「規制は時期尚早」
業界の中にも、規制強化に対する慎重な声は根強く存在します。全国に300店舗以上を展開する「鰻の成瀬」の山本昌弘社長は、報道インタビューにおいて「ウナギの生態についてはまだ分かっていない部分も多く、今の段階で国際規制に踏み切るのは時期尚早ではないか」と述べています。
また、現場の実務者からは、「仮に附属書Ⅱに掲載された場合、輸入や流通に必要な書類手続きが増え、商品供給に支障が出る」「業者間での価格交渉力に差が出る」といった実務的な負担増への懸念も表明されています。
さらに、規制によって合法的な輸入ルートが制限されれば、密輸ルートへの依存が高まる可能性もあるとされ、業界としては規制の実効性とリスクの両方を慎重に見極めようとしています。
輸入依存と価格への影響、密輸リスク
日本で消費されるウナギの多くは海外からの輸入に依存しています。特に加工品においては、輸入割合が極めて高く、価格や供給の安定性は海外の動向に大きく左右されます。
以下は、2024年時点でのウナギ供給構成を整理した表です。これを見ると、日本のウナギ市場がいかに輸入に依存しているかが明確にわかります。
| 区分 | 国内産割合 | 輸入割合 | 主な輸入先 |
|---|---|---|---|
| シラスウナギ(稚魚) | 約50% | 約50% | 香港(実質は台湾・中国経由) |
| 加工品(蒲焼等) | 約30% | 約70% | 中国(約90%以上) |
日本が消費するウナギの約7割は輸入に依存し、その多くを中国産が占めています。規制が実施されれば、輸出許可書の発行体制や認証の厳格化により、輸入の遅延・供給量の不安定化は避けられません。
中国の貿易構造や輸出制度は、ウナギ供給の先行きを判断する重要な基礎情報となります。

シラスウナギの輸入においては、香港が主な経由地となっていますが、香港では漁が行われていないため、実質的には台湾や中国本土から違法に持ち出された稚魚が流入している疑いがあります。
このような供給構造の中で附属書Ⅱに掲載され、正規の許可書取得が必須となれば、違法な流通に拍車がかかる可能性もあります。とはいえ、現在の段階ですでに密輸品が日本国内で流通している事例も多く、規制強化によって必ずしも新たな問題が生まれるとは限らないという指摘もあります。
つまり、規制によって取引が厳格化されることで、むしろ密輸の監視が強まり、不正流通の是正につながる可能性もあるという見方も存在します。
このように、日本政府や業界は規制案に対して慎重姿勢を取っていますが、その根拠には、資源評価の不一致、取引コストの増加、流通構造の複雑さといった、実に多様な要素が絡み合っています。
養殖構造と国際流通の実態——ウナギビジネスの裏側

ニホンウナギを含むウナギ類は、現在のところ完全養殖が商業ベースで確立されておらず、天然の稚魚(シラスウナギ)を採捕し、養殖して出荷する方法が一般的です。この構造が、国際取引規制に深く関わる重要な要素となっています。
養殖の実態:天然依存と流通の複雑化
日本国内のウナギ養殖では、毎年冬から春にかけてシラスウナギの採捕が行われますが、国内の供給量だけでは養殖業者の需要を賄いきれない年も多く、海外からの輸入に頼る割合が増加しています。
特に2010年代以降、香港経由での稚魚輸入が目立つようになりました。香港自体では稚魚の漁が行われておらず、その多くは台湾や中国本土などから違法に持ち出されたものと見られています。
養殖されたウナギは、日本だけでなく中国、台湾、韓国などの加工業者を通じて蒲焼などに加工され、再び日本に輸入されるというルートが一般的です。このような国際的な養殖・加工・輸出入のサイクルは、以下の図のように整理できます。
| 工程 | 主な国・地域 | 備考 |
|---|---|---|
| 稚魚採捕 | 日本、中国、台湾など | 自国および違法輸出が混在 |
| 稚魚輸出 | 主に香港経由 | 輸出許可の取得状況は不透明 |
| 養殖 | 日本、中国、台湾 | 稚魚の入手経路によって合法性に差 |
| 加工(蒲焼等) | 主に中国(輸出用) | 加工後、日本などに輸出 |
| 輸入(製品) | 日本 | 全体の約7割が中国からの加工品輸入 |
このように、多国間にまたがるサプライチェーンを持つウナギビジネスは、合法・違法の境界があいまいになりやすいという課題を抱えています。
「類似種」規定の意義:見分けにくさが密輸の温床に
ウナギ類の規制において特徴的なのが、「類似種」規定の存在です。ワシントン条約では、外見で区別しにくい種について、規制対象種と似ているものを「類似種」として附属書に掲載することができます。
たとえば、ヨーロッパウナギ(すでに附属書Ⅱ掲載)とニホンウナギ、アメリカウナギは、加工品(蒲焼など)になってしまうと見た目では区別がつきません。また、稚魚の段階でも専門家でなければ判別が難しく、流通段階での種別確認が非常に困難です。
このため、見た目が似ている種を一括で規制しなければ、規制の抜け道になる恐れがあり、今回の提案ではニホンウナギを含むウナギ属すべての掲載が提案されているのです。
この「類似種」規定は、過去にはサメやトカゲ類でも用いられ、効果的な取締手段として機能してきた例があります。ウナギ類においても、種の判別が難しい現状に鑑みると、国際的な監視体制を整える上で有効な手段といえるでしょう。
密輸・IUU漁業の実態とリスク
現時点でも、シラスウナギやウナギ製品の密輸事例は多発しており、既に規制が形骸化しつつある部分もあります。たとえば、ヨーロッパウナギは附属書Ⅱに掲載されていますが、2023年にはオランダの空港で17万匹以上の稚魚が押収された事件が報道されました。
また、日本国内でも、違法に輸入されたシラスウナギが養殖用として流通している可能性が高く、当局の監視体制の強化が求められています。
規制強化によって違法取引が増えることを懸念する声もありますが、現状でも違法取引が蔓延していることを踏まえると、むしろ合法な流通ルートを明確化する規制の方が、透明性の向上につながるという考え方も根強くあります。
国際協調の課題:分断された対応
ウナギは、長距離を回遊する魚種であり、国境を越えた資源としての管理が求められる存在です。しかし、ニホンウナギをめぐっては、日本、中国、韓国、台湾がそれぞれ独自に管理措置を導入しており、国際的な統一ルールが存在しないというのが現状です。
たとえば、各国は養殖に用いるシラスウナギの採捕量について自主的な上限を設けていますが、近年ではこの上限を超えた漁獲が常態化しているとの指摘もあります。
国際取引の規制は、こうした分断された管理体制に対して、国際的な枠組みで歯止めをかける一手と見ることもできます。ワシントン条約による規制は、貿易面からの統制に限られますが、全体として資源の持続可能性を確保するきっかけにもなり得るのです。
ウナギ規制のまとめ
2025年、ワシントン条約の締約国会議で提案された「ウナギ属全種の国際取引規制」は、日本にとって重要な岐路を意味します。ウナギは文化・食・経済の面で深く根づいてきた一方で、長年にわたって資源減少や違法取引といった課題を抱えてきました。
今回の提案は、単に「ウナギが食べられなくなるかもしれない」という表層的な不安にとどまりません。それはむしろ、ウナギを未来に残すために何をすべきかという本質的な問いかけです。
規制が採択された場合、施行は2027年6月が予定されており、稚魚や加工品すべてに輸出許可が求められるようになります。これにより、ウナギ業界は大きな転換期を迎えることになるでしょう。輸入量の減少、価格の高騰、業界の構造改革など、さまざまな影響が懸念されています。
その一方で、今回の議論は「規制する・しない」という二択ではありません。むしろ、科学的で透明性のある資源評価や、国際的な連携による共同管理体制の構築、そして消費者側の選択意識といった、多面的な対応こそが求められています。
これからのウナギとの関わり方は、単なる懐石の話ではありません。自然資源との向き合い方そのものが問われているのです。私たちは、食の豊かさと生物多様性の保全を両立させるために、どのような未来を選ぶべきなのでしょうか。
日本政府は一方で、水産物輸出を重要な経済戦略と位置付けています。ウナギ規制はその流れとも衝突しかねず、持続可能性と輸出促進の両立は今後の最大の課題です。
日本の水産物輸出の現状と課題については、下記の記事で詳しく整理しています。














