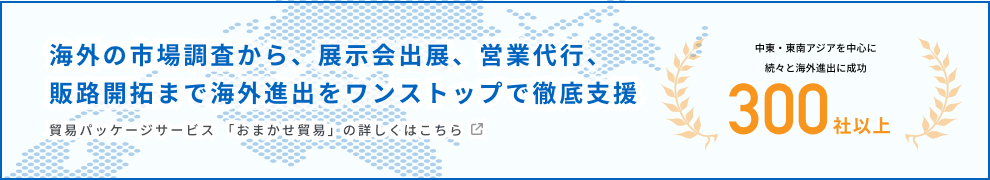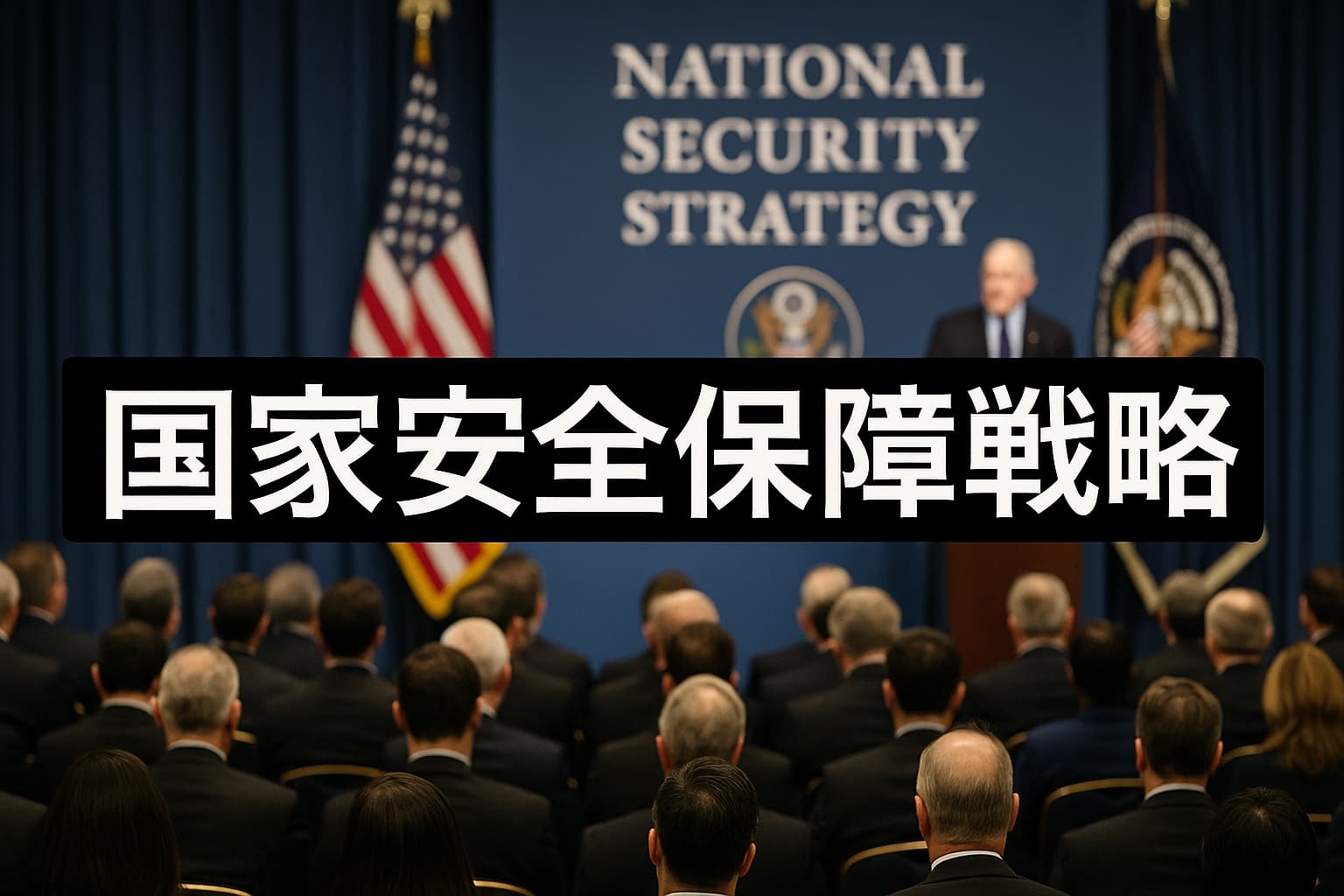抹茶が今、世界中で注目を集めています。アメリカやヨーロッパ、東南アジアでは「MATCHA」という言葉がそのまま通じるほど浸透し、カフェやレストランのメニューに抹茶ラテや抹茶スイーツが並ぶ光景も珍しくありません。
こうした抹茶人気の背景には、日本文化への憧れや関心の高まりに加え、健康志向のライフスタイルの拡大があります。抗酸化作用やカフェインの代替飲料としての評価も後押しし、「伝統 × 健康 × サステナブル」というキーワードで市場は急成長を遂げています。
本記事では、海外での抹茶の受け止められ方や需要動向、そして日本企業が抹茶を輸出・販売するうえで押さえておくべき貿易実務や課題を、統計や実例を交えながら詳しく解説します。
最新の貿易実務・政策動向については、X(旧Twitter)でも随時発信中です。ぜひ @bouekidotcom をフォローして、海外展開に関わる情報をチェックしてください。
海外で進化する抹茶のイメージ——伝統からトレンドへ

抹茶は、単なる日本の伝統飲料としてではなく、海外で「ヘルシーで洗練されたライフスタイルの象徴」として再解釈されています。このセクションでは、抹茶が海外でどのようなイメージを持たれているかを文化・消費の両面から掘り下げ、いま抹茶ビジネスが注目される理由を明らかにします。
海外での「MATCHA」という言葉の浸透
抹茶は今や「MATCHA」として世界の共通語になりつつあります。とくに欧米では、緑色のパウダーを使った飲料やスイーツが、健康志向の高い消費者層を中心に支持を得ています。以前は「Green Tea」として一括りにされていた日本の茶文化ですが、抹茶はその中でも独自の地位を確立し、「粉末状で飲む」「泡立てる」「鮮やかな緑色」といった特徴が「特別感」や「本物志向」を引き出す要素として評価されています。
SNSやYouTubeなどのメディアでも「MATCHA LATTE」や「MATCHA RECIPE」といったコンテンツが多数拡散され、若年層にも浸透しています。特に英語圏では、日本語の音そのままに「Matcha」という表記で受け入れられ、健康・伝統・オシャレといった複数の価値を含む新しいコンセプトとして広がっています。
抹茶メニューの広がりと文化的解釈
抹茶が海外で定着している理由の一つに、その応用の広さがあります。カフェでは抹茶ラテ、アイスクリーム、クッキーなどへの利用が一般的となり、抹茶のほろ苦さや鮮やかな色合いが商品価値を高めています。ヘルシーなイメージと同時に「ジャパニーズ・トラディショナル(日本の伝統)」という文脈で語られることが多く、日本の文化的背景そのものが付加価値となっています。
とくに欧米のマーケットでは、単なる食品ではなく「文化体験」としての抹茶に魅力を感じる消費者が増えています。京都の茶道体験や、禅との結びつきなどが紹介されることで、抹茶のブランドイメージはますます強化されています。これは日本産であること、そして日本のストーリーをまとっていることが、輸出商品として大きな武器になることを意味します。
なぜ今、抹茶ビジネスなのか
今、抹茶ビジネスが世界中で注目されているのは、いくつかの社会的背景と市場の動きが重なっているからです。
まず、世界的な健康志向の高まりがあります。砂糖を控え、カフェインの摂取を見直す動きの中で、抹茶はその代替として理想的なポジションを占めています。
次に、消費者の嗜好が「ストーリーのある商品」へと移っていることも大きな要因です。日本の伝統や精神性を背景にもつ抹茶は、その期待に応える力を持っています。
さらに、サステナビリティへの関心が高まる中で、農薬管理やトレーサビリティを重視した日本の茶葉生産方式は、他国との差別化要素として評価されています。これらの要素が重なり合い、「今こそ抹茶ビジネスを始めるべきタイミング」だと言えます。
国・地域別に見る抹茶の消費イメージとトレンド
| 国・地域 | 抹茶の一般的なイメージ | よく見られる商品例 | 消費層の傾向 |
|---|---|---|---|
| アメリカ | スーパーフード、カフェトレンド | 抹茶ラテ、抹茶クッキー、スムージー | 健康志向の若者・女性中心 |
| フランス | 高級感、日本文化、美容効果 | 抹茶マカロン、抹茶チョコレート | 菓子愛好家、美容志向の30〜40代 |
| シンガポール | 美容・健康・日本トレンド | 抹茶アイス、抹茶ミルクティー | 若年層から高所得層まで幅広い |
| オーストラリア | サステナブル・ビーガン対応食品 | 抹茶プロテインバー、抹茶ヨーグルト | フィットネス志向の中間層 |
このように、抹茶は世界中でそれぞれ異なる文脈で消費されながらも、共通して「健康・文化・品質」という価値に支えられて拡大しています。
健康志向と抹茶——海外で評価される栄養価と効能

抹茶が海外市場で注目を集める大きな理由のひとつが、その健康効果です。栄養価の高さに加え、カフェイン飲料の代替としても活用される抹茶は、健康意識の高い消費者にとって魅力的な選択肢となっています。
本セクションでは、抹茶の主な成分とその効能を紹介し、海外でのマーケティングや消費者ニーズとの関連性を解説します。
スーパーフードとしての栄養価
抹茶は、緑茶の一種でありながらも、茶葉をまるごと粉末にして摂取するという点で、他のお茶とは一線を画しています。このため、通常の煎茶と比較しても、栄養素をより効率的に取り込める特徴があります。代表的な栄養成分には、カテキン、テアニン、食物繊維、クロロフィル、ビタミンA・C・Eなどが含まれており、免疫力の強化や美容効果が期待されています。
特に欧米では、これらの成分がもたらす機能性に注目が集まり、「MATCHA is a superfood(抹茶はスーパーフードだ)」という認識が定着しつつあります。現地の健康食品店やオーガニックスーパーでは、抹茶パウダーがプロテインやチアシードと並んで陳列されることも珍しくありません。
抹茶とコーヒーの代替関係
健康志向が高まるなかで、コーヒーの代替として抹茶を選ぶ人が増えています。コーヒーには強い覚醒作用がある一方で、不安感や胃の不調を訴える人も多く、そうした消費者にとって、抹茶は穏やかなエネルギーを提供する飲料として魅力的です。
抹茶に含まれるカフェインは、テアニンとともに作用することで、リラックスと集中を両立させる効果があるとされており、「calm energy(穏やかなエネルギー)」というコンセプトで広くマーケティングされています。このバランスの取れた刺激が、ヨガ愛好者やクリエイティブ業界の人々、IT技術者など、精神的集中力が求められる層に受け入れられているのです。
医療・美容・スポーツ分野への展開
抹茶はその機能性の高さから、食品以外の分野でも注目を集めています。美容分野では、抗酸化作用を活かしたスキンケア製品や、抹茶を使ったサプリメントが登場しており、「インナーケア」としての市場が形成されています。
また、スポーツ栄養の分野では、トレーニング後の回復ドリンクやプロテインバーに抹茶が活用される事例が増えており、「植物性・ナチュラル・高機能」の3拍子を兼ね備えた素材として重宝されています。とくに欧州では、アスリートやベジタリアン向け製品に抹茶を配合する動きが進んでおり、機能性表示やエビデンスに基づいた商品開発が進行中です。
抹茶の主要成分と健康効果
| 成分名 | 期待される健康効果 | 海外での訴求ポイント |
|---|---|---|
| カテキン | 抗酸化作用、抗菌作用、脂肪燃焼促進 | エイジングケア、ダイエットサポート |
| テアニン | リラックス作用、集中力維持 | ストレス緩和、マインドフルネスとの親和性 |
| カフェイン | 覚醒作用、代謝促進 | コーヒーの代替としての自然なエネルギー補給 |
| クロロフィル | デトックス、消臭効果、抗炎症作用 | 植物性ナチュラル成分としての安全・安心イメージ |
| ビタミン類 | 免疫機能強化、美容効果 | 自然由来の美容成分として高い評価(特に女性層) |
抹茶の成分や効能が持つ魅力は、単なる「健康によい」という枠を超え、ライフスタイルやセルフケアの中に自然に組み込まれる価値として認識されています。こうした観点からも、抹茶は今後、食品だけでなく、複数分野にまたがる「マルチユースな輸出商品」として、より大きな可能性を秘めているといえるでしょう。
データで読み解く抹茶の海外市場——成長する需要と商機

抹茶は今やグローバルな市場で本格的な成長フェーズに入りつつあります。単なる一過性のブームではなく、各国の消費動向や輸出実績からもその拡大傾向は明確です。
本セクションでは、抹茶の国際市場における数値的な成長をデータから読み解き、今後のビジネスチャンスや中長期的な展望について考察します。
市場規模の拡大
抹茶を含むグリーンティー関連製品の世界市場は、近年急速な成長を遂げています。とくにアメリカや欧州、東南アジアを中心に、「機能性飲料」「ヘルシースイーツ」「ヴィーガン対応食品」などのカテゴリーで需要が伸びており、市場の裾野は着実に広がっています。
日本政府や民間調査機関のデータによれば、2025年時点での世界の抹茶市場規模は700億円超が見込まれており、今後も年平均7〜8%の成長が続くと予測されています。市場は健康志向、エシカル消費、サステナビリティといった潮流に合致しており、今後も安定した需要が期待されます。
国別の需要傾向と輸入データ
日本からの抹茶輸出先は、アメリカ、台湾、ドイツ、オーストラリア、シンガポールなどが主要市場となっています。国ごとに抹茶の利用形態や消費トレンドには差があり、たとえばアメリカでは飲料用・菓子用としての需要が多く、台湾や香港ではより高品質な茶道用抹茶の需要も存在します。
以下の表は、過去数年の輸出額と主な消費国の傾向を整理したものです。
| 年度 | 輸出総額(抹茶) | 主な輸出先 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2019年 | 約32億円 | アメリカ、台湾、香港 | 抹茶スイーツ人気が成長要因 |
| 2021年 | 約42億円 | アメリカ、シンガポール | ヘルシー食品としての需要が拡大 |
| 2024年推定 | 約60億円超 | アメリカ、欧州(仏・独) | サステナブル志向・高級市場開拓が進展 |
※出典:日本貿易振興機構(JETRO)等を基に再構成
製品の多様化と高付加価値化の流れ
抹茶の海外市場では、単純な「粉末茶」としてではなく、多様な形で商品化される傾向が強まっています。たとえば:
- 抹茶入りのビーガンプロテインバー
- 抹茶香る美容サプリメント
- 抹茶を使ったクラフトスピリッツやリキュール
- 機能性食品としての抹茶グラノーラ
このように、抹茶は単体商品としてだけでなく、他のカテゴリーと組み合わせることで高付加価値な商品として再定義されています。これは中小企業やスタートアップにとっても、独自のブランド構築や差別化戦略において好機と言えるでしょう。
海外展開で意識すべき中長期戦略
一時的な輸出や単発的な注文に終始するのではなく、海外市場で持続的に成長するためには、中長期的な視点での事業戦略が不可欠です。とくに以下のような点に注目することが重要です。
- 現地ニーズに即した製品設計(甘さ・色味・機能性の調整)
- ターゲット市場の絞り込みとパートナー戦略
- ブランドストーリーの構築と差別化
- 安定供給体制の構築とロジスティクスの最適化
抹茶は「どこでも売れる」商品ではなく、「売り方」が問われる素材です。市場ごとの食文化、消費習慣、宗教的背景などを踏まえた展開戦略が、長期的な成功を左右します。
日本の強みを活かすには:品質 × 文化ストーリー
抹茶の競合品は世界中に存在しますが、「日本産抹茶」には他にはない強みがあります。それは品質保証と文化的背景です。
日本の抹茶は、ISOやHACCPなどの品質基準を満たした生産体制が確立されており、海外のバイヤーからも「安全で信頼できる原料」として評価されています。また、京都や静岡などの産地ブランドや、茶道・禅といった文化的ストーリーを絡めた商品提案は、価格以上の価値を生み出します。
「これは日本から来た、特別な抹茶である」というメッセージを明確に伝えることができれば、価格競争に巻き込まれずに済むだけでなく、現地でのロイヤルカスタマーを生み出すきっかけにもなります。
抹茶のような高付加価値食品を海外に展開するには、収益化に向けた事業設計や戦略的なステップが求められます。

このように、抹茶の海外市場は単なる流行ではなく、継続的な成長基盤を持つ分野として拡大を続けています。
抹茶を海外へ輸出するための基本知識と実務ポイント

抹茶を海外で販売するには、魅力的な商品開発だけでなく、貿易に関する正確な知識と準備が不可欠です。このセクションでは、輸出に関わる基本的な実務フローから、関税や保存方法、各国の規制など、抹茶特有の注意点を含めて実践的に解説します。
輸出の流れと基本的な実務知識
抹茶の輸出を行うには、以下のような一般的な手順に沿って進める必要があります。
- 輸出先国の食品規制調査
- 抹茶製品の成分表示やラベルの調整
- 輸出許可や検疫・衛生証明書の取得(必要国のみ)
- インボイス・パッキングリスト・B/Lなどの貿易書類の準備
- 輸出申告・通関手続き
- 輸送(航空または海上)と現地通関
抹茶は食品カテゴリーに該当するため、保存方法や輸送中の温湿度管理にも細心の注意が求められます。また、抹茶は光・酸素・湿気に弱く、輸送中に品質が変化しやすいため、遮光・脱酸素・防湿包装などの対応が基本です。
関税分類(HSコード)と各国の規制
抹茶は国際的には「緑茶」に分類され、HSコードは一般的に0902.30(緑茶、粉末)に該当します。ただし、抹茶に糖類や他成分を加えた場合は別コードになるため、商品仕様に応じて事前に分類確認を行うことが重要です。
また、国によっては「抹茶=伝統食品」としてではなく、「加工食品」「機能性食品」として分類されることもあるため、輸入規制の対象が変わる場合があります。
| 国・地域 | HSコード | 一般関税率(参考) | 主な規制・注意点 |
|---|---|---|---|
| アメリカ | 0902.30 | 0%(EPA対象) | FDAの食品表示基準、ラベルに厳格な規定あり |
| EU(欧州) | 0902.30 | 約6% | 残留農薬基準が厳しい、原産地証明が求められる |
| シンガポール | 0902.30 | 無税 | HACCPまたはISO等の衛生基準を満たす必要あり |
| 中国 | 0902.30 | 約15% | CIQ認証、成分表示、食品登録制度に対応が必要 |
輸送と品質管理の注意点
抹茶は高品質であるほど、香りや鮮度が重要視されるため、物流段階での劣化防止が必須です。とくに抹茶の色味(鮮やかな緑)と香りは、消費者評価に直結するポイントであり、これを保つには以下の対策が必要です。
- アルミパック+脱酸素剤による個包装
- 冷蔵または定温コンテナでの輸送(高級品の場合)
- 製造日・賞味期限・保存方法の明確な表示
また、販売形態によっては、バルク輸出後に現地で小分け・充填を行う方式を選ぶことで、関税の圧縮やローカライズにも対応しやすくなります。
小ロット輸出と現地パートナーの活用
抹茶ビジネスを初めて海外展開する際には、いきなり大規模な輸出を目指すのではなく、小ロット・テストマーケティングから始めるのが現実的です。以下のような手法が有効です。
- 海外の展示会やバイヤー向けサンプル出展
- 越境ECや海外プラットフォームでのテスト販売
- 商社や海外販路開拓代行の活用
現地事情に精通したパートナーと連携しながら、規制対応や物流の課題をクリアしていくことが、長期的なビジネス構築につながります。
抹茶のような加工食品の輸出には、食品特有の規制や手続きが関わります。さらに詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

抹茶を海外に届けるには、製品の魅力を伝えるだけでなく、制度や物流面での信頼性も担保する必要があります。これらの準備を的確に行うことが、現地市場での継続的な展開につながります。
まとめ
抹茶は、健康志向の高まりや日本文化への関心を背景に、海外市場で確かな存在感を示しています。アメリカやヨーロッパ、アジア各国では、「MATCHA」という言葉がライフスタイルの一部として定着しつつあり、その需要は年々拡大しています。抹茶の持つ栄養価やリラックス効果はもちろん、京都や茶道といった文化的背景が商品に深みを与え、価格以上の価値を生み出しています。
こうした可能性を最大限に活かすには、単なる輸出ではなく、品質・ストーリー・現地ニーズに即した展開が求められます。加えて、関税や規制への対応、現地パートナーとの連携といった実務面の準備も欠かせません。抹茶を通じて日本の魅力を海外へ広めるには、戦略的な視点と継続的な努力が不可欠です。
海外展開を検討している企業や個人事業者の方は、実務の前に専門家に一度相談してみることをおすすめします。
海外販路開拓をゼロから始めるなら『おまかせ貿易』
『おまかせ貿易』は中小企業が、低コストでゼロから海外販路開拓をするための"貿易代行サービス"です。大手商社ではなしえない小規模小額の貿易や、国内買取対応も可能です。是非一度お気軽にお問い合わせください。